わかってない奴がわかったつもりで書き留める超準解析(その20) [数学]
【超準解析について生半可な知識しかない僕が、わかったつもりの内容をちょっとずつ書き留めていきます。不正確な内容や誤りもあることをご承知ください。】
(20) 直積空間とカントール空間
本記事では、直積空間を超準的に扱うことを考えます。
1. 直積空間のモナド
$I$ を添字集合とする集合族 $\{ \, X_i \, \}_{i \in I}$ があるとき、直積集合 $\prod_{i \in I} X_i$ が定まります(超冪を構成した時に用いた $I$ とは無関係です)。これは、$I$ から $\bigcup_{i \in I} X_i$ への写像 $x$ のうち、
\begin{equation*}
\forall i \in I \,( x(i) \in X_i )
\end{equation*}
をみたすものの全体です。特に $X_i$ が全て同じ $X$ の場合は、$\prod_{i \in I} X$ は $I$ から $X$ への写像の全体となり、本記事ではこれを ${}^IX$ で表します( $X^I$ で表す流儀もあります)。
以下では $\prod_{i \in I} X_i$ を簡単に $\hat{X}$ とおいて、$\hat{X}$ の超準モデル ${}^*\hat{X}$ について考えます。
一般に、集合 $W$ の全ての元が集合 $X$ から集合 $Y$ への写像であるとき、写像の定義より
\begin{equation*}
\forall w \in W \, ( \forall z \in w \, \exists x \in X \, \exists y \in Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) \land \forall x \in X \, \exists ! y \in Y \, ( \langle x, y \rangle \in w ) )
\end{equation*}
が成り立つので、移行原理より、
\begin{equation*}
\forall w \in {}^*W \, ( \forall z \in w \, \exists x \in {}^*X \, \exists y \in {}^*Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) \land \forall x \in {}^*X \, \exists ! y \in {}^*Y \, ( \langle x, y \rangle \in w ) )
\end{equation*}
が成り立ち、従って ${}^*W$ の全ての元は集合 ${}^*X$ から集合 ${}^*Y$ への写像になります。そこで、$\hat{X}$ の元は $I$ から $\bigcup_{i \in I} X_i$ への写像なので、${}^*\hat{X}$ の元は ${}^*I$ から ${}^*(\bigcup_{i \in I} X_i)$ への写像です。任意の $i \in I$ に対して
\begin{equation*}
\forall x \in \hat{X} \,( x(i) \in X_i )
\end{equation*}
が成り立つので、移行原理より任意の $i \in I$ に対して
\begin{equation} \tag{1}
\forall x \in {}^*\hat{X} \,( x(i) \in {}^*X_i )
\end{equation}
が成り立ちます。
ここで、各 $X_i$ が開集合族 $\mathcal{O}_i$ によって位相空間となっているとすると、直積集合 $\hat{X}$ の部分集合の族
は $\hat{X}$ の開基の条件を満たすので、これによって $\hat{X}$ の位相(直積位相)が定まります。このとき、モナドについて次の定理が成立します。
(証明)
($\rightarrow$ の証明)ある $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ が $\lnot ( \forall i \in I \, ( u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) ) )$ をみたすと仮定して矛盾を導く。このとき $\exists i \in I \, ( u(i) \notin \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) )$ であるから、これをみたす $i$ をひとつ取って $i_0$ とおく。$u(i_0) \notin \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0))$ だから、$X_{i_0}$ における $x(i_0)$ の近傍 $A_{i_0}$ で $u(i_0) \notin {}^*A_{i_0}$ となるものがとれる。$i \neq i_0$ に対して $A_i = X_i$ として $\hat{A} = \prod_{i \in I} A_i$ とおくと、$\hat{A}$ は $\hat{X}$ における $x$ の近傍になるから、$u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ より $u \in {}^*\hat{A}$ である。しかし $\forall z \in \hat{A} \, ( z(i_0) \in A_{i_0} )$ と移行原理より $\forall z \in {}^*\hat{A} \, ( z(i_0) \in {}^*A_{i_0} )$ だから、$u(i_0) \in {}^*A_{i_0}$ でなければならず、矛盾を生じる。
($\leftarrow$ の証明)ある $u \in {}^*\hat{X}$ が $\forall i \in I \, ( u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) )$ かつ $u \notin \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ と仮定して矛盾を導く。このとき $\hat{X}$ における $x$ の近傍 $\hat{A}$ で $u \notin {}^*\hat{A}$ となるものがとれる。直積位相の定義から、$\hat{A} \supseteq \hat{B} = \prod_{i \in I} B_i$ で各 $B_i$ は $x(i)$ の開近傍、かつ有限個の $i$ を除き $B_i = X_i$ となるような $\hat{B}$ がある。その有限個の $i$ を $i_1, i_2, \cdots , i_n$ とおくと、
\begin{equation*}
\forall z \in \hat{X} \, ( z \in \hat{B} \leftrightarrow z(i_1) \in B_{i_1} \land z(i_2) \in B_{i_2} \land \cdots \land z(i_n) \in B_{i_n} )
\end{equation*}
であり、移行原理より、
\begin{equation*}
\forall z \in {}^*\hat{X} \, ( z \in {}^*\hat{B} \leftrightarrow z(i_1) \in {}^*B_{i_1} \land z(i_2) \in {}^*B_{i_2} \land \cdots \land z(i_n) \in {}^*B_{i_n} )
\end{equation*}
である。一方、$\forall i \in I \, ( u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) )$ かつ各 $B_i$ が $x(i)$ の近傍であることから、
\begin{equation*}
u(i_1) \in {}^*B_{i_1} \land u(i_2) \in {}^*B_{i_2} \land \cdots \land u(i_n) \in {}^*B_{i_n}
\end{equation*}
これより $u \in {}^*\hat{B} \subseteq {}^*\hat{A}$ となって $u \notin {}^*\hat{A}$ と矛盾する。□
この定理から、特に $I$ が有限集合のときには次が成立します(第19回【補題1】と数学的帰納法を用いても証明できます)。
(証明)$I$ が有限集合のときは、${}^*I = I$ かつ ${}^*(\bigcup_{i \in I} X_i) = \bigcup_{i \in I} {}^*X_i$ であるから、${}^*\hat{X}$ の元は $I$ から $\bigcup_{i \in I} {}^*X_i$ への写像である。従って【定理1】より$(2)$が成り立つ。□
2. 直積空間の諸性質
【定理1】を使うと、位相空間におけるいくつかの性質が直積空間にも引き継がれることが機械的に証明できます。まずは閉集合から。
(証明)$\hat{A} = \prod_{i \in I} A_i$ とおく。
$\hat{A}$ が閉集合でないと仮定すると、第17回【定理3】 ii) より $\mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap {}^*\hat{A} \neq \emptyset$ となる $x \in \hat{X} \setminus \hat{A}$ が存在する。$x \notin \hat{A}$ だから、ある $i_0 \in I$ について $x(i_0) \notin A_{i_0}$ である。一方、ある $u \in {}^*\hat{X}$ に対して $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap {}^*\hat{A}$ であるから、【定理1】より $u(i_0) \in \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0))$ である。さらに$(1)$を導いた移行原理を同様に $\hat{A}$ に適用すると $u(i_0) \in {}^*A_{i_0}$ がいえるから、$u(i_0) \in \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap {}^*A_{i_0}$ より $\mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap {}^*A_{i_0} \neq \emptyset$ である。$A_{i_0}$ は閉集合で $x(i_0) \in X_{i_0}$ だから、第17回【定理3】 ii) より $x(i_0) \in A_{i_0}$ となり、矛盾を生じる。□
なお、開集合の直積は必ずしも開集合にはなりません。
次にコンパクト性について。
(証明)任意に $u \in {}^*\hat{X}$ をとる。任意の $i \in I$ に対して $u(i) \in {}^*X_i$ であり、$X_i$ がコンパクトだから、第17回【定理5】よりある $x_i \in X_i$ に対して $u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x_i)$ となる。$\forall i \in I \, (x(i) = x_i)$ となるように $x \in \hat{X}$ を定めると、
\begin{equation*}
\forall i \in I \, ( u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) )
\end{equation*}
であるから、【定理1】より $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ である。従って再び第17回【定理5】より $\hat{X}$ はコンパクトである。□
同様にして、分離公理に関する次の定理も証明できます。
(証明)
i) $\hat{X}$ が $\mathrm{T}_1$ でないと仮定する。第17回【定理4】 i) より、$x \neq y \land y \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ となる $x,y \in \hat{X}$ が存在する。$x \neq y$ だから、ある $i_0 \in I$ に対して $x(i_0) \neq y(i_0)$ となるが、$x(i_0), y(i_0) \in X_{i_0}$ かつ $X_{i_0}$ が $\mathrm{T}_1$ だから、第17回【定理4】 i) より $y(i_0) \notin \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0))$ である。一方、$y \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ と【定理1】より $y(i_0) \in \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0))$ が従うから、矛盾を生じる。
ii) $\hat{X}$ が $\mathrm{T}_2$ でないと仮定する。第17回【定理4】 ii) より、$x \neq y \land \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap \mathrm{monad}_{\hat{X}}(y) \neq \emptyset$ となる $x,y \in \hat{X}$ が存在する。$x \neq y$ だから、ある $i_0 \in I$ に対して $x(i_0) \neq y(i_0)$ となるが、$x(i_0), y(i_0) \in X_{i_0}$ かつ $X_{i_0}$ が $\mathrm{T}_2$ だから、第17回【定理4】 ii) より $\mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(y(i_0)) = \emptyset$ である。一方、$\mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap \mathrm{monad}_{\hat{X}}(y) \neq \emptyset$ より $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap \mathrm{monad}_{\hat{X}}(y)$ となる $u \in {}^*\hat{X}$ が存在し、【定理1】より $u(i_0) \in \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(y(i_0))$ が従うから、$\mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(y(i_0)) \neq \emptyset$ となって矛盾を生じる。□
また、連続写像に関する定理を用いると、次が証明できます。
(証明)任意に $x \in \hat{X}$ と $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ をとる。任意に $i \in I $ をとると、【定理1】より $u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i))$ である。一方、
\begin{equation*}
\forall z \in \hat{X} \, ( p_i(z) = z(i) )
\end{equation*}
と移行原理より、
\begin{equation*}
\forall z \in {}^*\hat{X} \, ( {}^*p_i(z) = z(i) )
\end{equation*}
であるから、${}^*p_i(u) = u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) = \mathrm{monad}_{X_i}(p_i(x))$ となり、第19回【定理2】より $p_i$ は $\hat{X}$ で連続である。□
どの性質も、極めて機械的に証明できることがわかります。
3. カントール空間
本節の議論の応用例として、カントール空間について考察してみます。
自然数の全体 $\mathbb{N}$ から$2$元集合 $\{ \, 0, 1 \, \}$(この集合を $2$ で表します) への写像の全体 ${}^{\mathbb{N}}2 \, ( \, = \prod_{i \in \mathbb{N}} 2 \, )$ を考え、$2$ に離散位相を入れて ${}^{\mathbb{N}}2$ を直積位相空間と考えます。明らかに $2$ はコンパクトだから、【定理4】(チコノフの定理)より ${}^{\mathbb{N}}2$ もコンパクトです。一方、区間 $[ 0, 1 ]$ に属する実数のうち$3$進法無限小数表記で$0$と$2$だけしか現れないようなものの全体 $\mathcal{C}$ は「カントール集合」と呼ばれますが(下図を参照)、これを$1$次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}$ の部分位相空間と考えると、$\mathbb{R}$ において有界閉集合なのでこれもコンパクトです。これら ${}^{\mathbb{N}}2$ と $\mathcal{C}$ は実は同相であり、どちらも「カントール空間」と呼ばれる位相空間の一つです。このことを以下で超準的手法を用いて証明します。
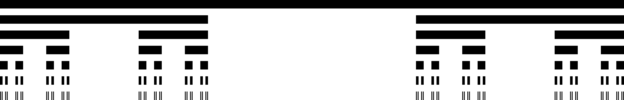
$x \in {}^{\mathbb{N}}2$ に対し、無限級数 $\displaystyle \sum_{i = 0}^\infty 2 x(i) / 3^{i+1}$ は $\mathbb{R}$ 内で収束するので、その和となる実数値を対応させる写像を $f$ とおくと、$f$ は ${}^{\mathbb{N}}2$ から $\mathcal{C}$ への全単射になります。従ってこの $f$ が連続写像であることを証明すれば、${}^{\mathbb{N}}2$ がコンパクト、$\mathbb{R}$ がハウスドルフ(従って $\mathcal{C}$ もハウスドルフ)なので、第19回【定理6】によって ${}^{\mathbb{N}}2$ と $\mathcal{C}$ が同相であることが示されます。第19回【定理2】を使ってこれを示すのですが、その概略は次のとおりです。
任意に $x \in {}^{\mathbb{N}}2$ をとり、その $x$ に対して任意に $u \in \mathrm{monad}_{{}^{\mathbb{N}}2}(x)$ をとります。$u \in {}^*( {}^{\mathbb{N}}2 )$ なので $u$ は ${}^*\mathbb{N}$ から $2 \, ( ={}^*2 )$ への写像であり、$i \in \mathbb{N}$ に対しては【定理1】より($2$ には離散位相が入るから) $u(i) \in \mathrm{monad}_2(x(i)) = \{ x(i) \}$ なので $u(i) = x(i)$ になります。この $u$ に対する ${}^*f(u)$ は超実数体 ${}^*\mathbb{R}$ における無限級数の和として $\displaystyle {}^*f(u) = {}^*\sum_{i = 0}^\infty 2 u(i) / 3^{i+1}$ となるので、その標準部分は実数体 $\mathbb{R}$ における無限級数の和として
\begin{equation} \tag{3}
\mathrm{st}({}^*f(u)) = \sum_{i = 0}^\infty 2 u(i) / 3^{i+1} = \sum_{i = 0}^\infty 2 x(i) / 3^{i+1} = f(x)
\end{equation}
となります。従って第18回【定理1】より ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_\mathbb{R}(x) \cap {}^*\mathcal{C} = \mathrm{monad}_\mathcal{C}(x)$ となるので、第19回【定理2】より $f$ は任意の $x \in {}^{\mathbb{N}}2$ で連続となり、証明が完了します。
この概略の最後の部分(「超実数体 ${}^*\mathbb{R}$ における無限級数の和」以降)は少々直感的にすぎるので、もう少し精密に考えてみます。$z \in {}^{\mathbb{N}}2$ に対する無限級数 $\displaystyle \sum_{i = 0}^\infty 2 z(i) / 3^{i+1}$ は常に $f(z)$ に収束するので、
\begin{equation} \tag{4}
\forall z \in {}^{\mathbb{N}}2 \, \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \exists n \in \mathbb{N} \, \forall k \in \mathbb{N} \, ( k \ge n \to \left| f(z) - \sum_{i = 0}^k 2 z(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon)
\end{equation}
が成り立ちます( $\mathbb{R}^+$ は正実数の全体)。すると移行原理によって、
\begin{equation} \tag{5}
\forall z \in {}^*( {}^{\mathbb{N}}2 ) \, \forall \epsilon \in {}^*\mathbb{R}^+ \, \exists n \in {}^*\mathbb{N} \, \forall k \in {}^*\mathbb{N} \, ( k \ge n \to \left| {}^*f(z) - {}^*\sum_{i = 0}^k 2 z(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon)
\end{equation}
が成り立ちます。そこで $u \in {}^*( {}^{\mathbb{N}}2 )$ に対して任意に正実数 $\epsilon$ をとり、$\mathbb{R}$ における無限級数 $\displaystyle \sum_{i = 0}^\infty 2 u(i) / 3^{i+1}$ の和を $s$ とおくと、$(4)$より十分大きな自然数 $m$ をとると、
\begin{equation*}
\left| s - \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon
\end{equation*}
が成り立ち、また$(5)$より十分大きな超自然数 $n ( > m)$ をとると、
\begin{equation*}
\left| {}^*f(u) - {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon
\end{equation*}
が成り立ちます。そして、
\begin{eqnarray*}
\left| {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} - \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} \right| &=& {}^*\sum_{i = m + 1}^n 2 u(i) / 3^{i+1} \le {}^*\sum_{i = m + 1}^n 2 / 3^{i+1} = \frac{1}{3^{m+1}}-\frac{1}{3^{n+1}} \\
&<& \frac{1}{3^{m+1}}
\end{eqnarray*}
であることから、$m$ を十分大きくとると、
\begin{equation*}
\left| {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} - \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon
\end{equation*}
となるようにできます。これらより、
\begin{eqnarray*}
&&\left| {}^*f(u) - s \right| \\
&\le& \left| {}^*f(u) - {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} \right| + \left| {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} - \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} \right| + \left| \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} -s \right| \\
&<& 3 \epsilon
\end{eqnarray*}
となり、$\epsilon \in \mathbb{R}^+$ は任意なので $\left| {}^*f(u) - s \right| \approx 0$ すなわち $\mathrm{st}({}^*f(u)) = s$ が成り立ちます。これで証明中の($3$)の最初の等号部分が厳密に示されました。
以上で、少し回りくどかったですが、超準的手法を用いて2種類のカントール空間 ${}^{\mathbb{N}}2$ と $\mathcal{C}$ が同相であることを示すことができました。
注意すべきは、「 ${}^{\mathbb{N}}2$ の元は $0$ または $1$ の無限列なので、2進法の無限小数と対応するから、${}^{\mathbb{N}}2$ と実数の区間 $[ 0, 1 ]$ が同相になるのではないのか?」と早とちりしてはいけないということです。$x \in {}^{\mathbb{N}}2$ に無限級数 $\displaystyle \sum_{i = 0}^\infty x(i) / 2^{i+1}$ を対応させると、例えば2進法無限小数 $0.011111 \cdots$ は $0.100000 \cdots$ と実数として等しいので、この対応では ${}^{\mathbb{N}}2$ と $[ 0, 1 ]$ が1対1になりません。一方、先ほどの証明の方法で ${}^{\mathbb{N}}2$ の元に3進法無限小数を対応させると、例えば $0.022222 \cdots = 0.100000 \cdots$ ですが、後者は $1$ を含むので ${}^{\mathbb{N}}2$ の元に対応せず、従ってこちらの対応だと ${}^{\mathbb{N}}2$ と $\mathcal{C}$ が1対1になるのです。
(続く)(前記事)(目次)
(20) 直積空間とカントール空間
本記事では、直積空間を超準的に扱うことを考えます。
1. 直積空間のモナド
$I$ を添字集合とする集合族 $\{ \, X_i \, \}_{i \in I}$ があるとき、直積集合 $\prod_{i \in I} X_i$ が定まります(超冪を構成した時に用いた $I$ とは無関係です)。これは、$I$ から $\bigcup_{i \in I} X_i$ への写像 $x$ のうち、
\begin{equation*}
\forall i \in I \,( x(i) \in X_i )
\end{equation*}
をみたすものの全体です。特に $X_i$ が全て同じ $X$ の場合は、$\prod_{i \in I} X$ は $I$ から $X$ への写像の全体となり、本記事ではこれを ${}^IX$ で表します( $X^I$ で表す流儀もあります)。
以下では $\prod_{i \in I} X_i$ を簡単に $\hat{X}$ とおいて、$\hat{X}$ の超準モデル ${}^*\hat{X}$ について考えます。
一般に、集合 $W$ の全ての元が集合 $X$ から集合 $Y$ への写像であるとき、写像の定義より
\begin{equation*}
\forall w \in W \, ( \forall z \in w \, \exists x \in X \, \exists y \in Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) \land \forall x \in X \, \exists ! y \in Y \, ( \langle x, y \rangle \in w ) )
\end{equation*}
が成り立つので、移行原理より、
\begin{equation*}
\forall w \in {}^*W \, ( \forall z \in w \, \exists x \in {}^*X \, \exists y \in {}^*Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) \land \forall x \in {}^*X \, \exists ! y \in {}^*Y \, ( \langle x, y \rangle \in w ) )
\end{equation*}
が成り立ち、従って ${}^*W$ の全ての元は集合 ${}^*X$ から集合 ${}^*Y$ への写像になります。そこで、$\hat{X}$ の元は $I$ から $\bigcup_{i \in I} X_i$ への写像なので、${}^*\hat{X}$ の元は ${}^*I$ から ${}^*(\bigcup_{i \in I} X_i)$ への写像です。任意の $i \in I$ に対して
\begin{equation*}
\forall x \in \hat{X} \,( x(i) \in X_i )
\end{equation*}
が成り立つので、移行原理より任意の $i \in I$ に対して
\begin{equation} \tag{1}
\forall x \in {}^*\hat{X} \,( x(i) \in {}^*X_i )
\end{equation}
が成り立ちます。
ここで、各 $X_i$ が開集合族 $\mathcal{O}_i$ によって位相空間となっているとすると、直積集合 $\hat{X}$ の部分集合の族
$\{ \, \prod_{i \in I} U_i \, \mid \, \forall i \in I \, (U_i \in \mathcal{O}_i)$ かつ有限個の $i$ を除き $U_i = X_i \, \}$
は $\hat{X}$ の開基の条件を満たすので、これによって $\hat{X}$ の位相(直積位相)が定まります。このとき、モナドについて次の定理が成立します。
【定理1】$\hat{X} \, (= \prod_{i \in I} X_i)$ の任意の点 $x$ に対して、次が成立する。
\begin{equation*}
\forall u \in {}^*\hat{X}\, ( u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \leftrightarrow \forall i \in I \, ( u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) ) )
\end{equation*}
(証明)
($\rightarrow$ の証明)ある $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ が $\lnot ( \forall i \in I \, ( u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) ) )$ をみたすと仮定して矛盾を導く。このとき $\exists i \in I \, ( u(i) \notin \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) )$ であるから、これをみたす $i$ をひとつ取って $i_0$ とおく。$u(i_0) \notin \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0))$ だから、$X_{i_0}$ における $x(i_0)$ の近傍 $A_{i_0}$ で $u(i_0) \notin {}^*A_{i_0}$ となるものがとれる。$i \neq i_0$ に対して $A_i = X_i$ として $\hat{A} = \prod_{i \in I} A_i$ とおくと、$\hat{A}$ は $\hat{X}$ における $x$ の近傍になるから、$u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ より $u \in {}^*\hat{A}$ である。しかし $\forall z \in \hat{A} \, ( z(i_0) \in A_{i_0} )$ と移行原理より $\forall z \in {}^*\hat{A} \, ( z(i_0) \in {}^*A_{i_0} )$ だから、$u(i_0) \in {}^*A_{i_0}$ でなければならず、矛盾を生じる。
($\leftarrow$ の証明)ある $u \in {}^*\hat{X}$ が $\forall i \in I \, ( u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) )$ かつ $u \notin \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ と仮定して矛盾を導く。このとき $\hat{X}$ における $x$ の近傍 $\hat{A}$ で $u \notin {}^*\hat{A}$ となるものがとれる。直積位相の定義から、$\hat{A} \supseteq \hat{B} = \prod_{i \in I} B_i$ で各 $B_i$ は $x(i)$ の開近傍、かつ有限個の $i$ を除き $B_i = X_i$ となるような $\hat{B}$ がある。その有限個の $i$ を $i_1, i_2, \cdots , i_n$ とおくと、
\begin{equation*}
\forall z \in \hat{X} \, ( z \in \hat{B} \leftrightarrow z(i_1) \in B_{i_1} \land z(i_2) \in B_{i_2} \land \cdots \land z(i_n) \in B_{i_n} )
\end{equation*}
であり、移行原理より、
\begin{equation*}
\forall z \in {}^*\hat{X} \, ( z \in {}^*\hat{B} \leftrightarrow z(i_1) \in {}^*B_{i_1} \land z(i_2) \in {}^*B_{i_2} \land \cdots \land z(i_n) \in {}^*B_{i_n} )
\end{equation*}
である。一方、$\forall i \in I \, ( u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) )$ かつ各 $B_i$ が $x(i)$ の近傍であることから、
\begin{equation*}
u(i_1) \in {}^*B_{i_1} \land u(i_2) \in {}^*B_{i_2} \land \cdots \land u(i_n) \in {}^*B_{i_n}
\end{equation*}
これより $u \in {}^*\hat{B} \subseteq {}^*\hat{A}$ となって $u \notin {}^*\hat{A}$ と矛盾する。□
この定理から、特に $I$ が有限集合のときには次が成立します(第19回【補題1】と数学的帰納法を用いても証明できます)。
【系2】$I$ が有限集合ならば、$\hat{X} \, (= \prod_{i \in I} X_i)$ の任意の点 $x$ に対して、次が成立する。
\begin{equation}
\mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) = \prod_{i \in I} \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) \tag{2}
\end{equation}
(証明)$I$ が有限集合のときは、${}^*I = I$ かつ ${}^*(\bigcup_{i \in I} X_i) = \bigcup_{i \in I} {}^*X_i$ であるから、${}^*\hat{X}$ の元は $I$ から $\bigcup_{i \in I} {}^*X_i$ への写像である。従って【定理1】より$(2)$が成り立つ。□
2. 直積空間の諸性質
【定理1】を使うと、位相空間におけるいくつかの性質が直積空間にも引き継がれることが機械的に証明できます。まずは閉集合から。
【定理3】直積空間 $\hat{X} \, (= \prod_{i \in I} X_i)$ において、各 $i \in I$ に対する $X_i$ の閉集合 $A_i$ の直積 $\prod_{i \in I} A_i$ は $\hat{X}$ の閉集合である。
(証明)$\hat{A} = \prod_{i \in I} A_i$ とおく。
$\hat{A}$ が閉集合でないと仮定すると、第17回【定理3】 ii) より $\mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap {}^*\hat{A} \neq \emptyset$ となる $x \in \hat{X} \setminus \hat{A}$ が存在する。$x \notin \hat{A}$ だから、ある $i_0 \in I$ について $x(i_0) \notin A_{i_0}$ である。一方、ある $u \in {}^*\hat{X}$ に対して $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap {}^*\hat{A}$ であるから、【定理1】より $u(i_0) \in \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0))$ である。さらに$(1)$を導いた移行原理を同様に $\hat{A}$ に適用すると $u(i_0) \in {}^*A_{i_0}$ がいえるから、$u(i_0) \in \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap {}^*A_{i_0}$ より $\mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap {}^*A_{i_0} \neq \emptyset$ である。$A_{i_0}$ は閉集合で $x(i_0) \in X_{i_0}$ だから、第17回【定理3】 ii) より $x(i_0) \in A_{i_0}$ となり、矛盾を生じる。□
なお、開集合の直積は必ずしも開集合にはなりません。
次にコンパクト性について。
【定理4】(チコノフの定理)すべての $i \in I$ に対して $X_i$ がコンパクト空間ならば、直積空間 $\hat{X} \, (= \prod_{i \in I} X_i)$ もコンパクトである。
(証明)任意に $u \in {}^*\hat{X}$ をとる。任意の $i \in I$ に対して $u(i) \in {}^*X_i$ であり、$X_i$ がコンパクトだから、第17回【定理5】よりある $x_i \in X_i$ に対して $u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x_i)$ となる。$\forall i \in I \, (x(i) = x_i)$ となるように $x \in \hat{X}$ を定めると、
\begin{equation*}
\forall i \in I \, ( u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) )
\end{equation*}
であるから、【定理1】より $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ である。従って再び第17回【定理5】より $\hat{X}$ はコンパクトである。□
同様にして、分離公理に関する次の定理も証明できます。
【定理5】直積空間 $\hat{X} \, (= \prod_{i \in I} X_i)$ について次が成立する。
i) すべての $i \in I$ に対して $X_i$ が $\mathrm{T}_1$ ならば、$\hat{X}$ も $\mathrm{T}_1$ である。
ii) すべての $i \in I$ に対して $X_i$ が $\mathrm{T}_2$(ハウスドルフ)ならば、$\hat{X}$ も $\mathrm{T}_2$(ハウスドルフ)である。
i) すべての $i \in I$ に対して $X_i$ が $\mathrm{T}_1$ ならば、$\hat{X}$ も $\mathrm{T}_1$ である。
ii) すべての $i \in I$ に対して $X_i$ が $\mathrm{T}_2$(ハウスドルフ)ならば、$\hat{X}$ も $\mathrm{T}_2$(ハウスドルフ)である。
(証明)
i) $\hat{X}$ が $\mathrm{T}_1$ でないと仮定する。第17回【定理4】 i) より、$x \neq y \land y \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ となる $x,y \in \hat{X}$ が存在する。$x \neq y$ だから、ある $i_0 \in I$ に対して $x(i_0) \neq y(i_0)$ となるが、$x(i_0), y(i_0) \in X_{i_0}$ かつ $X_{i_0}$ が $\mathrm{T}_1$ だから、第17回【定理4】 i) より $y(i_0) \notin \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0))$ である。一方、$y \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ と【定理1】より $y(i_0) \in \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0))$ が従うから、矛盾を生じる。
ii) $\hat{X}$ が $\mathrm{T}_2$ でないと仮定する。第17回【定理4】 ii) より、$x \neq y \land \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap \mathrm{monad}_{\hat{X}}(y) \neq \emptyset$ となる $x,y \in \hat{X}$ が存在する。$x \neq y$ だから、ある $i_0 \in I$ に対して $x(i_0) \neq y(i_0)$ となるが、$x(i_0), y(i_0) \in X_{i_0}$ かつ $X_{i_0}$ が $\mathrm{T}_2$ だから、第17回【定理4】 ii) より $\mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(y(i_0)) = \emptyset$ である。一方、$\mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap \mathrm{monad}_{\hat{X}}(y) \neq \emptyset$ より $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x) \cap \mathrm{monad}_{\hat{X}}(y)$ となる $u \in {}^*\hat{X}$ が存在し、【定理1】より $u(i_0) \in \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(y(i_0))$ が従うから、$\mathrm{monad}_{X_{i_0}}(x(i_0)) \cap \mathrm{monad}_{X_{i_0}}(y(i_0)) \neq \emptyset$ となって矛盾を生じる。□
また、連続写像に関する定理を用いると、次が証明できます。
【定理6】直積空間 $\hat{X} ( = \prod_{i \in I} X_i )$ において、すべての $i \in I$ に対して射影 $p_i : \hat{X} \to X_i$ は連続である。
(証明)任意に $x \in \hat{X}$ と $u \in \mathrm{monad}_{\hat{X}}(x)$ をとる。任意に $i \in I $ をとると、【定理1】より $u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i))$ である。一方、
\begin{equation*}
\forall z \in \hat{X} \, ( p_i(z) = z(i) )
\end{equation*}
と移行原理より、
\begin{equation*}
\forall z \in {}^*\hat{X} \, ( {}^*p_i(z) = z(i) )
\end{equation*}
であるから、${}^*p_i(u) = u(i) \in \mathrm{monad}_{X_i}(x(i)) = \mathrm{monad}_{X_i}(p_i(x))$ となり、第19回【定理2】より $p_i$ は $\hat{X}$ で連続である。□
どの性質も、極めて機械的に証明できることがわかります。
3. カントール空間
本節の議論の応用例として、カントール空間について考察してみます。
自然数の全体 $\mathbb{N}$ から$2$元集合 $\{ \, 0, 1 \, \}$(この集合を $2$ で表します) への写像の全体 ${}^{\mathbb{N}}2 \, ( \, = \prod_{i \in \mathbb{N}} 2 \, )$ を考え、$2$ に離散位相を入れて ${}^{\mathbb{N}}2$ を直積位相空間と考えます。明らかに $2$ はコンパクトだから、【定理4】(チコノフの定理)より ${}^{\mathbb{N}}2$ もコンパクトです。一方、区間 $[ 0, 1 ]$ に属する実数のうち$3$進法無限小数表記で$0$と$2$だけしか現れないようなものの全体 $\mathcal{C}$ は「カントール集合」と呼ばれますが(下図を参照)、これを$1$次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}$ の部分位相空間と考えると、$\mathbb{R}$ において有界閉集合なのでこれもコンパクトです。これら ${}^{\mathbb{N}}2$ と $\mathcal{C}$ は実は同相であり、どちらも「カントール空間」と呼ばれる位相空間の一つです。このことを以下で超準的手法を用いて証明します。
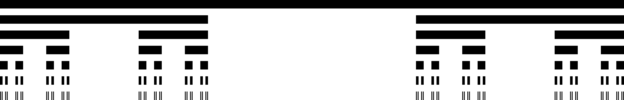
図. カントール集合( Wikimedia Commons より)
$x \in {}^{\mathbb{N}}2$ に対し、無限級数 $\displaystyle \sum_{i = 0}^\infty 2 x(i) / 3^{i+1}$ は $\mathbb{R}$ 内で収束するので、その和となる実数値を対応させる写像を $f$ とおくと、$f$ は ${}^{\mathbb{N}}2$ から $\mathcal{C}$ への全単射になります。従ってこの $f$ が連続写像であることを証明すれば、${}^{\mathbb{N}}2$ がコンパクト、$\mathbb{R}$ がハウスドルフ(従って $\mathcal{C}$ もハウスドルフ)なので、第19回【定理6】によって ${}^{\mathbb{N}}2$ と $\mathcal{C}$ が同相であることが示されます。第19回【定理2】を使ってこれを示すのですが、その概略は次のとおりです。
任意に $x \in {}^{\mathbb{N}}2$ をとり、その $x$ に対して任意に $u \in \mathrm{monad}_{{}^{\mathbb{N}}2}(x)$ をとります。$u \in {}^*( {}^{\mathbb{N}}2 )$ なので $u$ は ${}^*\mathbb{N}$ から $2 \, ( ={}^*2 )$ への写像であり、$i \in \mathbb{N}$ に対しては【定理1】より($2$ には離散位相が入るから) $u(i) \in \mathrm{monad}_2(x(i)) = \{ x(i) \}$ なので $u(i) = x(i)$ になります。この $u$ に対する ${}^*f(u)$ は超実数体 ${}^*\mathbb{R}$ における無限級数の和として $\displaystyle {}^*f(u) = {}^*\sum_{i = 0}^\infty 2 u(i) / 3^{i+1}$ となるので、その標準部分は実数体 $\mathbb{R}$ における無限級数の和として
\begin{equation} \tag{3}
\mathrm{st}({}^*f(u)) = \sum_{i = 0}^\infty 2 u(i) / 3^{i+1} = \sum_{i = 0}^\infty 2 x(i) / 3^{i+1} = f(x)
\end{equation}
となります。従って第18回【定理1】より ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_\mathbb{R}(x) \cap {}^*\mathcal{C} = \mathrm{monad}_\mathcal{C}(x)$ となるので、第19回【定理2】より $f$ は任意の $x \in {}^{\mathbb{N}}2$ で連続となり、証明が完了します。
この概略の最後の部分(「超実数体 ${}^*\mathbb{R}$ における無限級数の和」以降)は少々直感的にすぎるので、もう少し精密に考えてみます。$z \in {}^{\mathbb{N}}2$ に対する無限級数 $\displaystyle \sum_{i = 0}^\infty 2 z(i) / 3^{i+1}$ は常に $f(z)$ に収束するので、
\begin{equation} \tag{4}
\forall z \in {}^{\mathbb{N}}2 \, \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \exists n \in \mathbb{N} \, \forall k \in \mathbb{N} \, ( k \ge n \to \left| f(z) - \sum_{i = 0}^k 2 z(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon)
\end{equation}
が成り立ちます( $\mathbb{R}^+$ は正実数の全体)。すると移行原理によって、
\begin{equation} \tag{5}
\forall z \in {}^*( {}^{\mathbb{N}}2 ) \, \forall \epsilon \in {}^*\mathbb{R}^+ \, \exists n \in {}^*\mathbb{N} \, \forall k \in {}^*\mathbb{N} \, ( k \ge n \to \left| {}^*f(z) - {}^*\sum_{i = 0}^k 2 z(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon)
\end{equation}
が成り立ちます。そこで $u \in {}^*( {}^{\mathbb{N}}2 )$ に対して任意に正実数 $\epsilon$ をとり、$\mathbb{R}$ における無限級数 $\displaystyle \sum_{i = 0}^\infty 2 u(i) / 3^{i+1}$ の和を $s$ とおくと、$(4)$より十分大きな自然数 $m$ をとると、
\begin{equation*}
\left| s - \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon
\end{equation*}
が成り立ち、また$(5)$より十分大きな超自然数 $n ( > m)$ をとると、
\begin{equation*}
\left| {}^*f(u) - {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon
\end{equation*}
が成り立ちます。そして、
\begin{eqnarray*}
\left| {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} - \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} \right| &=& {}^*\sum_{i = m + 1}^n 2 u(i) / 3^{i+1} \le {}^*\sum_{i = m + 1}^n 2 / 3^{i+1} = \frac{1}{3^{m+1}}-\frac{1}{3^{n+1}} \\
&<& \frac{1}{3^{m+1}}
\end{eqnarray*}
であることから、$m$ を十分大きくとると、
\begin{equation*}
\left| {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} - \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} \right| < \epsilon
\end{equation*}
となるようにできます。これらより、
\begin{eqnarray*}
&&\left| {}^*f(u) - s \right| \\
&\le& \left| {}^*f(u) - {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} \right| + \left| {}^*\sum_{i = 0}^n 2 u(i) / 3^{i+1} - \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} \right| + \left| \sum_{i = 0}^m 2 u(i) / 3^{i+1} -s \right| \\
&<& 3 \epsilon
\end{eqnarray*}
となり、$\epsilon \in \mathbb{R}^+$ は任意なので $\left| {}^*f(u) - s \right| \approx 0$ すなわち $\mathrm{st}({}^*f(u)) = s$ が成り立ちます。これで証明中の($3$)の最初の等号部分が厳密に示されました。
以上で、少し回りくどかったですが、超準的手法を用いて2種類のカントール空間 ${}^{\mathbb{N}}2$ と $\mathcal{C}$ が同相であることを示すことができました。
注意すべきは、「 ${}^{\mathbb{N}}2$ の元は $0$ または $1$ の無限列なので、2進法の無限小数と対応するから、${}^{\mathbb{N}}2$ と実数の区間 $[ 0, 1 ]$ が同相になるのではないのか?」と早とちりしてはいけないということです。$x \in {}^{\mathbb{N}}2$ に無限級数 $\displaystyle \sum_{i = 0}^\infty x(i) / 2^{i+1}$ を対応させると、例えば2進法無限小数 $0.011111 \cdots$ は $0.100000 \cdots$ と実数として等しいので、この対応では ${}^{\mathbb{N}}2$ と $[ 0, 1 ]$ が1対1になりません。一方、先ほどの証明の方法で ${}^{\mathbb{N}}2$ の元に3進法無限小数を対応させると、例えば $0.022222 \cdots = 0.100000 \cdots$ ですが、後者は $1$ を含むので ${}^{\mathbb{N}}2$ の元に対応せず、従ってこちらの対応だと ${}^{\mathbb{N}}2$ と $\mathcal{C}$ が1対1になるのです。
(続く)(前記事)(目次)
わかってない奴がわかったつもりで書き留める超準解析(その19) [数学]
【超準解析について生半可な知識しかない僕が、わかったつもりの内容をちょっとずつ書き留めていきます。不正確な内容や誤りもあることをご承知ください。】
(19) 位相空間の連続写像
位相空間における写像(関数)の連続性についても、超準解析を使ったわかりやすい同値条件があります。本記事ではそのことを示し、それを用いて幾つかの定理を証明します。
1. 準備
本題に入る前に、直積や写像を超準解析で扱う際の基本事項について確認しておきます。
2つの集合 $X,Y$ があるとき、それらの直積 $X \times Y$ について、
\begin{equation*}
\forall x \in X \, \land y \in Y \, ( \langle x, y \rangle \in X \times Y )
\end{equation*}
が成り立ち、移行原理より、
\begin{equation*}
\forall x \in {}^*X \, \land y \in {}^*Y \, ( \langle x, y \rangle \in {}^*( X \times Y ) )
\end{equation*}
となるので ${}^*X \times {}^*Y \subseteq {}^*( X \times Y )$ です。一方、
\begin{equation*}
\forall z \in X \times Y \, ( \exists x \in X \, \exists y \in Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) )
\end{equation*}
が成り立ち、移行原理より、
\begin{equation*}
\forall z \in {}^*( X \times Y ) \, ( \exists x \in {}^*X \, \exists y \in {}^*Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) )
\end{equation*}
となるので ${}^*( X \times Y ) \subseteq {}^*X \times {}^*Y$ であり、あわせて
\begin{equation} \tag{1}
{}^*(X \times Y) = {}^*X \times {}^*Y
\end{equation}
が成立します。
また、$f$ が $X$ から $Y$ への写像であるとは、
\begin{equation} \tag{2}
\forall z \in f \, \exists x \in X \, \exists y \in Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) \land \forall x \in X \, \exists ! y \in Y \, ( \langle x, y \rangle \in f )
\end{equation}
が成り立つことをいいます。このとき移行原理より、
\begin{equation*}
\forall z \in {}^*f \, \exists x \in {}^*X \, \exists y \in {}^*Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) \land \forall x \in {}^*X \, \exists ! y \in {}^*Y \, ( \langle x, y \rangle \in {}^*f )
\end{equation*}
が成り立つので、$(2)$に照らし合わせることにより ${}^*f$ は ${}^*X$ から ${}^*Y$ への写像となります。$f \subseteq {}^*f$ なので、$x \in X$ のときは ${}^*f(x) = f(x)$ です。
写像の超準拡大については次が成立します( $A \subseteq X, B \subseteq Y$ とします)。
i) 像について ${}^*(f[A]) = {}^*f[{}^*A]$
ii) 逆像について ${}^*(f^{-1}[B]) = {}^*f^{-1}[{}^*B]$
iii) 制限について ${}^*(f \upharpoonright A) = {}^*f \upharpoonright {}^*A$
iv) $f$ が全単射ならば ${}^*f$ も全単射で、逆写像について ${}^*(f^{-1}) = {}^*f^{-1}$
これらは移行原理から簡単に導かれるので証明は省略し、以下自由に用いることにします。
ここから位相空間の内容に入ります。$X, Y$ がそれぞれ開集合族 $\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y$ によって位相空間となっているとすると、直積 $X \times Y$ の部分集合の族
\begin{equation*}
\{ \, U \times V \, \mid \, U \in \mathcal{O}_X \land V \in \mathcal{O}_Y \, \}
\end{equation*}
は $X \times Y$ の開基の条件を満たすので、これによって $X \times Y$ の位相(直積位相)が定まります。このとき、モナドについて次が成立します。
ここで位相空間 $X$ の点 $x$ のモナドは、$\mathcal{N}_X(x)$ を $x$ の近傍の全体として、
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_X(x) = \bigcap \{ \, {}^*A \, \mid \, A \in \mathcal{N}_X(x) \, \}
\end{equation*}
によって定まることを思い出しましょう。本記事ではいくつもの異なった位相空間が登場するので、どの空間についてのモナドや近傍なのかを表す添字は省略しません。
(証明)任意に $A \in \mathcal{N}_X(x)$ と $B \in \mathcal{N}_Y(y)$ をとると、ある $x$ の開近傍 $U$ と $y$ の開近傍 $V$ で $U \subseteq A \land V \subseteq B$ となるものが存在するから、$U \times V \subseteq A \times B$ と直積位相の定義より $A \times B \in \mathcal{N}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle )$ である。よって$(1)$より
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle ) \subseteq {}^*(A \times B) = {}^*A \times {}^*B
\end{equation*}
であり、$A, B$ は任意だから、
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle ) \subseteq \mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(y)
\end{equation*}
が成り立つ。
逆に、任意に $C \in \mathcal{N}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle )$ をとると、ある $\langle x, y \rangle$ の開近傍 $W$ で $W \subseteq C$ となるものが存在し、直積位相の定義より $x$ の開近傍 $U$ と $y$ の開近傍 $V$ で $U \times V \subseteq W \subseteq C$ となるものが存在するから、$(1)$より
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(y) \subseteq {}^*U \times {}^*V = {}^*(U \times V) \subseteq {}^*C
\end{equation*}
である。$C$ は任意だから、
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(y) \subseteq \mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle )
\end{equation*}
が成り立つ。□
2. 連続写像に関する定理
以上を踏まえて、本題の位相空間の連続性に入ります。位相空間 $X$ から位相空間 $Y$ への写像 $f$ が $X$ の点 $x$ で連続であるとは、$Y$ における点 $f(x)$ の任意の近傍 $B$ に対し、その逆像 $f^{-1}[B]$ が $X$ における $x$ の近傍となることをいいます。記号で書くと次のとおりです。
\begin{equation} \tag{3}
\forall B \in \mathcal{N}_Y(f(x)) \, ( f^{-1}[B] \in \mathcal{N}_X(x) )
\end{equation}
これは超準モデルを使って次の同値な条件で表すことができます。今回の主題となる定理です。
(証明)$(3) \Leftrightarrow (4)$ を示せばよい。
$(3) \Rightarrow (4)$:$(3)$が成り立つとし、$(4)$が成り立たないと仮定して矛盾を導く。このとき ${}^*f(u) \notin \mathrm{monad}_Y(f(x))$ となる $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ が存在し、この $u$ に対してある $B \in \mathcal{N}_Y(f(x))$ で ${}^*f(u) \notin {}^*B$ となるものが存在するが、$(3)$より $f^{-1}[B] \in \mathcal{N}_X(x)$ であるから、$\mathrm{monad}_X(x) \subseteq {}^*(f^{-1}[B]) = {}^*f^{-1}[{}^*B]$ となって、$u \in {}^*f^{-1}[{}^*B]$ である。これは ${}^*f(u) \in {}^*B$ を意味するから矛盾である。
$(3) \Leftarrow (4)$:$(4)$が成り立つとし、$(3)$が成り立たないと仮定して矛盾を導く。このとき $f^{-1}[B] \notin \mathcal{N}_X(x)$ となる $B \in \mathcal{N}_Y(f(x))$ が存在する。この $B$ に対して $\mathrm{monad}_X(x) \not\subseteq {}^*(f^{-1}[B]) = {}^*f^{-1}[{}^*B]$ であるから、$u \in \mathrm{monad}_X(x) \setminus {}^*f^{-1}[{}^*B]$ となる $u$ をとると、$(4)$より ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ であるが、一方で $u \notin {}^*f^{-1}[{}^*B]$ より ${}^*f(u) \notin {}^*B$ であるから $\mathrm{monad}_Y(f(x)) \not\subseteq {}^*B$ である。これは $B \in \mathcal{N}_Y(f(x))$ と矛盾する。□
以下、これを使って連続写像に関する諸定理を超準的手法で証明します。「開集合の逆像は開集合」は定義よりほとんど自明なので省略します。「閉集合の逆像は閉集合」も補集合を使えばそこからすぐに導かれますが、次のように超準的手法で証明することもできます。
(証明)任意に $\mathrm{monad}_X(x) \cap {}^*(f^{-1}[B]) \neq \emptyset$ となる $x \in X$ をとる。このとき $u \in \mathrm{monad}_X(x) \cap {}^*(f^{-1}[B])$ となる $u$ が存在し、$f$ は $x$ で連続だから【定理2】より ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ であり、また $u \in {}^*(f^{-1}[B]) = {}^*f^{-1}[{}^*B]$ だから ${}^*f(u) \in {}^*B$ であり、これらより $\mathrm{monad}_Y(f(x)) \cap {}^*B \neq \emptyset$ である。$B$ は閉集合だから第17回【定理3】 ii) より $f(x) \in B$ であり、よって $x \in f^{-1}[B]$ だから、再び第17回【定理3】 ii) より $f^{-1}[B]$ は閉集合である。□
「連結集合の像は連結集合」はこれらから容易に導かれるので省略します。
次にコンパクト性に関する定理を証明します。
(証明)
i) 任意に $v \in {}^*(f[A])$ をとる。$v \in {}^*f[{}^*A]$ だから、ある $u \in {}^*A$ に対して ${}^*f(u) = v$ となる。$A$ はコンパクトだから、第17回【定理5】より $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ となる $x \in A$ が存在する。$f$ は $x$ で連続だから、【定理2】より
\begin{equation*}
v = {}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))
\end{equation*}
である。$f(x) \in f[A]$ だから、第17回【定理5】より $f[A]$ はコンパクトである。
ii) 任意に $\langle u, v \rangle \in {}^*(f \upharpoonright A)$ をとる。$\langle u, v \rangle \in {}^*f \upharpoonright {}^*A$ だから $u \in {}^*A$ で、$A$ がコンパクトだから第17回【定理5】より $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ となる $x \in A$ が存在する。$f$ は $x$ で連続だから【定理2】より $v = {}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ であり、【補題1】より
\begin{equation*}
\langle u, v \rangle \in \mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(f(x)) = \mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, f(x) \rangle )
\end{equation*}
である。$\langle x, f(x) \rangle \in f \upharpoonright A$ だから第17回【定理5】より $f \upharpoonright A$ はコンパクトである。□
次に、【定理4】 ii) のある意味逆といえる定理を証明します。
(証明)任意に $x \in X$ と $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ をとる。このとき $\langle u, {}^*f(u) \rangle \in {}^*f$ で、$f$ は $X \times Y$ 上でコンパクトだから、第17回【定理5】より $\langle u, {}^*f(u) \rangle \in \mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x', f(x') \rangle )$ となる $x' \in X$ が存在する。【補題1】より $\mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x', f(x') \rangle ) = \mathrm{monad}_X(x') \times \mathrm{monad}_Y(f(x'))$ だから、$u \in \mathrm{monad}_X(x')$ かつ ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x'))$ である。これらより $\mathrm{monad}_X(x) \cap \mathrm{monad}_X(x') \neq \emptyset$ であり、$X$ はハウスドルフだから第17回【定理4】 ii) より $x = x'$ が従う。よって ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ となり、【定理2】より $f$ は $x$ で連続であり、従って $X$ で連続である。□
この定理から、2つの位相空間が同相になるための一つの十分条件が示されます。
(証明)$f$ が全単射だから逆写像 $f^{-1}$ が存在し、これが $Y \times X$ 上でコンパクトであることを示す。任意に $\langle v, u \rangle \in {}^*(f^{-1})$ をとると、${}^*(f^{-1}) = {}^*f^{-1} \subseteq {}^*Y \times {}^*X$ より $u \in {}^*X$ であり、$X$ がコンパクトだから第17回【定理5】より $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ となる $x \in X$ が存在する。$f$ は $x$ で連続だから、【定理2】より $v = {}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ である。よって【補題1】より、
\begin{equation*}
\langle v, u \rangle \in \mathrm{monad}_Y(f(x)) \times \mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_{Y \times X}( \langle f(x), x \rangle )
\end{equation*}
かつ $\langle f(x), x \rangle \in f^{-1}$ だから、第17回【定理5】より $f^{-1}$ はコンパクトである。すると、$Y$ がハウスドルフだから【定理5】より $f^{-1}$ は $Y$ で連続である。従って $X$ と $Y$ は同相であり、任意の $x \in X$ に対し、$(4)$を $f^{-1}$ に適用して ${}^*f^{-1}[ \mathrm{monad}_Y(f(x)) ] \subseteq \mathrm{monad}_X(x)$ となるから $\mathrm{monad}_Y(f(x)) \subseteq {}^*f[ \mathrm{monad}_X(x) ]$ であり、これと$(4)$より ${}^*f[ \mathrm{monad}_X(x) ] = \mathrm{monad}_Y(f(x))$ が得られ、$x \in X$ は任意だから$(5)$が得られる。□
このように、いろんな定理が超準的手法の条件の組み合わせで機械的に証明できることがわかります。
3. ユークリッド空間への応用
ここで応用例として、2次元以上のユークリッド空間が1次元ユークリッド空間と同相にならないことを、超準的手法を用いて証明することとします。まずそれに用いる常識的な補題から。
(証明)任意に $x \in X$ と $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ をとる。【補題1】より、
\begin{equation*}
\langle u, y_0 \rangle \in \mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(y_0) = \mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, y_0 \rangle )
\end{equation*}
であり、$f$ は連続だから【定理2】より
\begin{equation*}
{}^*g(u) = {}^*f( \langle u, y_0 \rangle ) \in \mathrm{monad}_Z( f( \langle x, y_0 \rangle ) ) = \mathrm{monad}_Z( g(x) )
\end{equation*}
である。従って再び【定理2】より $g$ は連続である。□
次が証明したい事柄です。
(証明)$\mathbb{R}$ のユークリッド位相における「連結であることと区間であることは同値」「有界閉区間はコンパクト」という事実を用いる。
内点をもつ $\mathbb{R}^n$ の部分集合を $C$ とし、$C$ から $\mathbb{R}$ への連続な単射 $f$ が存在すると仮定して矛盾を導く。以下 $m = n - 1$ とおいて $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ とみなし、また $\langle x,y \rangle \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ に対して $f( \langle x,y \rangle )$ を $f(x,y)$ とかく。
$C$ の内点 $\langle a, b \rangle \ ( a \in \mathbb{R} \land b \in \mathbb{R}^m )$ をとり、$a$ を内点にもつ $\mathbb{R}$ の閉区間 $A$ と、$\mathbb{R}^m$ における $b$ の近傍 $B$ を、$A \times B \subseteq C$ となるようにとる($A, B$ を十分小さくとれば可能)。
$A$ から $\mathbb{R}$ への写像 $g$ を $g(x) = f(x,b)$ によって定めると、$f$ が $A \times B$ で連続な単射だから、【補題7】より $g$ も $A$ で連続な単射である。$A$ はコンパクトで $\mathbb{R}$ はハウスドルフだから、【定理6】より
\begin{equation} \tag{6}
\forall x \in A \, ( {}^*g[ \mathrm{monad}_A(x) ] = \mathrm{monad}_{g[A]}(f(x)) )
\end{equation}
が成立する。また $A$ は $\mathbb{R}$ の区間だから連結で、その連続写像 $g$ による像 $g[A]$ も連結だから $\mathbb{R}$ の区間である。$A$ は2点以上をもち $g$ は単射だから $g[A]$ も2点以上をもち、従って内点 $c$ がとれる。この $c$ に対し $\mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c) \subseteq {}^*(g[A])$ であり、よって
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_{g[A]}(c) = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c) \cap {}^*(g[A]) = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c)
\end{equation*}
である。$f(a') = c$ となる $a' \in A$ をとると、$(6)$より
\begin{equation} \tag{7}
{}^*g[ \mathrm{monad}_A(a') ] = \mathrm{monad}_{g[A]}(c) = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c)
\end{equation}
が成り立つ。
この $a'$ に対し、$B$ から $\mathbb{R}$ への写像 $h$ を $h(y) = f(a',y)$ によって定める。$b$ は $\mathbb{R}^m$ の位相における $B$ の内点だから $\mathrm{monad}_{\mathbb{R}^m}(b) \subseteq {}^*B$ であり、よって
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_B(b) = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}^m}(b) \cap {}^*B = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}^m}(b)
\end{equation*}
であるから、$v \neq b$ となる $v \in \mathrm{monad}_B(b)$ がとれる。【補題7】より $h$ も $B$ で連続だから、【定理2】より ${}^*h(v) \in \mathrm{monad}_{h[B]}(c) \subseteq \mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c)$ である。$(7)$より ${}^*g(u) = {}^*h(v)$ となる $u \in \mathrm{monad}_A(a')$ がとれ、${}^*f(u,b) = {}^*g(u)$ かつ ${}^*f(a',v) = {}^*h(v)$ より ${}^*f(u,b) = {}^*f(a',v)$ が得られるが、$f$ は単射だから ${}^*f$ も単射であり、$\langle u, b \rangle \neq \langle a', v \rangle$ だからこれは矛盾である。□
直線と平面が同じ濃度を持つことを発見したカントルがその事実に困惑したのを見て、デデキントがカントルを慰める?ために指摘した内容を、ここでは超準解析を用いて証明してみました。
(続く)(前記事)(目次)
(19) 位相空間の連続写像
位相空間における写像(関数)の連続性についても、超準解析を使ったわかりやすい同値条件があります。本記事ではそのことを示し、それを用いて幾つかの定理を証明します。
1. 準備
本題に入る前に、直積や写像を超準解析で扱う際の基本事項について確認しておきます。
2つの集合 $X,Y$ があるとき、それらの直積 $X \times Y$ について、
\begin{equation*}
\forall x \in X \, \land y \in Y \, ( \langle x, y \rangle \in X \times Y )
\end{equation*}
が成り立ち、移行原理より、
\begin{equation*}
\forall x \in {}^*X \, \land y \in {}^*Y \, ( \langle x, y \rangle \in {}^*( X \times Y ) )
\end{equation*}
となるので ${}^*X \times {}^*Y \subseteq {}^*( X \times Y )$ です。一方、
\begin{equation*}
\forall z \in X \times Y \, ( \exists x \in X \, \exists y \in Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) )
\end{equation*}
が成り立ち、移行原理より、
\begin{equation*}
\forall z \in {}^*( X \times Y ) \, ( \exists x \in {}^*X \, \exists y \in {}^*Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) )
\end{equation*}
となるので ${}^*( X \times Y ) \subseteq {}^*X \times {}^*Y$ であり、あわせて
\begin{equation} \tag{1}
{}^*(X \times Y) = {}^*X \times {}^*Y
\end{equation}
が成立します。
また、$f$ が $X$ から $Y$ への写像であるとは、
\begin{equation} \tag{2}
\forall z \in f \, \exists x \in X \, \exists y \in Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) \land \forall x \in X \, \exists ! y \in Y \, ( \langle x, y \rangle \in f )
\end{equation}
が成り立つことをいいます。このとき移行原理より、
\begin{equation*}
\forall z \in {}^*f \, \exists x \in {}^*X \, \exists y \in {}^*Y \, ( z = \langle x, y \rangle ) \land \forall x \in {}^*X \, \exists ! y \in {}^*Y \, ( \langle x, y \rangle \in {}^*f )
\end{equation*}
が成り立つので、$(2)$に照らし合わせることにより ${}^*f$ は ${}^*X$ から ${}^*Y$ への写像となります。$f \subseteq {}^*f$ なので、$x \in X$ のときは ${}^*f(x) = f(x)$ です。
写像の超準拡大については次が成立します( $A \subseteq X, B \subseteq Y$ とします)。
i) 像について ${}^*(f[A]) = {}^*f[{}^*A]$
ii) 逆像について ${}^*(f^{-1}[B]) = {}^*f^{-1}[{}^*B]$
iii) 制限について ${}^*(f \upharpoonright A) = {}^*f \upharpoonright {}^*A$
iv) $f$ が全単射ならば ${}^*f$ も全単射で、逆写像について ${}^*(f^{-1}) = {}^*f^{-1}$
これらは移行原理から簡単に導かれるので証明は省略し、以下自由に用いることにします。
ここから位相空間の内容に入ります。$X, Y$ がそれぞれ開集合族 $\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y$ によって位相空間となっているとすると、直積 $X \times Y$ の部分集合の族
\begin{equation*}
\{ \, U \times V \, \mid \, U \in \mathcal{O}_X \land V \in \mathcal{O}_Y \, \}
\end{equation*}
は $X \times Y$ の開基の条件を満たすので、これによって $X \times Y$ の位相(直積位相)が定まります。このとき、モナドについて次が成立します。
【補題1】位相空間 $X, Y$ と直積位相空間 $X \times Y$ および任意の $x \in X, \, y \in Y$ に対して、次が成立する。
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle ) = \mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(y)
\end{equation*}
ここで位相空間 $X$ の点 $x$ のモナドは、$\mathcal{N}_X(x)$ を $x$ の近傍の全体として、
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_X(x) = \bigcap \{ \, {}^*A \, \mid \, A \in \mathcal{N}_X(x) \, \}
\end{equation*}
によって定まることを思い出しましょう。本記事ではいくつもの異なった位相空間が登場するので、どの空間についてのモナドや近傍なのかを表す添字は省略しません。
(証明)任意に $A \in \mathcal{N}_X(x)$ と $B \in \mathcal{N}_Y(y)$ をとると、ある $x$ の開近傍 $U$ と $y$ の開近傍 $V$ で $U \subseteq A \land V \subseteq B$ となるものが存在するから、$U \times V \subseteq A \times B$ と直積位相の定義より $A \times B \in \mathcal{N}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle )$ である。よって$(1)$より
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle ) \subseteq {}^*(A \times B) = {}^*A \times {}^*B
\end{equation*}
であり、$A, B$ は任意だから、
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle ) \subseteq \mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(y)
\end{equation*}
が成り立つ。
逆に、任意に $C \in \mathcal{N}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle )$ をとると、ある $\langle x, y \rangle$ の開近傍 $W$ で $W \subseteq C$ となるものが存在し、直積位相の定義より $x$ の開近傍 $U$ と $y$ の開近傍 $V$ で $U \times V \subseteq W \subseteq C$ となるものが存在するから、$(1)$より
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(y) \subseteq {}^*U \times {}^*V = {}^*(U \times V) \subseteq {}^*C
\end{equation*}
である。$C$ は任意だから、
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(y) \subseteq \mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, y \rangle )
\end{equation*}
が成り立つ。□
2. 連続写像に関する定理
以上を踏まえて、本題の位相空間の連続性に入ります。位相空間 $X$ から位相空間 $Y$ への写像 $f$ が $X$ の点 $x$ で連続であるとは、$Y$ における点 $f(x)$ の任意の近傍 $B$ に対し、その逆像 $f^{-1}[B]$ が $X$ における $x$ の近傍となることをいいます。記号で書くと次のとおりです。
\begin{equation} \tag{3}
\forall B \in \mathcal{N}_Y(f(x)) \, ( f^{-1}[B] \in \mathcal{N}_X(x) )
\end{equation}
これは超準モデルを使って次の同値な条件で表すことができます。今回の主題となる定理です。
【定理2】位相空間 $X$ から位相空間 $Y$ への写像 $f$ が $X$ の点 $x$ で連続であることと、
\begin{equation*}
\forall u \in \mathrm{monad}_X(x) \, ({}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x)) )
\end{equation*}
すなわち
\begin{equation} \tag{4}
{}^*f[ \mathrm{monad}_X(x) ] \subseteq \mathrm{monad}_Y(f(x))
\end{equation}
が成り立つことは同値である。
(証明)$(3) \Leftrightarrow (4)$ を示せばよい。
$(3) \Rightarrow (4)$:$(3)$が成り立つとし、$(4)$が成り立たないと仮定して矛盾を導く。このとき ${}^*f(u) \notin \mathrm{monad}_Y(f(x))$ となる $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ が存在し、この $u$ に対してある $B \in \mathcal{N}_Y(f(x))$ で ${}^*f(u) \notin {}^*B$ となるものが存在するが、$(3)$より $f^{-1}[B] \in \mathcal{N}_X(x)$ であるから、$\mathrm{monad}_X(x) \subseteq {}^*(f^{-1}[B]) = {}^*f^{-1}[{}^*B]$ となって、$u \in {}^*f^{-1}[{}^*B]$ である。これは ${}^*f(u) \in {}^*B$ を意味するから矛盾である。
$(3) \Leftarrow (4)$:$(4)$が成り立つとし、$(3)$が成り立たないと仮定して矛盾を導く。このとき $f^{-1}[B] \notin \mathcal{N}_X(x)$ となる $B \in \mathcal{N}_Y(f(x))$ が存在する。この $B$ に対して $\mathrm{monad}_X(x) \not\subseteq {}^*(f^{-1}[B]) = {}^*f^{-1}[{}^*B]$ であるから、$u \in \mathrm{monad}_X(x) \setminus {}^*f^{-1}[{}^*B]$ となる $u$ をとると、$(4)$より ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ であるが、一方で $u \notin {}^*f^{-1}[{}^*B]$ より ${}^*f(u) \notin {}^*B$ であるから $\mathrm{monad}_Y(f(x)) \not\subseteq {}^*B$ である。これは $B \in \mathcal{N}_Y(f(x))$ と矛盾する。□
以下、これを使って連続写像に関する諸定理を超準的手法で証明します。「開集合の逆像は開集合」は定義よりほとんど自明なので省略します。「閉集合の逆像は閉集合」も補集合を使えばそこからすぐに導かれますが、次のように超準的手法で証明することもできます。
【定理3】$X, Y$ は位相空間、$f$ は $X$ から $Y$ への写像で $X$(上のすべての点)で連続とする。$B \in \mathscr{P}(Y)$ が閉集合ならば、逆像 $f^{-1}[B]$ は閉集合である。
(証明)任意に $\mathrm{monad}_X(x) \cap {}^*(f^{-1}[B]) \neq \emptyset$ となる $x \in X$ をとる。このとき $u \in \mathrm{monad}_X(x) \cap {}^*(f^{-1}[B])$ となる $u$ が存在し、$f$ は $x$ で連続だから【定理2】より ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ であり、また $u \in {}^*(f^{-1}[B]) = {}^*f^{-1}[{}^*B]$ だから ${}^*f(u) \in {}^*B$ であり、これらより $\mathrm{monad}_Y(f(x)) \cap {}^*B \neq \emptyset$ である。$B$ は閉集合だから第17回【定理3】 ii) より $f(x) \in B$ であり、よって $x \in f^{-1}[B]$ だから、再び第17回【定理3】 ii) より $f^{-1}[B]$ は閉集合である。□
「連結集合の像は連結集合」はこれらから容易に導かれるので省略します。
次にコンパクト性に関する定理を証明します。
【定理4】$X, Y$ は位相空間、$A \in \mathscr{P}(X)$ は $X$ 上でコンパクト、$f$ は $X$ から $Y$ への写像で $A$ で連続とすると、次が成立する。
i) 像 $f[A]$ は $Y$ 上でコンパクトである。
ii) 制限 $f \upharpoonright A$(のグラフ)は $X \times Y$ 上でコンパクトである。
i) 像 $f[A]$ は $Y$ 上でコンパクトである。
ii) 制限 $f \upharpoonright A$(のグラフ)は $X \times Y$ 上でコンパクトである。
(証明)
i) 任意に $v \in {}^*(f[A])$ をとる。$v \in {}^*f[{}^*A]$ だから、ある $u \in {}^*A$ に対して ${}^*f(u) = v$ となる。$A$ はコンパクトだから、第17回【定理5】より $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ となる $x \in A$ が存在する。$f$ は $x$ で連続だから、【定理2】より
\begin{equation*}
v = {}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))
\end{equation*}
である。$f(x) \in f[A]$ だから、第17回【定理5】より $f[A]$ はコンパクトである。
ii) 任意に $\langle u, v \rangle \in {}^*(f \upharpoonright A)$ をとる。$\langle u, v \rangle \in {}^*f \upharpoonright {}^*A$ だから $u \in {}^*A$ で、$A$ がコンパクトだから第17回【定理5】より $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ となる $x \in A$ が存在する。$f$ は $x$ で連続だから【定理2】より $v = {}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ であり、【補題1】より
\begin{equation*}
\langle u, v \rangle \in \mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(f(x)) = \mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, f(x) \rangle )
\end{equation*}
である。$\langle x, f(x) \rangle \in f \upharpoonright A$ だから第17回【定理5】より $f \upharpoonright A$ はコンパクトである。□
次に、【定理4】 ii) のある意味逆といえる定理を証明します。
【定理5】$X, Y$ は位相空間で $X$ はハウスドルフとするとき、$X$ から $Y$ への写像 $f$ が $X \times Y$ 上でコンパクトならば、$f$ は $X$ で連続である。
(証明)任意に $x \in X$ と $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ をとる。このとき $\langle u, {}^*f(u) \rangle \in {}^*f$ で、$f$ は $X \times Y$ 上でコンパクトだから、第17回【定理5】より $\langle u, {}^*f(u) \rangle \in \mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x', f(x') \rangle )$ となる $x' \in X$ が存在する。【補題1】より $\mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x', f(x') \rangle ) = \mathrm{monad}_X(x') \times \mathrm{monad}_Y(f(x'))$ だから、$u \in \mathrm{monad}_X(x')$ かつ ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x'))$ である。これらより $\mathrm{monad}_X(x) \cap \mathrm{monad}_X(x') \neq \emptyset$ であり、$X$ はハウスドルフだから第17回【定理4】 ii) より $x = x'$ が従う。よって ${}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ となり、【定理2】より $f$ は $x$ で連続であり、従って $X$ で連続である。□
この定理から、2つの位相空間が同相になるための一つの十分条件が示されます。
【定理6】$X, Y$ は位相空間、$X$ はコンパクトで $Y$ はハウスドルフ、$f$ は $X$ から $Y$ への連続な全単射とすると、逆写像 $f^{-1}$ も $Y$ で連続である。従って $X$ と $Y$ は同相であり、
\begin{equation} \tag{5}
\forall x \in X \, ( {}^*f[ \mathrm{monad}_X(x) ] = \mathrm{monad}_Y(f(x)) )
\end{equation}
が成立する。
(証明)$f$ が全単射だから逆写像 $f^{-1}$ が存在し、これが $Y \times X$ 上でコンパクトであることを示す。任意に $\langle v, u \rangle \in {}^*(f^{-1})$ をとると、${}^*(f^{-1}) = {}^*f^{-1} \subseteq {}^*Y \times {}^*X$ より $u \in {}^*X$ であり、$X$ がコンパクトだから第17回【定理5】より $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ となる $x \in X$ が存在する。$f$ は $x$ で連続だから、【定理2】より $v = {}^*f(u) \in \mathrm{monad}_Y(f(x))$ である。よって【補題1】より、
\begin{equation*}
\langle v, u \rangle \in \mathrm{monad}_Y(f(x)) \times \mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_{Y \times X}( \langle f(x), x \rangle )
\end{equation*}
かつ $\langle f(x), x \rangle \in f^{-1}$ だから、第17回【定理5】より $f^{-1}$ はコンパクトである。すると、$Y$ がハウスドルフだから【定理5】より $f^{-1}$ は $Y$ で連続である。従って $X$ と $Y$ は同相であり、任意の $x \in X$ に対し、$(4)$を $f^{-1}$ に適用して ${}^*f^{-1}[ \mathrm{monad}_Y(f(x)) ] \subseteq \mathrm{monad}_X(x)$ となるから $\mathrm{monad}_Y(f(x)) \subseteq {}^*f[ \mathrm{monad}_X(x) ]$ であり、これと$(4)$より ${}^*f[ \mathrm{monad}_X(x) ] = \mathrm{monad}_Y(f(x))$ が得られ、$x \in X$ は任意だから$(5)$が得られる。□
このように、いろんな定理が超準的手法の条件の組み合わせで機械的に証明できることがわかります。
3. ユークリッド空間への応用
ここで応用例として、2次元以上のユークリッド空間が1次元ユークリッド空間と同相にならないことを、超準的手法を用いて証明することとします。まずそれに用いる常識的な補題から。
【補題7】$X, Y, Z$ は位相空間、$f$ は $X \times Y$ から $Z$ への連続写像とすると、ある $y_0 \in Y$ に対して
\begin{equation*}
g : X \to Z, \, x \mapsto f(x,y_0)
\end{equation*}
によって定まる写像 $g$ も連続である。
(証明)任意に $x \in X$ と $u \in \mathrm{monad}_X(x)$ をとる。【補題1】より、
\begin{equation*}
\langle u, y_0 \rangle \in \mathrm{monad}_X(x) \times \mathrm{monad}_Y(y_0) = \mathrm{monad}_{X \times Y}( \langle x, y_0 \rangle )
\end{equation*}
であり、$f$ は連続だから【定理2】より
\begin{equation*}
{}^*g(u) = {}^*f( \langle u, y_0 \rangle ) \in \mathrm{monad}_Z( f( \langle x, y_0 \rangle ) ) = \mathrm{monad}_Z( g(x) )
\end{equation*}
である。従って再び【定理2】より $g$ は連続である。□
次が証明したい事柄です。
【定理8】$n \ge 2$ のとき、内点をもつ $\mathbb{R}^n$ の部分集合から $\mathbb{R}$ への連続な単射は存在しない。ただし位相は通常のユークリッド位相とする。
(証明)$\mathbb{R}$ のユークリッド位相における「連結であることと区間であることは同値」「有界閉区間はコンパクト」という事実を用いる。
内点をもつ $\mathbb{R}^n$ の部分集合を $C$ とし、$C$ から $\mathbb{R}$ への連続な単射 $f$ が存在すると仮定して矛盾を導く。以下 $m = n - 1$ とおいて $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ とみなし、また $\langle x,y \rangle \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ に対して $f( \langle x,y \rangle )$ を $f(x,y)$ とかく。
$C$ の内点 $\langle a, b \rangle \ ( a \in \mathbb{R} \land b \in \mathbb{R}^m )$ をとり、$a$ を内点にもつ $\mathbb{R}$ の閉区間 $A$ と、$\mathbb{R}^m$ における $b$ の近傍 $B$ を、$A \times B \subseteq C$ となるようにとる($A, B$ を十分小さくとれば可能)。
$A$ から $\mathbb{R}$ への写像 $g$ を $g(x) = f(x,b)$ によって定めると、$f$ が $A \times B$ で連続な単射だから、【補題7】より $g$ も $A$ で連続な単射である。$A$ はコンパクトで $\mathbb{R}$ はハウスドルフだから、【定理6】より
\begin{equation} \tag{6}
\forall x \in A \, ( {}^*g[ \mathrm{monad}_A(x) ] = \mathrm{monad}_{g[A]}(f(x)) )
\end{equation}
が成立する。また $A$ は $\mathbb{R}$ の区間だから連結で、その連続写像 $g$ による像 $g[A]$ も連結だから $\mathbb{R}$ の区間である。$A$ は2点以上をもち $g$ は単射だから $g[A]$ も2点以上をもち、従って内点 $c$ がとれる。この $c$ に対し $\mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c) \subseteq {}^*(g[A])$ であり、よって
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_{g[A]}(c) = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c) \cap {}^*(g[A]) = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c)
\end{equation*}
である。$f(a') = c$ となる $a' \in A$ をとると、$(6)$より
\begin{equation} \tag{7}
{}^*g[ \mathrm{monad}_A(a') ] = \mathrm{monad}_{g[A]}(c) = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c)
\end{equation}
が成り立つ。
この $a'$ に対し、$B$ から $\mathbb{R}$ への写像 $h$ を $h(y) = f(a',y)$ によって定める。$b$ は $\mathbb{R}^m$ の位相における $B$ の内点だから $\mathrm{monad}_{\mathbb{R}^m}(b) \subseteq {}^*B$ であり、よって
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_B(b) = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}^m}(b) \cap {}^*B = \mathrm{monad}_{\mathbb{R}^m}(b)
\end{equation*}
であるから、$v \neq b$ となる $v \in \mathrm{monad}_B(b)$ がとれる。【補題7】より $h$ も $B$ で連続だから、【定理2】より ${}^*h(v) \in \mathrm{monad}_{h[B]}(c) \subseteq \mathrm{monad}_{\mathbb{R}}(c)$ である。$(7)$より ${}^*g(u) = {}^*h(v)$ となる $u \in \mathrm{monad}_A(a')$ がとれ、${}^*f(u,b) = {}^*g(u)$ かつ ${}^*f(a',v) = {}^*h(v)$ より ${}^*f(u,b) = {}^*f(a',v)$ が得られるが、$f$ は単射だから ${}^*f$ も単射であり、$\langle u, b \rangle \neq \langle a', v \rangle$ だからこれは矛盾である。□
直線と平面が同じ濃度を持つことを発見したカントルがその事実に困惑したのを見て、デデキントがカントルを慰める?ために指摘した内容を、ここでは超準解析を用いて証明してみました。
(続く)(前記事)(目次)
わかってない奴がわかったつもりで書き留める超準解析(その18) [数学]
【超準解析について生半可な知識しかない僕が、わかったつもりの内容をちょっとずつ書き留めていきます。不正確な内容や誤りもあることをご承知ください。】
(18) アレクサンドロフの1点コンパクト化
前回の続きとして、コンパクトでない空間をコンパクト空間に拡張する1つの手法「アレクサンドロフの1点コンパクト化」を、超準モデルを使って構成する方法を紹介します。
1. 超準モデルから定まる位相
$X$ を位相が定まっていない無限集合とするとき、その超準モデルを使って、次のようにして $X$ に位相を定めることができます。
すべての $X$ の点 $x$ に対して $x \in \nu(x)$ をみたす ${}^*X$ の部分集合 $\nu(x) \in \mathscr{P}({}^*X)$ が(何でもよいので)定まっているとします。このとき、
\begin{equation*}
\mathcal{O} = \{ \, A \in \mathscr{P}(X) \, \mid \, \forall x \in A \, (\nu(x) \subseteq {}^*A) \, \}
\end{equation*}
と定めると、この $\mathcal{O}$ は次の開集合系の性質を全てみたします。
① $\emptyset \in \mathcal{O} \land X \in \mathcal{O}$
② $A \in \mathcal{O} \land B \in \mathcal{O} \to A \cap B \in \mathcal{O}$
③ $\forall i \in I \, (A_i \in \mathcal{O}) \to \bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{O}$
①と②は明らかなので、和集合に関する性質③だけ示しておきます。$\forall i \in I \, (A_i \in \mathcal{O})$ が成り立つとし、$B = \bigcup_{i \in I} A_i$ とします。任意に $x \in B$ をとると、ある $i \in I$ に対して $x \in A_i$ だから $\nu(x) \subseteq {}^*A_i$ となります。$A_i \subseteq B$ だから移行原理より ${}^*A_i \subseteq {}^*B$ となり、従って $\nu(x) \subseteq {}^*B$ となるから $B \in \mathcal{O}$ です。これで $\mathcal{O}$ が開集合系の性質を全てみたすことが示されたので、$X$ に位相が定まります。
この位相に関して近傍系やモナドが定まりますが、$A$ が点 $x$ の近傍ならば簡単な考察により $\nu(x) \subseteq {}^*A$ がわかるので、$\nu(x) \subseteq \mathrm{monad}(x)$ となります。一般には必ずしもこれらは等しくなりません。
この方法を使って位相空間 $X$ を $X \subsetneq Y$ となる集合 $Y$ に拡張することを考えます。このため、一般に一方が他方の部分位相空間となるための超準モデルによる同値条件を考察します。
$X \subseteq Y$ の関係にある位相空間 $X, Y$ がそれぞれあるとします。$X$ と $Y$ の開集合系をそれぞれ $\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y$ とし、また、$X$ における点 $x$ の近傍系とモナドをそれぞれ $\mathcal{N}_X(x), \mathrm{monad}_X(x)$ とかき、同様に $Y$ における点 $x$ の近傍系とモナドをそれぞれ $\mathcal{N}_Y(x), \mathrm{monad}_Y(x)$ とかくことにします。このとき、$X$ が $Y$ の部分位相空間であるとは、
\begin{equation} \tag{1}
\forall A \in \mathscr{P}(X) \, (A \in \mathcal{O}_X \leftrightarrow \exists B \in \mathcal{O}_Y \, (A = B \cap X))
\end{equation}
であることをいいます。
これを超準モデルでの同値条件で表したものが次の定理です。
(証明)$(1) \Leftrightarrow (2)$ を示せばよい。
$(1) \Rightarrow (2)$ : $(1)$ が成り立つとし、任意に $x \in X$ をとる。
任意に $B \in \mathcal{N}_Y(x)$ をとると、$x \in B' \subseteq B$ となる $B' \in \mathcal{O}_Y$ がとれ、$A' = B' \cap X$ とすると $(1)$ より $A' \in \mathcal{O}_X$ で、$x \in A'$ だから
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_X(x) \subseteq {}^*A' \subseteq {}^*B' \subseteq {}^*B
\end{equation*}
である。$B \in \mathcal{N}_Y(x)$ は任意だから $\mathrm{monad}_X(x) \subseteq \mathrm{monad}_Y(x)$ であり、また $\mathrm{monad}_X(x) \subseteq {}^*X$ は明らかだから $\mathrm{monad}_X(x) \subseteq \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X$ が得られる。
逆に、任意に $A \in \mathcal{N}_X(x)$ をとると、$x \in A' \subseteq A$ となる $A' \in \mathcal{O}_X$ がとれ、$(1)$ よりある $B' \in \mathcal{O}_Y$ に対して $A' = B' \cap X$ となり、$x \in B'$ だから $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*B'$ より
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X \subseteq {}^*B' \cap {}^*X = {}^*A' \subseteq {}^*A
\end{equation*}
であり、$A \in \mathcal{N}_X(x)$ は任意だから $\mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X \subseteq \mathrm{monad}_X(x)$ が得られる。
以上より $\mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X$ であり、$(2)$ が示された。
$(2) \Rightarrow (1)$ : $(2)$ が成り立つとし、任意に $A \in \mathscr{P}(X)$ をとる。
$A \in \mathcal{O}_X$ とする。$B' = A \cup (Y \setminus X)$ とおき、任意の $x \in A$ に対して $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*B'$ となることを示す。任意に $y \in \mathrm{monad}_Y(x)$ をとると、$y \in {}^*X$ ならば $(2)$ より
\begin{equation*}
y \in \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X = \mathrm{monad}_X(x) \subseteq {}^*A \subseteq {}^*B'
\end{equation*}
となるから $y \in {}^*B'$ である。$y \notin {}^*X$ ならば
\begin{equation*}
y \in {}^*Y \setminus {}^*X = {}^*(Y \setminus X) \subseteq {}^*B'
\end{equation*}
よりやはり $y \in {}^*B'$ である。これで $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*B'$ が示されたから $B' \in \mathcal{N}_Y(x)$ であり、$x \in B(x) \subseteq B'$ をみたす $B(x) \in \mathcal{O}_Y$ が存在する。$B = \bigcup_{x \in A}B(x)$ とおくと $B \in \mathcal{O}_Y$ かつ $B \subseteq B'$ で、明らかに $A \subseteq B \cap X$ であり、また $B \cap X \subseteq B' \cap X = A$ だから $A = B \cap X$ である。
逆に、ある $B \in \mathcal{O}_Y$ に対して $A = B \cap X$ ならば、任意の $x \in A$ に対して、$\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*B$ と $(2)$ より
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X \subseteq {}^*B \cap {}^*X = {}^*A
\end{equation*}
が得られるから、$A \in \mathcal{O}_X$ である。
以上より $A \in \mathcal{O}_X \leftrightarrow \exists B \in \mathcal{O}_Y \, (A = B \cap X)$ であり、$(1)$ が示された。□
さて、超準モデルを使って位相空間 $X$ を $X \subsetneq Y$ となる $Y$ に拡張する一つの方法を、次の補題によって示します。
(証明)
任意に $x \in X$ をとる。まず、$\mathrm{monad}_X(x) = \nu(x) \subseteq \mathrm{monad}_Y(x)$ である。逆の包含関係を示すため、任意に $A \in \mathcal{N}_X(x)$ をとると、$x \in B \subseteq A$ となる $B \in \mathcal{O}_X$ が存在し、$\forall y \in B \, (\nu(y) = \mathrm{monad}_X(y) \subseteq {}^*B)$ より $B \in \mathcal{O}_Y$ となるから $A \in \mathcal{N}_Y(x)$ であり、これより $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*A$ である。$A \in \mathcal{N}_X(x)$ は任意だから $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq \mathrm{monad}_X(x)$ が得られる。以上で $(3)$ が示された。□
この補題の方法は、本来は $(2)$ でよいのにそれより強い $(3)$ が得られることから、位相空間の拡張手段としてはかなり「雑」といえます。しかし次に示す目的のためには、この方法で十分です。
2. アレクサンドロフの1点コンパクト化
ここまでの考察を利用して、「アレクサンドロフの1点コンパクト化」を超準モデルを用いて構成します。
位相空間 $X$ に対し、$X$ に属さない1点 $\infty$ を $X$ に追加した空間 $Y = X \cup \{ \infty \}$ を考え、次によって $\nu(\infty)$ を定めます。
\begin{equation*}
\nu(\infty) = \{ \, y \in {}^*X \, \mid \, \forall x \in X \, (y \notin \mathrm{monad}_X(x)) \, \} \cup \{ \infty \}
\end{equation*}
つまり「 ${}^*X$ のすべての遠標準点と $\infty$ を集めた集合」を $\nu(\infty)$ と定めます。
これを用いて【補題2】の方法で $X$ を部分位相空間とする $Y$ の位相が定まります。$(3)$ が成立するので、以下 $\mathrm{monad}$ の添字は省略します。
このとき、まず $Y$ はコンパクトです。なぜなら任意に $y \in {}^*Y$ をとると、$y$ はある $x \in X$ に対して $y \in \mathrm{monad}(x)$ となるか、または $y \in \nu(\infty)$ となるかのどちらかで、後者ならば $y \in \nu(\infty) \subseteq \mathrm{monad}(\infty)$ なので、第17回【定理5】より $Y$ はコンパクトになります。
次に、$X$ がコンパクトでない場合、$X$ は $Y$ において稠密となります。なぜなら $X$ がコンパクトでなければ ${}^*X$ は遠標準点をもつから $\nu(\infty) \cap {}^*X \neq \emptyset$ であり、従って $\mathrm{monad}(\infty) \cap {}^*X \neq \emptyset$ より $\forall x \in Y \, ( \mathrm{monad}(x) \cap {}^*X \neq \emptyset )$ となるから、第17回【定理3】の ix) より $X$ は $Y$ において稠密です。
これらの条件をみたす $Y = X \cup \{ \infty \}$ を $X$ のアレクサンドロフの1点コンパクト化といいます。従って上の方法は、任意のコンパクトでない位相空間から1点コンパクト化を構成する(超準モデルを使った)一つの方法を示しています。
さらに次が成り立ちます。
(証明)
$\mathrm{monad}(\infty) \supseteq \nu(\infty)$ は既に証明済み。$\mathrm{monad}(\infty) \subseteq \nu(\infty)$ を示すため、ある $ y \in \mathrm{monad}(\infty) \setminus \nu(\infty)$ が存在すると仮定して矛盾を導く。$y \notin \nu(\infty)$ なので、$\nu(\infty)$ の定義より、ある $x \in X$ に対して $y \in \mathrm{monad}(x)$ である。$X$ は局所コンパクトだから $A \in \mathcal{N}_X(x)$ となるコンパクトな $A$ が存在して $y \in \mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*A$ より $y \in {}^*A$ となる。$X$ はハウスドルフだから第17回【定理6】 ii) より $A$ は $X$ の閉集合で、従って $X \setminus A$ は $X$ の開集合である。そこで $B = (X \setminus A) \cup \{ \infty \}$ とすると $B = Y \setminus A$ で、任意の $z \in X \setminus A$ に対して $\nu(z) = \mathrm{monad}(z) \subseteq {}^*(X \setminus A) \subseteq {}^*B$ である。また $A$ がコンパクトだから第17回【定理5】より ${}^*A$ の点は全て ${}^*X$ の近標準点で、$\nu(\infty)$ は ${}^*X$ の遠標準点と $\infty$ の集合だから $\nu(\infty) \cap {}^*A = \emptyset$ であり、これより $\nu(\infty) \subseteq {}^*Y \setminus {}^*A = {}^*(Y \setminus A) = {}^*B$ となる。従って $B$ は $Y$ における開集合であるから $\infty$ の近傍であり、 $y \in \mathrm{monad}(\infty) \subseteq {}^*B = {}^*Y \setminus {}^*A$ となるから $y \in {}^*A$ と矛盾する。以上より $\mathrm{monad}(\infty) \subseteq \nu(\infty)$ が得られたから $\mathrm{monad}(\infty) = \nu(\infty)$ である。□
この補題を使って、次の有名な結果が示されます。
(証明)
$X$ がハウスドルフであることと第17回【定理4】 ii) より、任意の $x, y \in X$ に対して $x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset$ である。さらに【補題3】より $\mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(\infty) = \mathrm{monad}(x) \cap \nu(\infty) = \emptyset$ も明らかなので、任意の $x, y \in Y$ に対して $x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset$ が成り立ち、従って再び第17回【定理4】 ii) より $Y$ もハウスドルフである。□
ついでに、この定理の逆も超準モデルを利用して示しておきましょう。そのために必要になるのが次の補題です。
(証明)
【定理1】より任意の $x \in X$ に対して
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X
\end{equation*}
が成立する。$Y$ が $\mathrm{T}_1$ だから第17回【定理4】 i) より $\infty \notin \mathrm{monad}_Y(x)$ であり、かつ ${}^*Y = {}^*X \cup \{ \infty \}$ だから $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*X$ すなわち $\mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X = \mathrm{monad}_Y(x)$ である。従って $(4)$ が成立する。□
この補題を使って、【定理4】の逆が次のように示されます。
(証明)
$Y$ はハウスドルフだから $\mathrm{T}_1$ であり、【補題5】より $(4)$ が成立する。従って $Y$ のハウスドルフ性と第17回【定理4】 ii) より $X$ もハウスドルフである。任意に $x \in X$ をとると、$Y$ がハウスドルフだから $Y$ における $x$ の開近傍 $A$ と $\infty$ の開近傍 $B$ で $A \cap B = \emptyset$ となるものがとれる。$C = Y \setminus B$ とすると、$C$ はコンパクト空間 $Y$ の閉集合だから、第17回【定理6】 i) より $Y$ においてコンパクトである。従って第17回【定理5】より、
\begin{equation*}
\forall y \in {}^*C \, \exists z \in C \, (y \in \mathrm{monad}_Y(z))
\end{equation*}
が成立するが、$\infty \notin C$ より $C \subseteq X$ であり、これと $(4)$ より
\begin{equation*}
\forall y \in {}^*C \, \exists z \in C \, (y \in \mathrm{monad}_X(z))
\end{equation*}
が成立し、第17回【定理5】より $C$ は $X$ においてもコンパクトである。$A \subseteq C$ だから $C$ は $x$ のコンパクトな近傍であり、$x \in X$ は任意だから $X$ は局所コンパクトである。□
以上でアレクサンドロフの1点コンパクト化に関する諸定理が、超準モデルを使って証明されました。通常の方法に比べて特に簡単になるとは言えませんが、ハウスドルフ性やコンパクト性とモナドとの関係を見通しよく利用することができて、面白い方法だと思います。
(続く)(前記事)(目次)
(18) アレクサンドロフの1点コンパクト化
前回の続きとして、コンパクトでない空間をコンパクト空間に拡張する1つの手法「アレクサンドロフの1点コンパクト化」を、超準モデルを使って構成する方法を紹介します。
1. 超準モデルから定まる位相
$X$ を位相が定まっていない無限集合とするとき、その超準モデルを使って、次のようにして $X$ に位相を定めることができます。
すべての $X$ の点 $x$ に対して $x \in \nu(x)$ をみたす ${}^*X$ の部分集合 $\nu(x) \in \mathscr{P}({}^*X)$ が(何でもよいので)定まっているとします。このとき、
\begin{equation*}
\mathcal{O} = \{ \, A \in \mathscr{P}(X) \, \mid \, \forall x \in A \, (\nu(x) \subseteq {}^*A) \, \}
\end{equation*}
と定めると、この $\mathcal{O}$ は次の開集合系の性質を全てみたします。
① $\emptyset \in \mathcal{O} \land X \in \mathcal{O}$
② $A \in \mathcal{O} \land B \in \mathcal{O} \to A \cap B \in \mathcal{O}$
③ $\forall i \in I \, (A_i \in \mathcal{O}) \to \bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{O}$
①と②は明らかなので、和集合に関する性質③だけ示しておきます。$\forall i \in I \, (A_i \in \mathcal{O})$ が成り立つとし、$B = \bigcup_{i \in I} A_i$ とします。任意に $x \in B$ をとると、ある $i \in I$ に対して $x \in A_i$ だから $\nu(x) \subseteq {}^*A_i$ となります。$A_i \subseteq B$ だから移行原理より ${}^*A_i \subseteq {}^*B$ となり、従って $\nu(x) \subseteq {}^*B$ となるから $B \in \mathcal{O}$ です。これで $\mathcal{O}$ が開集合系の性質を全てみたすことが示されたので、$X$ に位相が定まります。
この位相に関して近傍系やモナドが定まりますが、$A$ が点 $x$ の近傍ならば簡単な考察により $\nu(x) \subseteq {}^*A$ がわかるので、$\nu(x) \subseteq \mathrm{monad}(x)$ となります。一般には必ずしもこれらは等しくなりません。
この方法を使って位相空間 $X$ を $X \subsetneq Y$ となる集合 $Y$ に拡張することを考えます。このため、一般に一方が他方の部分位相空間となるための超準モデルによる同値条件を考察します。
$X \subseteq Y$ の関係にある位相空間 $X, Y$ がそれぞれあるとします。$X$ と $Y$ の開集合系をそれぞれ $\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y$ とし、また、$X$ における点 $x$ の近傍系とモナドをそれぞれ $\mathcal{N}_X(x), \mathrm{monad}_X(x)$ とかき、同様に $Y$ における点 $x$ の近傍系とモナドをそれぞれ $\mathcal{N}_Y(x), \mathrm{monad}_Y(x)$ とかくことにします。このとき、$X$ が $Y$ の部分位相空間であるとは、
\begin{equation} \tag{1}
\forall A \in \mathscr{P}(X) \, (A \in \mathcal{O}_X \leftrightarrow \exists B \in \mathcal{O}_Y \, (A = B \cap X))
\end{equation}
であることをいいます。
これを超準モデルでの同値条件で表したものが次の定理です。
【定理1】位相空間 $X,Y$ が $X \subseteq Y$ のとき、$X$ が $Y$ の部分位相空間となることは、
\begin{equation} \tag{2}
\forall x \in X \, (\mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X)
\end{equation}
が成り立つことと同値である。
(証明)$(1) \Leftrightarrow (2)$ を示せばよい。
$(1) \Rightarrow (2)$ : $(1)$ が成り立つとし、任意に $x \in X$ をとる。
任意に $B \in \mathcal{N}_Y(x)$ をとると、$x \in B' \subseteq B$ となる $B' \in \mathcal{O}_Y$ がとれ、$A' = B' \cap X$ とすると $(1)$ より $A' \in \mathcal{O}_X$ で、$x \in A'$ だから
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_X(x) \subseteq {}^*A' \subseteq {}^*B' \subseteq {}^*B
\end{equation*}
である。$B \in \mathcal{N}_Y(x)$ は任意だから $\mathrm{monad}_X(x) \subseteq \mathrm{monad}_Y(x)$ であり、また $\mathrm{monad}_X(x) \subseteq {}^*X$ は明らかだから $\mathrm{monad}_X(x) \subseteq \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X$ が得られる。
逆に、任意に $A \in \mathcal{N}_X(x)$ をとると、$x \in A' \subseteq A$ となる $A' \in \mathcal{O}_X$ がとれ、$(1)$ よりある $B' \in \mathcal{O}_Y$ に対して $A' = B' \cap X$ となり、$x \in B'$ だから $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*B'$ より
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X \subseteq {}^*B' \cap {}^*X = {}^*A' \subseteq {}^*A
\end{equation*}
であり、$A \in \mathcal{N}_X(x)$ は任意だから $\mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X \subseteq \mathrm{monad}_X(x)$ が得られる。
以上より $\mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X$ であり、$(2)$ が示された。
$(2) \Rightarrow (1)$ : $(2)$ が成り立つとし、任意に $A \in \mathscr{P}(X)$ をとる。
$A \in \mathcal{O}_X$ とする。$B' = A \cup (Y \setminus X)$ とおき、任意の $x \in A$ に対して $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*B'$ となることを示す。任意に $y \in \mathrm{monad}_Y(x)$ をとると、$y \in {}^*X$ ならば $(2)$ より
\begin{equation*}
y \in \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X = \mathrm{monad}_X(x) \subseteq {}^*A \subseteq {}^*B'
\end{equation*}
となるから $y \in {}^*B'$ である。$y \notin {}^*X$ ならば
\begin{equation*}
y \in {}^*Y \setminus {}^*X = {}^*(Y \setminus X) \subseteq {}^*B'
\end{equation*}
よりやはり $y \in {}^*B'$ である。これで $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*B'$ が示されたから $B' \in \mathcal{N}_Y(x)$ であり、$x \in B(x) \subseteq B'$ をみたす $B(x) \in \mathcal{O}_Y$ が存在する。$B = \bigcup_{x \in A}B(x)$ とおくと $B \in \mathcal{O}_Y$ かつ $B \subseteq B'$ で、明らかに $A \subseteq B \cap X$ であり、また $B \cap X \subseteq B' \cap X = A$ だから $A = B \cap X$ である。
逆に、ある $B \in \mathcal{O}_Y$ に対して $A = B \cap X$ ならば、任意の $x \in A$ に対して、$\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*B$ と $(2)$ より
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X \subseteq {}^*B \cap {}^*X = {}^*A
\end{equation*}
が得られるから、$A \in \mathcal{O}_X$ である。
以上より $A \in \mathcal{O}_X \leftrightarrow \exists B \in \mathcal{O}_Y \, (A = B \cap X)$ であり、$(1)$ が示された。□
さて、超準モデルを使って位相空間 $X$ を $X \subsetneq Y$ となる $Y$ に拡張する一つの方法を、次の補題によって示します。
【補題2】位相空間 $X$ と $X \subsetneq Y$ となる $Y$ があり、任意の $x \in Y \setminus X$ に対して $x \in \nu(x)$ をみたす $\nu(x) \in \mathscr{P}({}^*X)$ が定まっているとする。このとき任意の $x \in X$ に対して $\nu(x) = \mathrm{monad}_X(x)$ と定め、
\begin{equation*}
\mathcal{O}_Y = \{ \, A \in \mathscr{P}(Y) \, \mid \, \forall x \in A \, (\nu(x) \subseteq {}^*A) \, \}
\end{equation*}
で定まる開集合系 $\mathcal{O}_Y$ によって $Y$ に位相を定めると、
\begin{equation} \tag{3}
\forall x \in X \, (\mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_Y(x))
\end{equation}
であり、従って【定理1】より $X$ は $Y$ の部分位相空間となる。
(証明)
任意に $x \in X$ をとる。まず、$\mathrm{monad}_X(x) = \nu(x) \subseteq \mathrm{monad}_Y(x)$ である。逆の包含関係を示すため、任意に $A \in \mathcal{N}_X(x)$ をとると、$x \in B \subseteq A$ となる $B \in \mathcal{O}_X$ が存在し、$\forall y \in B \, (\nu(y) = \mathrm{monad}_X(y) \subseteq {}^*B)$ より $B \in \mathcal{O}_Y$ となるから $A \in \mathcal{N}_Y(x)$ であり、これより $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*A$ である。$A \in \mathcal{N}_X(x)$ は任意だから $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq \mathrm{monad}_X(x)$ が得られる。以上で $(3)$ が示された。□
この補題の方法は、本来は $(2)$ でよいのにそれより強い $(3)$ が得られることから、位相空間の拡張手段としてはかなり「雑」といえます。しかし次に示す目的のためには、この方法で十分です。
2. アレクサンドロフの1点コンパクト化
ここまでの考察を利用して、「アレクサンドロフの1点コンパクト化」を超準モデルを用いて構成します。
位相空間 $X$ に対し、$X$ に属さない1点 $\infty$ を $X$ に追加した空間 $Y = X \cup \{ \infty \}$ を考え、次によって $\nu(\infty)$ を定めます。
\begin{equation*}
\nu(\infty) = \{ \, y \in {}^*X \, \mid \, \forall x \in X \, (y \notin \mathrm{monad}_X(x)) \, \} \cup \{ \infty \}
\end{equation*}
つまり「 ${}^*X$ のすべての遠標準点と $\infty$ を集めた集合」を $\nu(\infty)$ と定めます。
これを用いて【補題2】の方法で $X$ を部分位相空間とする $Y$ の位相が定まります。$(3)$ が成立するので、以下 $\mathrm{monad}$ の添字は省略します。
このとき、まず $Y$ はコンパクトです。なぜなら任意に $y \in {}^*Y$ をとると、$y$ はある $x \in X$ に対して $y \in \mathrm{monad}(x)$ となるか、または $y \in \nu(\infty)$ となるかのどちらかで、後者ならば $y \in \nu(\infty) \subseteq \mathrm{monad}(\infty)$ なので、第17回【定理5】より $Y$ はコンパクトになります。
次に、$X$ がコンパクトでない場合、$X$ は $Y$ において稠密となります。なぜなら $X$ がコンパクトでなければ ${}^*X$ は遠標準点をもつから $\nu(\infty) \cap {}^*X \neq \emptyset$ であり、従って $\mathrm{monad}(\infty) \cap {}^*X \neq \emptyset$ より $\forall x \in Y \, ( \mathrm{monad}(x) \cap {}^*X \neq \emptyset )$ となるから、第17回【定理3】の ix) より $X$ は $Y$ において稠密です。
これらの条件をみたす $Y = X \cup \{ \infty \}$ を $X$ のアレクサンドロフの1点コンパクト化といいます。従って上の方法は、任意のコンパクトでない位相空間から1点コンパクト化を構成する(超準モデルを使った)一つの方法を示しています。
さらに次が成り立ちます。
【補題3】$X$ がハウスドルフかつ局所コンパクト(任意の点に対してコンパクトな近傍が存在する)ならば、上の方法で構成した1点コンパクト化において、
\begin{equation*}
\mathrm{monad}(\infty) = \nu(\infty)
\end{equation*}
が成立する。
(証明)
$\mathrm{monad}(\infty) \supseteq \nu(\infty)$ は既に証明済み。$\mathrm{monad}(\infty) \subseteq \nu(\infty)$ を示すため、ある $ y \in \mathrm{monad}(\infty) \setminus \nu(\infty)$ が存在すると仮定して矛盾を導く。$y \notin \nu(\infty)$ なので、$\nu(\infty)$ の定義より、ある $x \in X$ に対して $y \in \mathrm{monad}(x)$ である。$X$ は局所コンパクトだから $A \in \mathcal{N}_X(x)$ となるコンパクトな $A$ が存在して $y \in \mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*A$ より $y \in {}^*A$ となる。$X$ はハウスドルフだから第17回【定理6】 ii) より $A$ は $X$ の閉集合で、従って $X \setminus A$ は $X$ の開集合である。そこで $B = (X \setminus A) \cup \{ \infty \}$ とすると $B = Y \setminus A$ で、任意の $z \in X \setminus A$ に対して $\nu(z) = \mathrm{monad}(z) \subseteq {}^*(X \setminus A) \subseteq {}^*B$ である。また $A$ がコンパクトだから第17回【定理5】より ${}^*A$ の点は全て ${}^*X$ の近標準点で、$\nu(\infty)$ は ${}^*X$ の遠標準点と $\infty$ の集合だから $\nu(\infty) \cap {}^*A = \emptyset$ であり、これより $\nu(\infty) \subseteq {}^*Y \setminus {}^*A = {}^*(Y \setminus A) = {}^*B$ となる。従って $B$ は $Y$ における開集合であるから $\infty$ の近傍であり、 $y \in \mathrm{monad}(\infty) \subseteq {}^*B = {}^*Y \setminus {}^*A$ となるから $y \in {}^*A$ と矛盾する。以上より $\mathrm{monad}(\infty) \subseteq \nu(\infty)$ が得られたから $\mathrm{monad}(\infty) = \nu(\infty)$ である。□
この補題を使って、次の有名な結果が示されます。
【定理4】$X$ がハウスドルフかつ局所コンパクトのとき、上の方法で構成した1点コンパクト化はハウスドルフである。
(証明)
$X$ がハウスドルフであることと第17回【定理4】 ii) より、任意の $x, y \in X$ に対して $x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset$ である。さらに【補題3】より $\mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(\infty) = \mathrm{monad}(x) \cap \nu(\infty) = \emptyset$ も明らかなので、任意の $x, y \in Y$ に対して $x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset$ が成り立ち、従って再び第17回【定理4】 ii) より $Y$ もハウスドルフである。□
ついでに、この定理の逆も超準モデルを利用して示しておきましょう。そのために必要になるのが次の補題です。
【補題5】位相空間 $X$ が $Y = X \cup \{ \infty \} \ ( \infty \notin X )$ の部分位相空間であり、かつ $Y$ が $\mathrm{T}_1$ ならば、次が成立する。
\begin{equation} \tag{4}
\forall x \in X \, (\mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_Y(x))
\end{equation}
(証明)
【定理1】より任意の $x \in X$ に対して
\begin{equation*}
\mathrm{monad}_X(x) = \mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X
\end{equation*}
が成立する。$Y$ が $\mathrm{T}_1$ だから第17回【定理4】 i) より $\infty \notin \mathrm{monad}_Y(x)$ であり、かつ ${}^*Y = {}^*X \cup \{ \infty \}$ だから $\mathrm{monad}_Y(x) \subseteq {}^*X$ すなわち $\mathrm{monad}_Y(x) \cap {}^*X = \mathrm{monad}_Y(x)$ である。従って $(4)$ が成立する。□
この補題を使って、【定理4】の逆が次のように示されます。
【定理6】$X$ の1点コンパクト化 $Y$ がハウスドルフならば、$X$ はハウスドルフかつ局所コンパクトである。
(証明)
$Y$ はハウスドルフだから $\mathrm{T}_1$ であり、【補題5】より $(4)$ が成立する。従って $Y$ のハウスドルフ性と第17回【定理4】 ii) より $X$ もハウスドルフである。任意に $x \in X$ をとると、$Y$ がハウスドルフだから $Y$ における $x$ の開近傍 $A$ と $\infty$ の開近傍 $B$ で $A \cap B = \emptyset$ となるものがとれる。$C = Y \setminus B$ とすると、$C$ はコンパクト空間 $Y$ の閉集合だから、第17回【定理6】 i) より $Y$ においてコンパクトである。従って第17回【定理5】より、
\begin{equation*}
\forall y \in {}^*C \, \exists z \in C \, (y \in \mathrm{monad}_Y(z))
\end{equation*}
が成立するが、$\infty \notin C$ より $C \subseteq X$ であり、これと $(4)$ より
\begin{equation*}
\forall y \in {}^*C \, \exists z \in C \, (y \in \mathrm{monad}_X(z))
\end{equation*}
が成立し、第17回【定理5】より $C$ は $X$ においてもコンパクトである。$A \subseteq C$ だから $C$ は $x$ のコンパクトな近傍であり、$x \in X$ は任意だから $X$ は局所コンパクトである。□
以上でアレクサンドロフの1点コンパクト化に関する諸定理が、超準モデルを使って証明されました。通常の方法に比べて特に簡単になるとは言えませんが、ハウスドルフ性やコンパクト性とモナドとの関係を見通しよく利用することができて、面白い方法だと思います。
(続く)(前記事)(目次)
わかってない奴がわかったつもりで書き留める超準解析(その17) [数学]
【超準解析について生半可な知識しかない僕が、わかったつもりの内容をちょっとずつ書き留めていきます。不正確な内容や誤りもあることをご承知ください。】
(17) 位相空間の超準的考察
第7回で距離空間を超準的に考察しましたが、本記事では一般の位相空間を超準的に考察することにします。位相空間の諸概念が簡単な論理式で表現できて、とても面白いです。
1. 上部構造と広大性原理
位相空間を超準的に考察するためには、超準モデルの「広大性原理」と呼ばれる性質が必要となります。まずこれを極めて雑にですが説明します。
$X$ を無限集合とし、適切な無限集合 $I$ とその上の超フィルターを使って、第6回で示した方法を使って $X$ から超冪 ${}^*X$ を構成します。同一視によって $X \subseteq {}^*X$ とみなし、${}^*X$ は $X$ の真の拡大とすることができます。
さらに考察の対象を広げて、$X$ から始めてその冪集合 $\mathscr{P}(X)$ との和集合 $X \cup \mathscr{P}(X)$ を作り、またその冪集合との和集合を作り、この作業を任意有限回繰り返してできる集合すべての和集合を $\mathcal{U}$ とします。これを「 $X$ の上部構造」と呼びます。また、 ${}^*X$ から始めて同様の操作で作られる「 ${}^*X$ の上部構造」を ${}^*\mathcal{U}$ とします。このとき $\mathcal{U}$ から ${}^*\mathcal{U}$ への写像 ${}^*$ を定義し、任意の $a \in \mathcal{U}$ に対して ${}^*a \in {}^*\mathcal{U}$ を対応させることができます。ただし $x \in X$ に対しては ${}^*x = x$ となります。
本稿ではこうして作った ${}^*\mathcal{U}$ を $\mathcal{U}$ の超準モデルとよび、$a$ に対する ${}^*a$ を $a$ の超準拡大とよぶこととします(あまり標準的なよび方ではないかもしれません)。
集合論言語の論理式 $\varphi(x_1, x_2, \cdots , x_n)$( $x_1, x_2, \cdots , x_n$ 以外に自由変数を持たない)と任意の $a_1, a_2, \cdots , a_n \in \mathcal{U}$ に対して、次の移行原理が成り立ちます。
ここでは「有界論理式」についての詳細は省略します。移行原理によって、任意の $X$ の部分集合 $A, B$ に対して、例えば ${}^*(A \cap B) = {}^*A \cap {}^*B$ や $A \subseteq B \Leftrightarrow {}^*A \subseteq {}^*B$ などの法則が示されます(第1回を参照)。
これに加え、超冪の構成で使用する $I$ とその上の超フィルターをうまくとると、次の広大性原理とよばれる性質が成り立ちます。
本記事では、超準モデルでは常に広大性原理が成立するものとします。
2. 位相空間の基本概念の超準的考察
$\langle X, \mathcal{O} \rangle$ を無限個の元をもつ位相空間とします。$\mathcal{O}$ は開集合系で、以降これを簡単に「位相空間 $X$」と呼びます。$x \in X, A \in \mathscr{P}(X)$ に対して $A$ が $x$ の近傍であるとは、$x \in B \subseteq A$ となる開集合 $B$ が存在することです。$x \in X$ に対して $x$ の近傍の全体を $\mathcal{N}(x)$ とかくこととします。
ここで、超準モデルを使ってモナドと呼ばれる次の集合を定義します。
必ず $x \in \mathrm{monad}(x)$ なので、これは空集合にはなりません。このとき次が成立します。
(証明)
$\Rightarrow$ の証明:モナドの定義から明らか。
$\Leftarrow$ の証明:$\mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*A$ とし、$A \notin \mathcal{N}(x)$ を仮定して矛盾を導く。このとき任意の $B \in \mathcal{N}(x)$ に対して $B \not\subseteq A$ であるから $\exists y \in X \, (y \in B \setminus A)$ である。そこで、$\mathcal{N}(x) \times X$ 上の関係 $R$ を
\begin{equation*}
R = \{ \, \langle B, y \rangle \in \mathcal{N}(x) \times X \, \mid \, y \in B \setminus A \, \}
\end{equation*}
によって定めると、任意有限個の $B_1, B_2, \cdots , B_n \in \mathcal{N}(x)$ に対して $B_1 \cap B_2 \cap \cdots \cap B_n \in \mathcal{N}(x)$ だから、
\begin{equation*}
\exists y \in X \, (\langle B_1, y \rangle \in R \land \langle B_2, y \rangle \in R \land \cdots \land \langle B_n, y \rangle \in R)
\end{equation*}
が成り立ち、$R$ は有限共起的である。従って広大性原理によって
\begin{equation*}
\exists y \in {}^*X \, \forall B \in \mathcal{N}(x) \, (\langle {}^*B, y \rangle \in {}^*R)
\end{equation*}
すなわち
\begin{equation*}
\exists y \in {}^*X \, \forall B \in \mathcal{N}(x) \, (y \in {}^*B \setminus {}^*A)
\end{equation*}
が成り立つ。これより
\begin{equation*}
\exists y \in {}^*X \, (y \in \mathrm{monad}(x) \setminus {}^*A)
\end{equation*}
が従い、これは $\mathrm{monad}(x) \not\subseteq {}^*A$ を意味するから矛盾である。□
これを基本として、位相空間の様々な概念を超準モデルの論理式で表すことができます。
(証明)
i) $A$ が開集合 $\quad \Leftrightarrow \quad A$ が $A$ の各点 $x$ の近傍
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in A \, (\mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*A)$
ii) $A$ が閉集合 $\quad \Leftrightarrow \quad X \setminus A$ が開集合
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in X \setminus A \, (\mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*X \setminus {}^*A)$
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in X \, (x \notin A \to \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A = \emptyset)$
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in X \, (\mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset \to x \in A)$
iii) $x$ が $A$ の内点 $\quad \Leftrightarrow \quad A$ が $x$ の近傍 $\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*A$
iv) $x$ が $A$ の触点 $\quad \Leftrightarrow \quad x$ が $X \setminus A$ の内点でない $\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \not\subseteq {}^*X \setminus {}^*A$
$\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset$
v) $x$ が $A$ の境界点 $\quad \Leftrightarrow \quad x$ が $A$ と $X \setminus A$ の両方の触点
$\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset \land \mathrm{monad}(x) \cap ({}^*X \setminus {}^*A) \neq \emptyset$
vi) $x$ が $A$ の孤立点 $\quad \Leftrightarrow \quad \exists B \in \mathcal{N}(x) \, (B \cap A = \{ x \} )$
$\quad \Leftrightarrow \quad \exists B \in \mathcal{N}(x) \, (B \subseteq (X \setminus A) \cup \{ x \} \land x \in A)$
$\quad \Leftrightarrow \quad \exists B \in \mathcal{N}(x) \, ({}^*B \subseteq ({}^*X \setminus {}^*A) \cup \{ x \} \land x \in {}^*A)$ (移行原理)
$\quad \Leftrightarrow \quad \exists B \in \mathscr{P}(X) \, (\mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*B \subseteq ({}^*X \setminus {}^*A) \cup \{ x \} \land x \in {}^*A)$
$\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \subseteq ({}^*X \setminus {}^*A) \cup \{ x \} \land x \in {}^*A$
$\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A = \{ x \}$
vii) $x$ が $A$ の集積点 $\quad \Leftrightarrow \quad$ $x$ が $A$ の触点であり、かつ孤立点でない
$\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset \land \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \{ x \}$
$\quad \Leftrightarrow \quad ( \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A) \setminus \{ x \} \neq \emptyset$
viii) $A$ が自己稠密 $\quad \Leftrightarrow \quad A$ の各点が $A$ の集積点
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in A \, ( ( \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A) \setminus \{ x \} \neq \emptyset )$
ix) $A$ が $X$ において稠密 $\quad \Leftrightarrow \quad X$ の各点が $A$ の触点
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in X \, ( \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset )$
□
【定理3】の表の論理式は、第7回で紹介した距離空間における表の右側欄と同じになっていることがわかります。距離空間は位相空間の特別なものなので、この結果は整合が取れています。
3. 分離公理とコンパクト性
2種類の分離公理について、超準モデルによる同値条件を示します。
(証明)
i) $X$ が $\mathrm{T}_1$ である
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to \exists A \in \mathcal{N}(x) \, (y \notin A) \land \exists B \in \mathcal{N}(y) \, (x \notin B))$
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to \exists A \in \mathcal{N}(x) \, (y \notin {}^*A) \land \exists B \in \mathcal{N}(y) \, (x \notin {}^*B))$ (移行原理)
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to y \notin \mathrm{monad}(x) \land x \notin \mathrm{monad}(y))$
ii) $X$ が $\mathrm{T}_2$(ハウスドルフ)である
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to \exists A \in \mathcal{N}(x) \, \exists B \in \mathcal{N}(y) \, (A \cap B = \emptyset))$
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to \exists A \in \mathcal{N}(x) \, \exists B \in \mathcal{N}(y) \, ({}^*A \cap {}^*B = \emptyset))$ (移行原理)
$\quad \Rightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset )$
逆に $\forall x, y \in X \, (x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset )$ かつ $X$ がハウスドルフでないと仮定すると、ある $x, y \in X, x \neq y$ が存在して、
\begin{equation*}
\forall A \in \mathcal{N}(x) \, \forall B \in \mathcal{N}(y) \, (A \cap B \neq \emptyset))
\end{equation*}
すなわち
\begin{equation*}
\forall A \in \mathcal{N}(x) \, \forall B \in \mathcal{N}(y) \, \exists z \in X \, (z \in A \cap B)
\end{equation*}
となる。そこで $(\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y)) \times X$ 上の関係 $R$ を、
\begin{equation*}
R = \{ \, \langle \langle A, B \rangle , z \rangle \in (\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y)) \times X \, \mid \, z \in A \cap B \, \}
\end{equation*}
によって定めると、$R$ は明らかに有限共起的だから、広大性原理によって、
\begin{equation*}
\exists z \in {}^*X \, \forall A \in \mathcal{N}(x) \, \forall B \in \mathcal{N}(y) \, (z \in {}^*A \cap {}^*B)
\end{equation*}
が成り立つ。よって $\exists z \in {}^*X \, (z \in \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y))$ となるが、これは $\mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset$ と矛盾する。よって、
$\forall x, y \in X \, (x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset ) \quad \Rightarrow \quad X$ が$\mathrm{T}_2$(ハウスドルフ)である
□
この定理より、$\mathrm{T}_1$ 空間は「どの点も他の点のモナドに属さない空間」、ハウスドルフ空間は「異なる点のモナドが交わらない空間」とイメージできます。特にハウスドルフ空間を簡単に言うと「モナドがダブらない空間」です。
また、コンパクト性については、次の非常に簡明な同値条件があります。
(証明)
$\Rightarrow$ の証明:$A$ がコンパクトとする。$\exists y \in {}^*A \, \forall x \in A \, (y \notin \mathrm{monad}(x))$ を仮定して矛盾を導く。これをみたす $y$ をとると、任意の $x \in A$ に対して開近傍 $B(x) \in \mathcal{N}(x) \cap \mathcal{O}$ が存在して $y \notin {}^*B(x)$ となる。すると、
\begin{equation*}
\{ \, B(x) \, \mid \, x \in A \, \}
\end{equation*}
は $A$ の開被覆であり、$A$ はコンパクトだから有限個の $x_1, x_2, \cdots , x_n$ がとれて、
\begin{equation*}
A \subseteq B(x_1) \cup B(x_2) \cup \cdots \cup B(x_n)
\end{equation*}
とすることができる。移行原理より、
\begin{equation*}
{}^*A \subseteq {}^*B(x_1) \cup {}^*B(x_2) \cup \cdots \cup {}^*B(x_n)
\end{equation*}
かつ $y \notin {}^*B(x_1) \cup {}^*B(x_2) \cup \cdots \cup {}^*B(x_n)$ だから $y \notin {}^*A$ となるが、これは矛盾である。
$\Leftarrow$ の証明:$\forall y \in {}^*A \, \exists x \in A \, (y \in \mathrm{monad}(x))$ とする。$A$ がコンパクトでないと仮定して矛盾を導く。$A$ の開被覆 $\mathcal{C}$ で、有限個の元をどのようにとっても $A$ の被覆にならないものが存在する。このとき $\mathcal{C} \times A$ 上の関係 $R$ を、
\begin{equation*}
R = \{ \, \langle B, y \rangle \in \mathcal{C} \times A \, \mid \, y \notin B \, \}
\end{equation*}
によって定めると、任意有限個の $B_1, B_2, \cdots , B_n \in \mathcal{C}$ に対して $A \setminus (B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n) \neq \emptyset$ だから、
\begin{equation*}
\exists y \in A \, (\langle B_1, y \rangle \in R \land \langle B_2, y \rangle \in R \land \cdots \land \langle B_n, y \rangle \in R)
\end{equation*}
となって $R$ は有限共起的である。従って広大性原理より、
\begin{equation*}
\exists y \in {}^*A \, \forall B \in \mathcal{C} \, (\langle {}^*B, y \rangle \in {}^*R)
\end{equation*}
すなわち
\begin{equation*}
\exists y \in {}^*A \, \forall B \in \mathcal{C} \, (y \notin {}^*B)
\end{equation*}
である。これをみたす $y$ をとると、$y \in \mathrm{monad}(x)$ となる $x \in A$ が存在し、この $x$ に対し $x \in B_0 \in \mathcal{C}$ となる開集合 $B_0$ が存在するから、
\begin{equation*}
y \in \mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*B_0
\end{equation*}
すなわち $y \in {}^*B_0$ となるが、一方で $\forall B \in \mathcal{C} \, (y \notin {}^*B)$ より $y \notin {}^*B_0$ だから矛盾である。□
この定理より、コンパクト集合は「超準拡大が各点のモナドで覆い切れる集合」とイメージできます。もっと簡単に言うと「モナドに漏れがない集合」です。この結果も第8回の距離空間に関する結果と整合が取れていることがわかります。
そうすると、ハウスドルフでかつコンパクトな位相空間は「モナドにダブリも漏れもない空間」、どこかで聞いた用語を使うと「モナドがMECEな空間」となります。イメージしやすいですね。
これらの同値条件を使うと、例えば次の定理が論理式を使った簡単な考察だけで証明できます。
(証明)
i) 任意に $y \in {}^*A$ をとる。$X$ がコンパクトだから【定理5】より $y \in \mathrm{monad}(x)$ となる $x \in X$ が存在する。$y \in \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A$ すなわち $\mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset$ で、$A$ は閉集合だから、【定理3】ii) より $x \in A$ となる。従って $\forall y \in {}^*A \, \exists x \in A \, (y \in \mathrm{monad}(x))$ であるから、再び【定理5】より $A$ はコンパクトである。
ii) 任意に $\mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset$ をみたす $x \in X$ をとる。$y \in \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A$ をとると、$A$ がコンパクトだから【定理5】より $y \in \mathrm{monad}(x')$ となる $x' \in A$ がある。$\mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(x') \neq \emptyset$ で $X$ がハウスドルフだから、【定理4】ii) より $x = x'$ であり、これより $x \in A$ となる。従って【定理3】ii) より $A$ は閉集合である。
□
なお、$\exists x \in X \, (y \in \mathrm{monad}(x))$ をみたす $y \in {}^*X$ を ${}^*X$ の近標準点といい、そうでない $y \in {}^*X$ を ${}^*X$ の遠標準点といいます。この用語を使うと、空間 $X$ 自身がコンパクトであることは「すべての ${}^*X$ の点が近標準点である」ことと同値です。
[参考文献]
中村 徹『超準解析と物理学(増補改訂版)』(日本評論社, 2017)
(続く)(前記事)(目次)
(17) 位相空間の超準的考察
第7回で距離空間を超準的に考察しましたが、本記事では一般の位相空間を超準的に考察することにします。位相空間の諸概念が簡単な論理式で表現できて、とても面白いです。
1. 上部構造と広大性原理
位相空間を超準的に考察するためには、超準モデルの「広大性原理」と呼ばれる性質が必要となります。まずこれを極めて雑にですが説明します。
$X$ を無限集合とし、適切な無限集合 $I$ とその上の超フィルターを使って、第6回で示した方法を使って $X$ から超冪 ${}^*X$ を構成します。同一視によって $X \subseteq {}^*X$ とみなし、${}^*X$ は $X$ の真の拡大とすることができます。
さらに考察の対象を広げて、$X$ から始めてその冪集合 $\mathscr{P}(X)$ との和集合 $X \cup \mathscr{P}(X)$ を作り、またその冪集合との和集合を作り、この作業を任意有限回繰り返してできる集合すべての和集合を $\mathcal{U}$ とします。これを「 $X$ の上部構造」と呼びます。また、 ${}^*X$ から始めて同様の操作で作られる「 ${}^*X$ の上部構造」を ${}^*\mathcal{U}$ とします。このとき $\mathcal{U}$ から ${}^*\mathcal{U}$ への写像 ${}^*$ を定義し、任意の $a \in \mathcal{U}$ に対して ${}^*a \in {}^*\mathcal{U}$ を対応させることができます。ただし $x \in X$ に対しては ${}^*x = x$ となります。
本稿ではこうして作った ${}^*\mathcal{U}$ を $\mathcal{U}$ の超準モデルとよび、$a$ に対する ${}^*a$ を $a$ の超準拡大とよぶこととします(あまり標準的なよび方ではないかもしれません)。
集合論言語の論理式 $\varphi(x_1, x_2, \cdots , x_n)$( $x_1, x_2, \cdots , x_n$ 以外に自由変数を持たない)と任意の $a_1, a_2, \cdots , a_n \in \mathcal{U}$ に対して、次の移行原理が成り立ちます。
【移行原理】
$\varphi(x_1, x_2, \cdots , x_n)$ が有界論理式のとき、$\mathcal{U}$ 上で \begin{equation*} \varphi(a_1, a_2, \cdots , a_n) \end{equation*} が成り立つことと、${}^*\mathcal{U}$ 上で \begin{equation*} \varphi({}^*a_1, {}^*a_2, \cdots , {}^*a_n) \end{equation*} が成り立つことは同値である。
$\varphi(x_1, x_2, \cdots , x_n)$ が有界論理式のとき、$\mathcal{U}$ 上で \begin{equation*} \varphi(a_1, a_2, \cdots , a_n) \end{equation*} が成り立つことと、${}^*\mathcal{U}$ 上で \begin{equation*} \varphi({}^*a_1, {}^*a_2, \cdots , {}^*a_n) \end{equation*} が成り立つことは同値である。
ここでは「有界論理式」についての詳細は省略します。移行原理によって、任意の $X$ の部分集合 $A, B$ に対して、例えば ${}^*(A \cap B) = {}^*A \cap {}^*B$ や $A \subseteq B \Leftrightarrow {}^*A \subseteq {}^*B$ などの法則が示されます(第1回を参照)。
これに加え、超冪の構成で使用する $I$ とその上の超フィルターをうまくとると、次の広大性原理とよばれる性質が成り立ちます。
【広大性原理】
$\mathcal{U}$ 上の2項関係 $R \, (\subseteq A \times B, \ A, B \in \mathcal{U})$ が有限共起的であるとする。すなわち任意にとった有限個の $a_1, a_2, \cdots , a_n \in \mathrm{Dom}(R) \subseteq A$ に対して、$\mathcal{U}$ 上で \begin{equation*} \exists b \in B \, (\langle a_1, b \rangle \in R \land \langle a_2, b \rangle \in R \land \cdots \land \langle a_n, b \rangle \in R) \end{equation*} が成り立つとする。このとき ${}^*\mathcal{U}$ 上で次が成り立つ。 \begin{equation*} \exists b \in {}^*B \, \forall a \in \mathrm{Dom}(R) \, (\langle {}^*a, b \rangle \in {}^*R) \end{equation*}
$\mathcal{U}$ 上の2項関係 $R \, (\subseteq A \times B, \ A, B \in \mathcal{U})$ が有限共起的であるとする。すなわち任意にとった有限個の $a_1, a_2, \cdots , a_n \in \mathrm{Dom}(R) \subseteq A$ に対して、$\mathcal{U}$ 上で \begin{equation*} \exists b \in B \, (\langle a_1, b \rangle \in R \land \langle a_2, b \rangle \in R \land \cdots \land \langle a_n, b \rangle \in R) \end{equation*} が成り立つとする。このとき ${}^*\mathcal{U}$ 上で次が成り立つ。 \begin{equation*} \exists b \in {}^*B \, \forall a \in \mathrm{Dom}(R) \, (\langle {}^*a, b \rangle \in {}^*R) \end{equation*}
本記事では、超準モデルでは常に広大性原理が成立するものとします。
2. 位相空間の基本概念の超準的考察
$\langle X, \mathcal{O} \rangle$ を無限個の元をもつ位相空間とします。$\mathcal{O}$ は開集合系で、以降これを簡単に「位相空間 $X$」と呼びます。$x \in X, A \in \mathscr{P}(X)$ に対して $A$ が $x$ の近傍であるとは、$x \in B \subseteq A$ となる開集合 $B$ が存在することです。$x \in X$ に対して $x$ の近傍の全体を $\mathcal{N}(x)$ とかくこととします。
ここで、超準モデルを使ってモナドと呼ばれる次の集合を定義します。
【定義1】(モナド)
$x \in X$ に対し、次によって定まる $^*X$ の部分集合 $\mathrm{monad}(x)$ を「$x$ のモナド」と呼ぶ。 \begin{equation*} \mathrm{monad}(x) = \bigcap \{ \, {}^*A \, \mid \, A \in \mathcal{N}(x) \, \} \end{equation*}
$x \in X$ に対し、次によって定まる $^*X$ の部分集合 $\mathrm{monad}(x)$ を「$x$ のモナド」と呼ぶ。 \begin{equation*} \mathrm{monad}(x) = \bigcap \{ \, {}^*A \, \mid \, A \in \mathcal{N}(x) \, \} \end{equation*}
必ず $x \in \mathrm{monad}(x)$ なので、これは空集合にはなりません。このとき次が成立します。
【定理2】(近傍の超準モデルによる同値条件)
$x \in X, A \in \mathscr{P}(X)$ に対して、次が成立する。 \begin{equation*} A \in \mathcal{N}(x) \quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*A \end{equation*}
$x \in X, A \in \mathscr{P}(X)$ に対して、次が成立する。 \begin{equation*} A \in \mathcal{N}(x) \quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*A \end{equation*}
(証明)
$\Rightarrow$ の証明:モナドの定義から明らか。
$\Leftarrow$ の証明:$\mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*A$ とし、$A \notin \mathcal{N}(x)$ を仮定して矛盾を導く。このとき任意の $B \in \mathcal{N}(x)$ に対して $B \not\subseteq A$ であるから $\exists y \in X \, (y \in B \setminus A)$ である。そこで、$\mathcal{N}(x) \times X$ 上の関係 $R$ を
\begin{equation*}
R = \{ \, \langle B, y \rangle \in \mathcal{N}(x) \times X \, \mid \, y \in B \setminus A \, \}
\end{equation*}
によって定めると、任意有限個の $B_1, B_2, \cdots , B_n \in \mathcal{N}(x)$ に対して $B_1 \cap B_2 \cap \cdots \cap B_n \in \mathcal{N}(x)$ だから、
\begin{equation*}
\exists y \in X \, (\langle B_1, y \rangle \in R \land \langle B_2, y \rangle \in R \land \cdots \land \langle B_n, y \rangle \in R)
\end{equation*}
が成り立ち、$R$ は有限共起的である。従って広大性原理によって
\begin{equation*}
\exists y \in {}^*X \, \forall B \in \mathcal{N}(x) \, (\langle {}^*B, y \rangle \in {}^*R)
\end{equation*}
すなわち
\begin{equation*}
\exists y \in {}^*X \, \forall B \in \mathcal{N}(x) \, (y \in {}^*B \setminus {}^*A)
\end{equation*}
が成り立つ。これより
\begin{equation*}
\exists y \in {}^*X \, (y \in \mathrm{monad}(x) \setminus {}^*A)
\end{equation*}
が従い、これは $\mathrm{monad}(x) \not\subseteq {}^*A$ を意味するから矛盾である。□
これを基本として、位相空間の様々な概念を超準モデルの論理式で表すことができます。
【定理3】(位相空間の諸概念の超準モデルによる同値条件)
$x \in X, A \in \mathscr{P}(X)$ に対して、次表の同値な対応関係が成立する。
$x \in X, A \in \mathscr{P}(X)$ に対して、次表の同値な対応関係が成立する。
| 位相的概念 | 超準モデル上の同値条件 | |
|---|---|---|
| i) | $A$ が開集合 | $\forall x \in A \, (\mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*A)$ |
| ii) | $A$ が閉集合 | $\forall x \in X \, (\mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset \to x \in A)$ |
| iii) | $x$ が $A$ の内点 | $\mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*A$ |
| iv) | $x$ が $A$ の触点 | $\mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset$ |
| v) | $x$ が $A$ の境界点 | $\mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset \land \mathrm{monad}(x) \cap ({}^*X \setminus {}^*A) \neq \emptyset$ |
| vi) | $x$ が $A$ の孤立点 | $\mathrm{monad}(x) \cap {}^*A = \{ x \}$ |
| vii) | $x$ が $A$ の集積点 | $(\mathrm{monad}(x) \cap {}^*A) \setminus \{x\} \neq \emptyset$ |
| viii) | $A$ が自己稠密 | $\forall x \in A \, ((\mathrm{monad}(x) \cap {}^*A) \setminus \{x\} \neq \emptyset)$ |
| ix) | $A$ が $X$ において稠密 | $\forall x \in X \, (\mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset)$ |
(証明)
i) $A$ が開集合 $\quad \Leftrightarrow \quad A$ が $A$ の各点 $x$ の近傍
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in A \, (\mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*A)$
ii) $A$ が閉集合 $\quad \Leftrightarrow \quad X \setminus A$ が開集合
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in X \setminus A \, (\mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*X \setminus {}^*A)$
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in X \, (x \notin A \to \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A = \emptyset)$
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in X \, (\mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset \to x \in A)$
iii) $x$ が $A$ の内点 $\quad \Leftrightarrow \quad A$ が $x$ の近傍 $\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*A$
iv) $x$ が $A$ の触点 $\quad \Leftrightarrow \quad x$ が $X \setminus A$ の内点でない $\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \not\subseteq {}^*X \setminus {}^*A$
$\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset$
v) $x$ が $A$ の境界点 $\quad \Leftrightarrow \quad x$ が $A$ と $X \setminus A$ の両方の触点
$\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset \land \mathrm{monad}(x) \cap ({}^*X \setminus {}^*A) \neq \emptyset$
vi) $x$ が $A$ の孤立点 $\quad \Leftrightarrow \quad \exists B \in \mathcal{N}(x) \, (B \cap A = \{ x \} )$
$\quad \Leftrightarrow \quad \exists B \in \mathcal{N}(x) \, (B \subseteq (X \setminus A) \cup \{ x \} \land x \in A)$
$\quad \Leftrightarrow \quad \exists B \in \mathcal{N}(x) \, ({}^*B \subseteq ({}^*X \setminus {}^*A) \cup \{ x \} \land x \in {}^*A)$ (移行原理)
$\quad \Leftrightarrow \quad \exists B \in \mathscr{P}(X) \, (\mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*B \subseteq ({}^*X \setminus {}^*A) \cup \{ x \} \land x \in {}^*A)$
$\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \subseteq ({}^*X \setminus {}^*A) \cup \{ x \} \land x \in {}^*A$
$\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A = \{ x \}$
vii) $x$ が $A$ の集積点 $\quad \Leftrightarrow \quad$ $x$ が $A$ の触点であり、かつ孤立点でない
$\quad \Leftrightarrow \quad \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset \land \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \{ x \}$
$\quad \Leftrightarrow \quad ( \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A) \setminus \{ x \} \neq \emptyset$
viii) $A$ が自己稠密 $\quad \Leftrightarrow \quad A$ の各点が $A$ の集積点
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in A \, ( ( \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A) \setminus \{ x \} \neq \emptyset )$
ix) $A$ が $X$ において稠密 $\quad \Leftrightarrow \quad X$ の各点が $A$ の触点
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x \in X \, ( \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset )$
□
【定理3】の表の論理式は、第7回で紹介した距離空間における表の右側欄と同じになっていることがわかります。距離空間は位相空間の特別なものなので、この結果は整合が取れています。
3. 分離公理とコンパクト性
2種類の分離公理について、超準モデルによる同値条件を示します。
【定理4】($\mathrm{T}_1, \mathrm{T}_2$ 分離公理の超準モデルによる同値条件)
i) $X$ が $\mathrm{T}_1$ である $\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to y \notin \mathrm{monad}(x) \land x \notin \mathrm{monad}(y))$
ii) $X$ が $\mathrm{T}_2$(ハウスドルフ)である $\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset )$
i) $X$ が $\mathrm{T}_1$ である $\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to y \notin \mathrm{monad}(x) \land x \notin \mathrm{monad}(y))$
ii) $X$ が $\mathrm{T}_2$(ハウスドルフ)である $\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset )$
(証明)
i) $X$ が $\mathrm{T}_1$ である
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to \exists A \in \mathcal{N}(x) \, (y \notin A) \land \exists B \in \mathcal{N}(y) \, (x \notin B))$
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to \exists A \in \mathcal{N}(x) \, (y \notin {}^*A) \land \exists B \in \mathcal{N}(y) \, (x \notin {}^*B))$ (移行原理)
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to y \notin \mathrm{monad}(x) \land x \notin \mathrm{monad}(y))$
ii) $X$ が $\mathrm{T}_2$(ハウスドルフ)である
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to \exists A \in \mathcal{N}(x) \, \exists B \in \mathcal{N}(y) \, (A \cap B = \emptyset))$
$\quad \Leftrightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to \exists A \in \mathcal{N}(x) \, \exists B \in \mathcal{N}(y) \, ({}^*A \cap {}^*B = \emptyset))$ (移行原理)
$\quad \Rightarrow \quad \forall x, y \in X \, (x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset )$
逆に $\forall x, y \in X \, (x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset )$ かつ $X$ がハウスドルフでないと仮定すると、ある $x, y \in X, x \neq y$ が存在して、
\begin{equation*}
\forall A \in \mathcal{N}(x) \, \forall B \in \mathcal{N}(y) \, (A \cap B \neq \emptyset))
\end{equation*}
すなわち
\begin{equation*}
\forall A \in \mathcal{N}(x) \, \forall B \in \mathcal{N}(y) \, \exists z \in X \, (z \in A \cap B)
\end{equation*}
となる。そこで $(\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y)) \times X$ 上の関係 $R$ を、
\begin{equation*}
R = \{ \, \langle \langle A, B \rangle , z \rangle \in (\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y)) \times X \, \mid \, z \in A \cap B \, \}
\end{equation*}
によって定めると、$R$ は明らかに有限共起的だから、広大性原理によって、
\begin{equation*}
\exists z \in {}^*X \, \forall A \in \mathcal{N}(x) \, \forall B \in \mathcal{N}(y) \, (z \in {}^*A \cap {}^*B)
\end{equation*}
が成り立つ。よって $\exists z \in {}^*X \, (z \in \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y))$ となるが、これは $\mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset$ と矛盾する。よって、
$\forall x, y \in X \, (x \neq y \to \mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(y) = \emptyset ) \quad \Rightarrow \quad X$ が$\mathrm{T}_2$(ハウスドルフ)である
□
この定理より、$\mathrm{T}_1$ 空間は「どの点も他の点のモナドに属さない空間」、ハウスドルフ空間は「異なる点のモナドが交わらない空間」とイメージできます。特にハウスドルフ空間を簡単に言うと「モナドがダブらない空間」です。
また、コンパクト性については、次の非常に簡明な同値条件があります。
【定理5】(コンパクト性の超準モデルによる同値条件)
$A \subseteq X$ とすると、次が成立する。
$A \subseteq X$ とすると、次が成立する。
$A$ がコンパクトである $\quad \Leftrightarrow \quad \forall y \in {}^*A \, \exists x \in A \, (y \in \mathrm{monad}(x))$
(証明)
$\Rightarrow$ の証明:$A$ がコンパクトとする。$\exists y \in {}^*A \, \forall x \in A \, (y \notin \mathrm{monad}(x))$ を仮定して矛盾を導く。これをみたす $y$ をとると、任意の $x \in A$ に対して開近傍 $B(x) \in \mathcal{N}(x) \cap \mathcal{O}$ が存在して $y \notin {}^*B(x)$ となる。すると、
\begin{equation*}
\{ \, B(x) \, \mid \, x \in A \, \}
\end{equation*}
は $A$ の開被覆であり、$A$ はコンパクトだから有限個の $x_1, x_2, \cdots , x_n$ がとれて、
\begin{equation*}
A \subseteq B(x_1) \cup B(x_2) \cup \cdots \cup B(x_n)
\end{equation*}
とすることができる。移行原理より、
\begin{equation*}
{}^*A \subseteq {}^*B(x_1) \cup {}^*B(x_2) \cup \cdots \cup {}^*B(x_n)
\end{equation*}
かつ $y \notin {}^*B(x_1) \cup {}^*B(x_2) \cup \cdots \cup {}^*B(x_n)$ だから $y \notin {}^*A$ となるが、これは矛盾である。
$\Leftarrow$ の証明:$\forall y \in {}^*A \, \exists x \in A \, (y \in \mathrm{monad}(x))$ とする。$A$ がコンパクトでないと仮定して矛盾を導く。$A$ の開被覆 $\mathcal{C}$ で、有限個の元をどのようにとっても $A$ の被覆にならないものが存在する。このとき $\mathcal{C} \times A$ 上の関係 $R$ を、
\begin{equation*}
R = \{ \, \langle B, y \rangle \in \mathcal{C} \times A \, \mid \, y \notin B \, \}
\end{equation*}
によって定めると、任意有限個の $B_1, B_2, \cdots , B_n \in \mathcal{C}$ に対して $A \setminus (B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n) \neq \emptyset$ だから、
\begin{equation*}
\exists y \in A \, (\langle B_1, y \rangle \in R \land \langle B_2, y \rangle \in R \land \cdots \land \langle B_n, y \rangle \in R)
\end{equation*}
となって $R$ は有限共起的である。従って広大性原理より、
\begin{equation*}
\exists y \in {}^*A \, \forall B \in \mathcal{C} \, (\langle {}^*B, y \rangle \in {}^*R)
\end{equation*}
すなわち
\begin{equation*}
\exists y \in {}^*A \, \forall B \in \mathcal{C} \, (y \notin {}^*B)
\end{equation*}
である。これをみたす $y$ をとると、$y \in \mathrm{monad}(x)$ となる $x \in A$ が存在し、この $x$ に対し $x \in B_0 \in \mathcal{C}$ となる開集合 $B_0$ が存在するから、
\begin{equation*}
y \in \mathrm{monad}(x) \subseteq {}^*B_0
\end{equation*}
すなわち $y \in {}^*B_0$ となるが、一方で $\forall B \in \mathcal{C} \, (y \notin {}^*B)$ より $y \notin {}^*B_0$ だから矛盾である。□
この定理より、コンパクト集合は「超準拡大が各点のモナドで覆い切れる集合」とイメージできます。もっと簡単に言うと「モナドに漏れがない集合」です。この結果も第8回の距離空間に関する結果と整合が取れていることがわかります。
そうすると、ハウスドルフでかつコンパクトな位相空間は「モナドにダブリも漏れもない空間」、どこかで聞いた用語を使うと「モナドがMECEな空間」となります。イメージしやすいですね。
これらの同値条件を使うと、例えば次の定理が論理式を使った簡単な考察だけで証明できます。
【定理6】$A \subseteq X$ とすると、次が成立する。
i) $X$ がコンパクトのとき、$A$ が閉集合ならばコンパクトである。
ii) $X$ がハウスドルフのとき、$A$ がコンパクトならば閉集合である。
i) $X$ がコンパクトのとき、$A$ が閉集合ならばコンパクトである。
ii) $X$ がハウスドルフのとき、$A$ がコンパクトならば閉集合である。
(証明)
i) 任意に $y \in {}^*A$ をとる。$X$ がコンパクトだから【定理5】より $y \in \mathrm{monad}(x)$ となる $x \in X$ が存在する。$y \in \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A$ すなわち $\mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset$ で、$A$ は閉集合だから、【定理3】ii) より $x \in A$ となる。従って $\forall y \in {}^*A \, \exists x \in A \, (y \in \mathrm{monad}(x))$ であるから、再び【定理5】より $A$ はコンパクトである。
ii) 任意に $\mathrm{monad}(x) \cap {}^*A \neq \emptyset$ をみたす $x \in X$ をとる。$y \in \mathrm{monad}(x) \cap {}^*A$ をとると、$A$ がコンパクトだから【定理5】より $y \in \mathrm{monad}(x')$ となる $x' \in A$ がある。$\mathrm{monad}(x) \cap \mathrm{monad}(x') \neq \emptyset$ で $X$ がハウスドルフだから、【定理4】ii) より $x = x'$ であり、これより $x \in A$ となる。従って【定理3】ii) より $A$ は閉集合である。
□
なお、$\exists x \in X \, (y \in \mathrm{monad}(x))$ をみたす $y \in {}^*X$ を ${}^*X$ の近標準点といい、そうでない $y \in {}^*X$ を ${}^*X$ の遠標準点といいます。この用語を使うと、空間 $X$ 自身がコンパクトであることは「すべての ${}^*X$ の点が近標準点である」ことと同値です。
[参考文献]
中村 徹『超準解析と物理学(増補改訂版)』(日本評論社, 2017)
(続く)(前記事)(目次)
ウカシェビッチの公理系から全トートロジーが証明可能なことを証明する(勉強ノート) [数学]
命題論理において、最小限の公理系によって形式化された体系として、ポーランドのヤン・ウカシェビッチが考案した公理系が知られています。この体系を使うと、命題論理の全てのトートロジー(恒真式)が形式的に証明できます。面白そうだったので自分で実際にやってみましたが、あまり簡単ではなくパズルみたいな面白さがありましたので、本記事ではこれを一通り紹介します。
1. 論理式と形式的証明の定義
まず、本記事における論理式を次で定義します。
以下、論理式の記述において、カッコは紛れがない限り省略し、論理演算子 $\lnot, \to$ の結合は $\lnot$ が $\to$ より強いものとします。例えば $\lnot A \to B$ は正式には $(\lnot (A)) \to (B)$ のことです。
一般の論理体系では他に $\lor, \land, \leftrightarrow$ といった論理演算子も使われますが、本記事ではこれらは略記法とみなします。つまり、
i) $A \lor B$ は $\lnot A \to B$ の略記
ii) $A \land B$ は $\lnot(A \to \lnot B)$ の略記
iii) $A \leftrightarrow B$ は $(A \to B) \land (B \to A)$ の略記
とします。本記事では最後までこれらの論理演算子は使わず、$\lnot$ と $\to$ だけで突っ走ります。
次に、論理の公理を定義します。ウカシェビッチの公理系といわれるものです。
これらを使って、次によって形式的証明が定義されます。
この定義の iii) で、「$B_j$ と $B_j \to B_i$ から $B_i$ を推論すること」が形式的証明における推論規則として定められています。この推論規則をモーダス・ポーネンスといい、以下「MP」と略記します。本記事で使う推論規則はMPだけです。
このように定義した形式的証明と、体系を外から取り扱う(メタ理論としての)証明は、ごっちゃになると紛らわしいので本記事では言葉を使い分けます。
2. いろいろな論理の定理の形式的証明
この体系でいろいろな論理式が論理の定理であることの形式的証明が得られます。公理の種類が少ないだけにその形式的証明はいささかトリッキーです。
まず最初に、一見あたりまえのような次の論理式を形式的に証明します。
(証明)
次は $A \to A$ の形式的証明である。各行の頭の (a),(b),…は識別記号であり、: の右側の記述は形式的証明に使われた根拠を表す。
□
このように、形式的証明をまじめにやると意外と手間がかかります。そこで、少しでも手間を省く強力な手法である演繹定理を先に証明します。
(証明)
$(2)$から$(1)$はMPより明らかなので、$(1)$から$(2)$を証明する。$(1)$より $\Sigma \cup \{A\}$ から $B$ への形式的証明となる論理式の列 $C_1, C_2, \cdots, C_{n-1}, B$ がある。形式的証明の長さ $n$ に関する帰納法を用いる。すなわち、$C_i \ (i < n)$ については全て $\Sigma \vdash A \to C_i$ であると仮定する。形式的証明の定義から $B$ について場合分けする。
i) $B$ が $\Sigma$ の要素(前提)、または論理の公理[A1] $\sim$ [A3]のいずれかのとき:
次は $\Sigma$ からの $A \to B$ の形式的証明である。
ii) $B$ が $A$ のとき:
[T1] が論理の定理だから $\vdash A \to A$ すなわち $\vdash A \to B$ である。
iii) $B$ がある $C_i, C_j \ (i,j < n)$ からMPによって得られるとき、すなわち $C_j$ が $C_i \to B$ のとき:
帰納法の仮定より $\Sigma \vdash A \to C_i$ かつ $\Sigma \vdash A \to (C_i \to B)$ である。従ってこれらの形式的証明となる論理式の列を連結し、それに次の論理式の列を追加することにより、$\Sigma$ からの $A \to B$ の形式的証明が得られる。
以上より全ての場合について$(2)$が示された。
□
演繹定理を利用すると、以下次々と論理の定理が形式的に証明できます。
(証明)
[T2] 演繹定理より $\{ \lnot A \} \vdash A \to B$ を示せばよい。
[T3] $\{ \lnot \lnot A \} \vdash A$ を示せばよい。
[T4]
[T5] $\{ A \to (B \to C), B, A \} \vdash C$ を示せばよい。
[T6] $\{ A \to B, B \to C, A \} \vdash C$ を示せばよい。
[T7] $\{ \lnot A \to A \} \vdash A$ を示せばよい。
[T8] $\{ A \to B, \lnot A \to B \} \vdash B$ を示せばよい。
[T9] $\{ A \to B \} \vdash \lnot B \to \lnot A$ を示せばよい。
[T10] $\{ A \} \vdash \lnot B \to \lnot(A \to B)$ を示せばよい。
□
このようにして、論理の定理がいくらでも形式的に証明できますが、キリがないのでここでやめておきます。
3. トートロジーが形式的証明可能なことの証明
ここまでの議論では、論理演算子 $\lnot, \to$ や推論規則には何の意味もなく、形式的証明はただ記号列を規則に従って並べているだけでした。これから論理演算子に意味を持たせ、論理式の真偽を定義します。
トートロジーを言い換えると、原始命題の真理値をどのように割り当てても真になる論理式ということです。定義から具体的に検証することによって、論理の公理 [A1] $\sim$ [A3] は全てトートロジーになることが分かります。
このように論理式に真偽の意味を持たせると、形式的証明が次の定理によって意味づけされます。
(証明)
$\Sigma \vdash A$ かつ $\Sigma$ の要素が全て真とする。$\Sigma$ から $A$ への形式的証明を $B_1, B_2, \cdots, B_{n-1}, A$ とし、$i < n$ に対して定理が成り立つ、すなわち $\Sigma \models B_i \ (i < n)$ であると仮定すると、$B_i \ (i < n)$ は全て真である。
i) $A$ が $\Sigma$ の要素のとき:
明らかに $A$ は真である。
ii) $A$ が [A1] $\sim$ [A3] のいずれかのとき:
[A1] $\sim$ [A3] はどれもトートロジーだから、やはり $A$ は真 である。
iii) ある $B_i, B_j \ (i,j < n)$ に対して $B_j$ が $B_i \to A$ のとき:
$B_i$ が真、かつ $B_i \to A$ が真 であるから、【定義7】iii) より $A$ は真でなければならない。
以上より全ての場合で $A$ が真であるから、形式的証明の長さ $n$ に関する帰納法によって $\Sigma \models A$ が示された。
□
つまり「形式的に証明できれば論理的に正しい」と言って良いわけです。これによって、論理の定理は前提なしで形式的に証明できるので、全てトートロジーです。
逆に、トートロジーが全て形式的に証明できること、すなわち論理の定理であることの証明に進みます。準備として、論理式の真理値と形式的証明の関係がよくわかる次の補題を証明します。
(証明)
論理式 $A$ の構成に関する帰納法を用いる。
i) $A$ が原始命題 $P$ のとき:
(a) $P$ が真のとき $A$ は真である。このとき $\{ P \} \vdash P$ は自明だから $\{ P \} \vdash A$ となり、$(3)$が成立する。
(b) $P$ が偽のとき $A$ は偽である。このとき $\{ \lnot P \} \vdash \lnot P$ は自明だから $\{ \lnot P \} \vdash \lnot A$ となり、$(4)$が成立する。
ii) $A$ が $\lnot B$ で、$B$ について補題が成立するとき:
(a) $P_1, \cdots , P_m$ が真、$P_{m+1}, \cdots , P_n$ が偽のときに $A$ が真ならば、このとき $B$ は偽であるから、
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash \lnot B
\end{equation*}
である。$\lnot B$ は $A$ だから$(3)$が成立する。
(b) $P_1, \cdots , P_m$ が真、$P_{m+1}, \cdots , P_n$ が偽のときに $A$ が偽ならば、このとき $B$ は真であるから、
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash B
\end{equation*}
であり、さらに [T4] より $\vdash B \to \lnot \lnot B$ だから、
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash \lnot \lnot B
\end{equation*}
である。$\lnot B$ は $A$ だから$(4)$が成立する。
iii) $A$ が $B \to C$ で、$B$ と $C$ について補題が成立するとき:
(a) $P_1, \cdots , P_m$ が真、$P_{m+1}, \cdots , P_n$ が偽のときに $A$ が真ならば、このとき $B$ が偽であるか、または $C$ が真である。
$B$ が偽の場合は、
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash \lnot B
\end{equation*}
であり、さらに [T2] より $\vdash \lnot B \to (B \to C)$ だから、
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash B \to C
\end{equation*}
である。$B \to C$ は $A$ だから$(3)$が成立する。
$C$ が真の場合は、
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash C
\end{equation*}
であり、さらに [A1] より $\vdash C \to (B \to C)$ だから、
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash B \to C
\end{equation*}
である。$B \to C$ は $A$ だから$(3)$が成立する。
(b) $P_1, \cdots , P_m$ が真、$P_{m+1}, \cdots , P_n$ が偽のときに $A$ が偽ならば、このとき $B$ が真かつ $C$ が偽であるから、
\begin{eqnarray*}
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} &\vdash& B \\
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} &\vdash& \lnot C
\end{eqnarray*}
であり、さらに [T10] より $\vdash B \to (\lnot C \to \lnot (B \to C))$ だから、
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash \lnot (B \to C)
\end{equation*}
である。$B \to C$ は $A$ だから$(4)$が成立する。
以上より、全ての論理式 $A$ に対して補題が証明できた。
□
この補題を使って、本記事の目的である次の定理を証明します。
(証明)
$\models A$ とする。$A$ を構成する原始命題を全て取り出し $P_1, P_2, \cdots , P_n$ とすると、これらの真理値がどのように割り当てられても $A$ は真である。特に $P_n$ に注目すると、【補題10】より、
\begin{eqnarray*}
\{ P_1, \cdots , P_{n-1}, P_n \} &\vdash& A \\
\{ P_1, \cdots , P_{n-1}, \lnot P_n \} &\vdash& A
\end{eqnarray*}
である。これから演繹定理より、
\begin{eqnarray*}
\{ P_1, \cdots , P_{n-1} \} &\vdash& P_n \to A \\
\{ P_1, \cdots , P_{n-1} \} &\vdash& \lnot P_n \to A
\end{eqnarray*}
となる。一方 [T8] より、
\begin{equation*}
\vdash (P_n \to A) \to ((\lnot P_n \to A) \to A)
\end{equation*}
であるから、
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_{n-2}, P_{n-1} \} \vdash A
\end{equation*}
が得られる。同様に、
\begin{eqnarray*}
\{ P_1, \cdots , P_{n-2}, \lnot P_{n-1}, P_n \} &\vdash& A \\
\{ P_1, \cdots , P_{n-2}, \lnot P_{n-1}, \lnot P_n \} &\vdash& A
\end{eqnarray*}
から
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_{n-2}, \lnot P_{n-1} \} \vdash A
\end{equation*}
が得られる。従って、
\begin{eqnarray*}
\{ P_1, \cdots , P_{n-2}, P_{n-1} \} \vdash A \\
\{ P_1, \cdots , P_{n-2}, \lnot P_{n-1} \} \vdash A
\end{eqnarray*}
である。以下この操作を次々繰り返すと、最終的に
\begin{equation*}
\vdash A
\end{equation*}
が得られる。
□
たった3種類の公理系と1つの推論規則から全てのトートロジーが形式的に証明できることが、これで確認できました。
1. 論理式と形式的証明の定義
まず、本記事における論理式を次で定義します。
【定義1】(論理式)記号の集合として、原始命題と呼ばれる無限個の記号 $P_1 \ P_2 \ \cdots$ と、論理演算子と呼ばれる2個の記号 $\lnot \ \to$ およびカッコ $( \ )$ がある。このとき、次によって帰納的に定まる記号の列を論理式と呼ぶ。
i) 原始命題 $P_1, P_2, \cdots$ はそれぞれ論理式である。
ii) $A$ が論理式ならば $\lnot (A)$ は論理式である。
iii) $A, B$ が論理式ならば $(A) \to (B)$ は論理式である。
iv) 以上で定義されるものだけが論理式である。
i) 原始命題 $P_1, P_2, \cdots$ はそれぞれ論理式である。
ii) $A$ が論理式ならば $\lnot (A)$ は論理式である。
iii) $A, B$ が論理式ならば $(A) \to (B)$ は論理式である。
iv) 以上で定義されるものだけが論理式である。
以下、論理式の記述において、カッコは紛れがない限り省略し、論理演算子 $\lnot, \to$ の結合は $\lnot$ が $\to$ より強いものとします。例えば $\lnot A \to B$ は正式には $(\lnot (A)) \to (B)$ のことです。
一般の論理体系では他に $\lor, \land, \leftrightarrow$ といった論理演算子も使われますが、本記事ではこれらは略記法とみなします。つまり、
i) $A \lor B$ は $\lnot A \to B$ の略記
ii) $A \land B$ は $\lnot(A \to \lnot B)$ の略記
iii) $A \leftrightarrow B$ は $(A \to B) \land (B \to A)$ の略記
とします。本記事では最後までこれらの論理演算子は使わず、$\lnot$ と $\to$ だけで突っ走ります。
次に、論理の公理を定義します。ウカシェビッチの公理系といわれるものです。
【定義2】(論理の公理)$A,B,C$ が任意の論理式のとき、次の3種類の論理式を論理の公理という。
[A1] $A \to (B \to A)$
[A2] $(A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))$
[A3] $(\lnot B \to \lnot A) \to (A \to B)$
[A1] $A \to (B \to A)$
[A2] $(A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))$
[A3] $(\lnot B \to \lnot A) \to (A \to B)$
これらを使って、次によって形式的証明が定義されます。
【定義3】(形式的証明)$\Sigma$を論理式の集合、$A$ を論理式とする。論理式の有限個の列 $B_1, B_2, \cdots, B_{n-1}, B_n$ があり、$B_n$ が $A$ であって、かつ各々の $B_i$ が、
i) $\Sigma$ の要素である。
ii) 論理の公理 [A1] $\sim$ [A3] のいずれかである。
iii) ある $B_j, B_k \ (j,k < i)$ があって、$B_k$ が $B_j \to B_i$ となっている。
のいずれかをみたすとき、$A$ は $\Sigma$ から形式的証明可能といい、 \begin{equation*} \Sigma \vdash A \end{equation*} と書く。このとき、論理式の列 $B_1, B_2, \cdots, B_{n-1}, A$ を 「$\Sigma$ からの $A$ の形式的証明」といい、$\Sigma$ の要素となる論理式を前提、$A$ を結論という。
$\Sigma$ が空集合のとき、$\Sigma \vdash A$ を $\vdash A$ と書き、このとき $A$ を論理の定理という。
i) $\Sigma$ の要素である。
ii) 論理の公理 [A1] $\sim$ [A3] のいずれかである。
iii) ある $B_j, B_k \ (j,k < i)$ があって、$B_k$ が $B_j \to B_i$ となっている。
のいずれかをみたすとき、$A$ は $\Sigma$ から形式的証明可能といい、 \begin{equation*} \Sigma \vdash A \end{equation*} と書く。このとき、論理式の列 $B_1, B_2, \cdots, B_{n-1}, A$ を 「$\Sigma$ からの $A$ の形式的証明」といい、$\Sigma$ の要素となる論理式を前提、$A$ を結論という。
$\Sigma$ が空集合のとき、$\Sigma \vdash A$ を $\vdash A$ と書き、このとき $A$ を論理の定理という。
この定義の iii) で、「$B_j$ と $B_j \to B_i$ から $B_i$ を推論すること」が形式的証明における推論規則として定められています。この推論規則をモーダス・ポーネンスといい、以下「MP」と略記します。本記事で使う推論規則はMPだけです。
このように定義した形式的証明と、体系を外から取り扱う(メタ理論としての)証明は、ごっちゃになると紛らわしいので本記事では言葉を使い分けます。
2. いろいろな論理の定理の形式的証明
この体系でいろいろな論理式が論理の定理であることの形式的証明が得られます。公理の種類が少ないだけにその形式的証明はいささかトリッキーです。
まず最初に、一見あたりまえのような次の論理式を形式的に証明します。
【定理4】$A$ を任意の論理式とする。次の論理式は論理の定理である。
[T1] $A \to A$
[T1] $A \to A$
(証明)
次は $A \to A$ の形式的証明である。各行の頭の (a),(b),…は識別記号であり、: の右側の記述は形式的証明に使われた根拠を表す。
| (a) | $A \to ((A \to A) \to A)$ | : [A1] |
| (b) | $(A \to ((A \to A) \to A)) \to ((A \to (A \to A)) \to (A \to A))$ | : [A2] |
| (c) | $(A \to (A \to A)) \to (A \to A)$ | : (a),(b),MP |
| (d) | $A \to (A \to A)$ | : [A1] |
| (e) | $A \to A$ | : (d),(c),MP |
□
このように、形式的証明をまじめにやると意外と手間がかかります。そこで、少しでも手間を省く強力な手法である演繹定理を先に証明します。
【定理5】(演繹定理)$\Sigma$を論理式の集合、$A, B$ を論理式とするとき、
\begin{equation} \tag{1}
\Sigma \cup \{A\} \vdash B
\end{equation}
であることと、
\begin{equation} \tag{2}
\Sigma \vdash A \to B
\end{equation}
であることとは同値である。
(証明)
$(2)$から$(1)$はMPより明らかなので、$(1)$から$(2)$を証明する。$(1)$より $\Sigma \cup \{A\}$ から $B$ への形式的証明となる論理式の列 $C_1, C_2, \cdots, C_{n-1}, B$ がある。形式的証明の長さ $n$ に関する帰納法を用いる。すなわち、$C_i \ (i < n)$ については全て $\Sigma \vdash A \to C_i$ であると仮定する。形式的証明の定義から $B$ について場合分けする。
i) $B$ が $\Sigma$ の要素(前提)、または論理の公理[A1] $\sim$ [A3]のいずれかのとき:
次は $\Sigma$ からの $A \to B$ の形式的証明である。
| (a) | $B$ | : 前提または論理の公理 |
| (b) | $B \to (A \to B)$ | : [A1] |
| (c) | $A \to B$ | : (a),(b),MP |
ii) $B$ が $A$ のとき:
[T1] が論理の定理だから $\vdash A \to A$ すなわち $\vdash A \to B$ である。
iii) $B$ がある $C_i, C_j \ (i,j < n)$ からMPによって得られるとき、すなわち $C_j$ が $C_i \to B$ のとき:
帰納法の仮定より $\Sigma \vdash A \to C_i$ かつ $\Sigma \vdash A \to (C_i \to B)$ である。従ってこれらの形式的証明となる論理式の列を連結し、それに次の論理式の列を追加することにより、$\Sigma$ からの $A \to B$ の形式的証明が得られる。
| (a) | $(A \to (C_i \to B)) \to ((A \to C_i) \to (A \to B))$ | : [A2] |
| (b) | $(A \to C_i) \to (A \to B)$ | : $A \to (C_i \to B)$, (a), MP |
| (c) | $A \to B$ | : $A \to C_i$, (b), MP |
以上より全ての場合について$(2)$が示された。
□
演繹定理を利用すると、以下次々と論理の定理が形式的に証明できます。
【定理6】$A,B,C$ を任意の論理式とする。次の各々は論理の定理である。
[T2] $\lnot A \to (A \to B)$
[T3] $\lnot \lnot A \to A$
[T4] $A \to \lnot \lnot A$
[T5] $(A \to (B \to C)) \to (B \to (A \to C))$
[T6] $(A \to B) \to ((B \to C) \to (A \to C))$
[T7] $(\lnot A \to A) \to A$
[T8] $(A \to B) \to ((\lnot A \to B) \to B)$
[T9] $(A \to B) \to (\lnot B \to \lnot A)$
[T10] $A \to (\lnot B \to \lnot(A \to B))$
[T2] $\lnot A \to (A \to B)$
[T3] $\lnot \lnot A \to A$
[T4] $A \to \lnot \lnot A$
[T5] $(A \to (B \to C)) \to (B \to (A \to C))$
[T6] $(A \to B) \to ((B \to C) \to (A \to C))$
[T7] $(\lnot A \to A) \to A$
[T8] $(A \to B) \to ((\lnot A \to B) \to B)$
[T9] $(A \to B) \to (\lnot B \to \lnot A)$
[T10] $A \to (\lnot B \to \lnot(A \to B))$
(証明)
[T2] 演繹定理より $\{ \lnot A \} \vdash A \to B$ を示せばよい。
| (a) | $\lnot A$ | : 前提 |
| (b) | $\lnot A \to (\lnot B \to \lnot A)$ | : [A1] |
| (c) | $\lnot B \to \lnot A$ | : (a),(b),MP |
| (d) | $(\lnot B \to \lnot A) \to (A \to B)$ | : [A3] |
| (e) | $A \to B$ | : (c),(d),MP |
[T3] $\{ \lnot \lnot A \} \vdash A$ を示せばよい。
| (a) | $\lnot \lnot A$ | : 前提 |
| (b) | $\lnot \lnot A \to (\lnot A \to \lnot \lnot \lnot A)$ | : [T2] |
| (c) | $\lnot A \to \lnot \lnot \lnot A$ | : (a),(b),MP |
| (d) | $(\lnot A \to \lnot \lnot \lnot A) \to (\lnot \lnot A \to A)$ | : [A3] |
| (e) | $\lnot \lnot A \to A$ | : (c),(d),MP |
| (f) | $A$ | : (a),(e),MP |
[T4]
| (a) | $\lnot \lnot \lnot A \to \lnot A$ | : [T3] |
| (b) | $(\lnot \lnot \lnot A \to \lnot A) \to (A \to \lnot \lnot A)$ | : [A3] |
| (c) | $A \to \lnot \lnot A$ | : (a),(b),MP |
[T5] $\{ A \to (B \to C), B, A \} \vdash C$ を示せばよい。
| (a) | $A$ | : 前提 |
| (b) | $A \to (B \to C)$ | : 前提 |
| (c) | $B \to C$ | : (a),(b),MP |
| (d) | $B$ | : 前提 |
| (e) | $C$ | : (d),(c),MP |
[T6] $\{ A \to B, B \to C, A \} \vdash C$ を示せばよい。
| (a) | $A$ | : 前提 |
| (b) | $A \to B$ | : 前提 |
| (c) | $B$ | : (a),(b),MP |
| (d) | $B \to C$ | : 前提 |
| (e) | $C$ | : (c),(d),MP |
[T7] $\{ \lnot A \to A \} \vdash A$ を示せばよい。
| (a) | $\lnot A \to (A \to \lnot (A \to A))$ | : [T2] |
| (b) | $(\lnot A \to (A \to \lnot (A \to A))) \to ((\lnot A \to A) \to (\lnot A \to \lnot (A \to A)))$ | : [A2] |
| (c) | $(\lnot A \to A) \to (\lnot A \to \lnot (A \to A))$ | : (a),(b),MP |
| (d) | $\lnot A \to A$ | : 前提 |
| (e) | $\lnot A \to \lnot (A \to A)$ | : (d),(c),MP |
| (f) | $(\lnot A \to \lnot (A \to A)) \to ((A \to A) \to A)$ | : [A3] |
| (g) | $(A \to A) \to A$ | : (e),(f),MP |
| (h) | $A \to A$ | : [T1] |
| (i) | $A$ | : (h),(g),MP |
[T8] $\{ A \to B, \lnot A \to B \} \vdash B$ を示せばよい。
| (a) | $\lnot A \to B$ | : 前提 |
| (b) | $(\lnot A \to B) \to ((B \to \lnot \lnot B) \to (\lnot A \to \lnot \lnot B))$ | : [T6] |
| (c) | $(B \to \lnot \lnot B) \to (\lnot A \to \lnot \lnot B)$ | : (a),(b),MP |
| (d) | $B \to \lnot \lnot B$ | : [T4] |
| (e) | $\lnot A \to \lnot \lnot B$ | : (d),(c),MP |
| (f) | $(\lnot A \to \lnot \lnot B) \to (\lnot B \to A)$ | : [A3] |
| (g) | $\lnot B \to A$ | : (e),(f),MP |
| (h) | $(\lnot B \to A) \to ((A \to B) \to (\lnot B \to B))$ | : [T6] |
| (i) | $(A \to B) \to (\lnot B \to B)$ | : (g),(h),MP |
| (j) | $A \to B$ | : 前提 |
| (k) | $\lnot B \to B$ | : (j),(i),MP |
| (l) | $(\lnot B \to B) \to B$ | : [T7] |
| (m) | $B$ | : (k),(l),MP |
[T9] $\{ A \to B \} \vdash \lnot B \to \lnot A$ を示せばよい。
| (a) | $A \to B$ | : 前提 |
| (b) | $(A \to B) \to ((B \to \lnot \lnot B) \to (A \to \lnot \lnot B))$ | : [T6] |
| (c) | $(B \to \lnot \lnot B) \to (A \to \lnot \lnot B)$ | : (a),(b),MP |
| (d) | $B \to \lnot \lnot B$ | : [T4] |
| (e) | $A \to \lnot \lnot B$ | : (d),(c),MP |
| (f) | $\lnot \lnot A \to A$ | : [T3] |
| (g) | $(\lnot \lnot A \to A) \to ((A \to \lnot \lnot B) \to (\lnot \lnot A \to \lnot \lnot B))$ | : [T6] |
| (h) | $(A \to \lnot \lnot B) \to (\lnot \lnot A \to \lnot \lnot B)$ | : (f),(g),MP |
| (i) | $\lnot \lnot A \to \lnot \lnot B$ | : (e),(h),MP |
| (j) | $(\lnot \lnot A \to \lnot \lnot B) \to (\lnot B \to \lnot A)$ | : [A3] |
| (k) | $\lnot B \to \lnot A$ | : (i),(j),MP |
[T10] $\{ A \} \vdash \lnot B \to \lnot(A \to B)$ を示せばよい。
| (a) | $(A \to B) \to (A \to B)$ | : [T1] |
| (b) | $((A \to B) \to (A \to B)) \to (A \to ((A \to B) \to B))$ | : [T5] |
| (c) | $A \to ((A \to B) \to B)$ | : (a),(b),MP |
| (d) | $A$ | : 前提 |
| (e) | $(A \to B) \to B$ | : (d),(c),MP |
| (f) | $((A \to B) \to B) \to (\lnot B \to \lnot(A \to B))$ | : [T9] |
| (g) | $\lnot B \to \lnot(A \to B)$ | : (e),(f),MP |
□
このようにして、論理の定理がいくらでも形式的に証明できますが、キリがないのでここでやめておきます。
3. トートロジーが形式的証明可能なことの証明
ここまでの議論では、論理演算子 $\lnot, \to$ や推論規則には何の意味もなく、形式的証明はただ記号列を規則に従って並べているだけでした。これから論理演算子に意味を持たせ、論理式の真偽を定義します。
【定義7】(論理式の真偽)議論の対象としている原始命題それぞれに真理値と呼ばれる $\{$ 真, 偽 $\}$ どちらかの値が割り当てられているとする。このとき、論理式 $A$ の真理値を次で帰納的に与える。
i) $A$ が原始命題 $P$ のとき:
・$A$ の真理値は $P$ の真理値と同じ
ii) $A$ が $\lnot B$ で $B$ が論理式のとき:
・$B$ の真理値が真ならば $A$ の真理値は偽
・$B$ の真理値が偽ならば $A$ の真理値は真
(これは論理演算子 $\lnot$ に否定の意味を持たせることである。)
iii) $A$ が $B \to C$ で $B, C$ が論理式のとき:
・$B$ の真理値が真かつ $C$ の真理値が偽ならば $A$ の真理値は偽
・それ以外の場合は $A$ の真理値は真
(これは論理演算子 $\to$ に「ならば」の意味を持たせることである。)
論理式 $A$ の真理値が真のとき「$A$ は真」、真理値が偽のとき「$A$ は偽」という。
i) $A$ が原始命題 $P$ のとき:
・$A$ の真理値は $P$ の真理値と同じ
ii) $A$ が $\lnot B$ で $B$ が論理式のとき:
・$B$ の真理値が真ならば $A$ の真理値は偽
・$B$ の真理値が偽ならば $A$ の真理値は真
(これは論理演算子 $\lnot$ に否定の意味を持たせることである。)
iii) $A$ が $B \to C$ で $B, C$ が論理式のとき:
・$B$ の真理値が真かつ $C$ の真理値が偽ならば $A$ の真理値は偽
・それ以外の場合は $A$ の真理値は真
(これは論理演算子 $\to$ に「ならば」の意味を持たせることである。)
論理式 $A$ の真理値が真のとき「$A$ は真」、真理値が偽のとき「$A$ は偽」という。
【定義8】(論理的帰結)$\Sigma$ に属する論理式が全て真ならば論理式 $A$ が必ず真になるとき、$A$ は $\Sigma$ の論理的帰結であるといい、
\begin{equation*}
\Sigma \models A
\end{equation*}
と書く。$\Sigma$ が空集合のときは
\begin{equation*}
\models A
\end{equation*}
と書き、$A$ はトートロジー(恒真式)であるという。
トートロジーを言い換えると、原始命題の真理値をどのように割り当てても真になる論理式ということです。定義から具体的に検証することによって、論理の公理 [A1] $\sim$ [A3] は全てトートロジーになることが分かります。
このように論理式に真偽の意味を持たせると、形式的証明が次の定理によって意味づけされます。
【定理9】(健全性定理)$\Sigma \vdash A$ ならば $\Sigma \models A$ である。すなわち、$\Sigma$ から $A$ が形式的に証明できれば、$A$ は $\Sigma$ の論理的帰結である。
(証明)
$\Sigma \vdash A$ かつ $\Sigma$ の要素が全て真とする。$\Sigma$ から $A$ への形式的証明を $B_1, B_2, \cdots, B_{n-1}, A$ とし、$i < n$ に対して定理が成り立つ、すなわち $\Sigma \models B_i \ (i < n)$ であると仮定すると、$B_i \ (i < n)$ は全て真である。
i) $A$ が $\Sigma$ の要素のとき:
明らかに $A$ は真である。
ii) $A$ が [A1] $\sim$ [A3] のいずれかのとき:
[A1] $\sim$ [A3] はどれもトートロジーだから、やはり $A$ は真 である。
iii) ある $B_i, B_j \ (i,j < n)$ に対して $B_j$ が $B_i \to A$ のとき:
$B_i$ が真、かつ $B_i \to A$ が真 であるから、【定義7】iii) より $A$ は真でなければならない。
以上より全ての場合で $A$ が真であるから、形式的証明の長さ $n$ に関する帰納法によって $\Sigma \models A$ が示された。
□
つまり「形式的に証明できれば論理的に正しい」と言って良いわけです。これによって、論理の定理は前提なしで形式的に証明できるので、全てトートロジーです。
逆に、トートロジーが全て形式的に証明できること、すなわち論理の定理であることの証明に進みます。準備として、論理式の真理値と形式的証明の関係がよくわかる次の補題を証明します。
【補題10】論理式 $A$ を構成する原始命題は $P_1, P_2, \cdots , P_n$ 以外にないとする。$0 \le m \le n$ として、
(a) $P_1, \cdots , P_m$ が真、$P_{m+1}, \cdots , P_n$ が偽のときに $A$ が真ならば、 \begin{equation} \tag{3} \{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash A \end{equation} (b) $P_1, \cdots , P_m$ が真、$P_{m+1}, \cdots , P_n$ が偽のときに $A$ が偽ならば、 \begin{equation} \tag{4} \{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash \lnot A \end{equation}
(a) $P_1, \cdots , P_m$ が真、$P_{m+1}, \cdots , P_n$ が偽のときに $A$ が真ならば、 \begin{equation} \tag{3} \{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash A \end{equation} (b) $P_1, \cdots , P_m$ が真、$P_{m+1}, \cdots , P_n$ が偽のときに $A$ が偽ならば、 \begin{equation} \tag{4} \{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash \lnot A \end{equation}
(証明)
論理式 $A$ の構成に関する帰納法を用いる。
i) $A$ が原始命題 $P$ のとき:
(a) $P$ が真のとき $A$ は真である。このとき $\{ P \} \vdash P$ は自明だから $\{ P \} \vdash A$ となり、$(3)$が成立する。
(b) $P$ が偽のとき $A$ は偽である。このとき $\{ \lnot P \} \vdash \lnot P$ は自明だから $\{ \lnot P \} \vdash \lnot A$ となり、$(4)$が成立する。
ii) $A$ が $\lnot B$ で、$B$ について補題が成立するとき:
(a) $P_1, \cdots , P_m$ が真、$P_{m+1}, \cdots , P_n$ が偽のときに $A$ が真ならば、このとき $B$ は偽であるから、
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash \lnot B
\end{equation*}
である。$\lnot B$ は $A$ だから$(3)$が成立する。
(b) $P_1, \cdots , P_m$ が真、$P_{m+1}, \cdots , P_n$ が偽のときに $A$ が偽ならば、このとき $B$ は真であるから、
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash B
\end{equation*}
であり、さらに [T4] より $\vdash B \to \lnot \lnot B$ だから、
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash \lnot \lnot B
\end{equation*}
である。$\lnot B$ は $A$ だから$(4)$が成立する。
iii) $A$ が $B \to C$ で、$B$ と $C$ について補題が成立するとき:
(a) $P_1, \cdots , P_m$ が真、$P_{m+1}, \cdots , P_n$ が偽のときに $A$ が真ならば、このとき $B$ が偽であるか、または $C$ が真である。
$B$ が偽の場合は、
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash \lnot B
\end{equation*}
であり、さらに [T2] より $\vdash \lnot B \to (B \to C)$ だから、
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash B \to C
\end{equation*}
である。$B \to C$ は $A$ だから$(3)$が成立する。
$C$ が真の場合は、
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash C
\end{equation*}
であり、さらに [A1] より $\vdash C \to (B \to C)$ だから、
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash B \to C
\end{equation*}
である。$B \to C$ は $A$ だから$(3)$が成立する。
(b) $P_1, \cdots , P_m$ が真、$P_{m+1}, \cdots , P_n$ が偽のときに $A$ が偽ならば、このとき $B$ が真かつ $C$ が偽であるから、
\begin{eqnarray*}
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} &\vdash& B \\
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} &\vdash& \lnot C
\end{eqnarray*}
であり、さらに [T10] より $\vdash B \to (\lnot C \to \lnot (B \to C))$ だから、
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_m, \lnot P_{m+1}, \cdots , \lnot P_n \} \vdash \lnot (B \to C)
\end{equation*}
である。$B \to C$ は $A$ だから$(4)$が成立する。
以上より、全ての論理式 $A$ に対して補題が証明できた。
□
この補題を使って、本記事の目的である次の定理を証明します。
【定理11】$\models A$ ならば $\vdash A$ である。すなわちトートロジーは全て論理の定理である。
(証明)
$\models A$ とする。$A$ を構成する原始命題を全て取り出し $P_1, P_2, \cdots , P_n$ とすると、これらの真理値がどのように割り当てられても $A$ は真である。特に $P_n$ に注目すると、【補題10】より、
\begin{eqnarray*}
\{ P_1, \cdots , P_{n-1}, P_n \} &\vdash& A \\
\{ P_1, \cdots , P_{n-1}, \lnot P_n \} &\vdash& A
\end{eqnarray*}
である。これから演繹定理より、
\begin{eqnarray*}
\{ P_1, \cdots , P_{n-1} \} &\vdash& P_n \to A \\
\{ P_1, \cdots , P_{n-1} \} &\vdash& \lnot P_n \to A
\end{eqnarray*}
となる。一方 [T8] より、
\begin{equation*}
\vdash (P_n \to A) \to ((\lnot P_n \to A) \to A)
\end{equation*}
であるから、
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_{n-2}, P_{n-1} \} \vdash A
\end{equation*}
が得られる。同様に、
\begin{eqnarray*}
\{ P_1, \cdots , P_{n-2}, \lnot P_{n-1}, P_n \} &\vdash& A \\
\{ P_1, \cdots , P_{n-2}, \lnot P_{n-1}, \lnot P_n \} &\vdash& A
\end{eqnarray*}
から
\begin{equation*}
\{ P_1, \cdots , P_{n-2}, \lnot P_{n-1} \} \vdash A
\end{equation*}
が得られる。従って、
\begin{eqnarray*}
\{ P_1, \cdots , P_{n-2}, P_{n-1} \} \vdash A \\
\{ P_1, \cdots , P_{n-2}, \lnot P_{n-1} \} \vdash A
\end{eqnarray*}
である。以下この操作を次々繰り返すと、最終的に
\begin{equation*}
\vdash A
\end{equation*}
が得られる。
□
たった3種類の公理系と1つの推論規則から全てのトートロジーが形式的に証明できることが、これで確認できました。
シュトルツ・チェザロの定理の超準解析による証明 [数学]
久々に超準解析で証明問題をやってみました。
お題として「シュトルツ・チェザロの定理」です。
なんか見たことあるような雰囲気の定理ですが、これはあれです。「差分の比が収束すれば元の比も同じ値に収束する」という主張なので、差分を微分に変えたら有名なロピタルの定理になりますね。
また、$b_n = n, a_0 = 0$ としたら、これも有名な「実数列が収束すればそのチェザロ平均も同じ値に収束する」という定理にもなります。
では、証明していきましょう。以前の記事「チェザロ平均の収束の超準解析での証明例」のやり方に倣って進めます。
(証明)
実数列 $\{ a_n \}, \{ b_n \}$ を、超自然数を番号とする超実数列に拡大しておく。
任意の $m,n \in {}^*\mathbb{N}, m < n$ について、次が成り立つ。
\begin{eqnarray*}
a_n - a_m &=& \sum_{k=m}^{n-1}( a_{k+1} - a_k ) \\
&=& \sum_{k=m}^{n-1}( b_{k+1} - b_k ) \frac{ a_{k+1} - a_k }{ b_{k+1} - b_k }
\end{eqnarray*}
この全体を $b_n$ で割って両辺から $c$ を引くと、次の変形ができる。
\begin{eqnarray*}
\frac{ a_n }{ b_n } - c &=& \frac{ a_m }{ b_n } + \frac{1}{ b_n } \sum_{k=m}^{n-1}( b_{k+1} - b_k ) \frac{ a_{k+1} - a_k }{ b_{k+1} - b_k } - c \\
&=& \frac{ a_m }{ b_n } + \frac{1}{ b_n } \sum_{k=m}^{n-1}( b_{k+1} - b_k )( \frac{ a_{k+1} - a_k }{ b_{k+1} - b_k } - c ) + \frac{1}{ b_n } \sum_{k=m}^{n-1}( b_{k+1} - b_k ) c - c \\
&=& \frac{ a_m }{ b_n } + \frac{1}{ b_n } \sum_{k=m}^{n-1}( b_{k+1} - b_k )( \frac{ a_{k+1} - a_k }{ b_{k+1} - b_k } - c ) + \frac{1}{ b_n }( b_n - b_m ) c - c \\
&=& \frac{ a_m - b_m c }{ b_n } + \frac{1}{ b_n } \sum_{k=m}^{n-1}( b_{k+1} - b_k )( \frac{ a_{k+1} - a_k }{ b_{k+1} - b_k } - c )
\end{eqnarray*}
ここで、無限大超自然数 $n$ を任意にとる。$\displaystyle \lim_{n \to \infty} b_n = +\infty$ だから、この $n$ に対する $b_n$ は正の無限大超実数であり、従って $\sqrt{ b_n }$ も正の無限大超実数である。任意の自然数 $m$ に対して $a_m - b_m c$ は実数だから $\left| a_m - b_m c \right| < \sqrt{ b_n }$ であり、従って $m$ を十分小さな無限大超自然数にとると $\left| a_m - b_m c \right| < \sqrt{ b_n }$ とできる。この $m,n$ に対して、
\[ \mu = \max_{m \le k \le n-1} \left| \frac{ a_{k+1} - a_k }{ b_{k+1} - b_k } - c \right| \]
が存在し、
\[ \lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = c \]
より $\mu \approx 0$(無限小超実数)である。これらと $\{ b_n \}$ が狭義単調増加であることより、
\begin{eqnarray*}
\left| \frac{ a_n }{ b_n } - c \right| &\le& \frac{ \left| a_m - b_m c \right| }{ b_n } + \frac{1}{ b_n } \sum_{k=m}^{n-1}( b_{k+1} - b_k ) \left| \frac{ a_{k+1} - a_k }{ b_{k+1} - b_k } - c \right| \\
&<& \frac{\sqrt{ b_n }}{ b_n } + \frac{1}{ b_n } \sum_{k=m}^{n-1}( b_{k+1} - b_k ) \mu \\
&=& \frac{1}{\sqrt{ b_n }} + \frac{1}{ b_n } ( b_n - b_m ) \mu \\
&<& \frac{1}{\sqrt{ b_n }} + \mu \\
&\approx& 0
\end{eqnarray*}
従って、任意の無限大超自然数 $n$ に対して $\displaystyle \frac{a_n}{b_n} \approx c$ が成り立つから、$\displaystyle \lim_{n \to \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$ である。□
どうでしょうか。普通の証明に比べて簡単になっているわけでもなさそうですが、やはり無限大や無限小を数として式変形して証明できるところは面白いかもしれません。
念のため、上の証明中に使った超準解析の基本的な補題を証明しておきましょう。
(証明)
$\{ a_n \}$ を超自然数を番号とする超実数列に拡大しておく。$K$ を任意の正の実数とし、$A_K = \{ \, k \in \mathbb{N} \, \mid \, \left| a_k \right| \ge K \, \}$ とおくと、自然数の性質より $A_K$ は空でなければ最小元をもつ。すなわち、
\[ \forall K \in \mathbb{R} \, ( K > 0 \land A_K \neq \emptyset \to \exists m \in \mathbb{N} \, ( m = \min A_K ) ) \]
移行原理より、
\[ \forall K \in {}^*\mathbb{R} \, ( K > 0 \land {}^*A_K \neq \emptyset \to \exists m \in {}^*\mathbb{N} \, ( m = \min {}^*A_K ) ) \]
ここで ${}^*A_K = \{ \, k \in {}^*\mathbb{N} \, \mid \, \left| a_k \right| \ge K \, \}$ であるから、これを $B_K$ とおく。
そこで、正の超実数 $M$ が任意の自然数 $k$ に対して $\left| a_k \right| < M$ であるとする。$B_M = \emptyset$ ならば、任意の無限大超自然数 $n$ に対して明らかに$(1)$は成立する。$B_M \neq \emptyset$ ならば、$m = \min B_M$ となる超自然数 $m$ が存在し、任意の自然数 $k$ に対して $k \notin B_M$ だから $m$ は無限大超自然数である。$n = m - 1$ とすると $n$ も無限大超自然数で、この $n$ に対し$(1)$が成立する。□
お題として「シュトルツ・チェザロの定理」です。
【定理】実数列 $\{ a_n \}, \{ b_n \}$ について、$\{ b_n \}$ は狭義単調増加で非有界、かつ極限
\[ \lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = c \]
が存在すれば、
\[ \lim_{n \to \infty} \frac{a_n}{b_n} = c \]
である。
なんか見たことあるような雰囲気の定理ですが、これはあれです。「差分の比が収束すれば元の比も同じ値に収束する」という主張なので、差分を微分に変えたら有名なロピタルの定理になりますね。
また、$b_n = n, a_0 = 0$ としたら、これも有名な「実数列が収束すればそのチェザロ平均も同じ値に収束する」という定理にもなります。
では、証明していきましょう。以前の記事「チェザロ平均の収束の超準解析での証明例」のやり方に倣って進めます。
(証明)
実数列 $\{ a_n \}, \{ b_n \}$ を、超自然数を番号とする超実数列に拡大しておく。
任意の $m,n \in {}^*\mathbb{N}, m < n$ について、次が成り立つ。
\begin{eqnarray*}
a_n - a_m &=& \sum_{k=m}^{n-1}( a_{k+1} - a_k ) \\
&=& \sum_{k=m}^{n-1}( b_{k+1} - b_k ) \frac{ a_{k+1} - a_k }{ b_{k+1} - b_k }
\end{eqnarray*}
この全体を $b_n$ で割って両辺から $c$ を引くと、次の変形ができる。
\begin{eqnarray*}
\frac{ a_n }{ b_n } - c &=& \frac{ a_m }{ b_n } + \frac{1}{ b_n } \sum_{k=m}^{n-1}( b_{k+1} - b_k ) \frac{ a_{k+1} - a_k }{ b_{k+1} - b_k } - c \\
&=& \frac{ a_m }{ b_n } + \frac{1}{ b_n } \sum_{k=m}^{n-1}( b_{k+1} - b_k )( \frac{ a_{k+1} - a_k }{ b_{k+1} - b_k } - c ) + \frac{1}{ b_n } \sum_{k=m}^{n-1}( b_{k+1} - b_k ) c - c \\
&=& \frac{ a_m }{ b_n } + \frac{1}{ b_n } \sum_{k=m}^{n-1}( b_{k+1} - b_k )( \frac{ a_{k+1} - a_k }{ b_{k+1} - b_k } - c ) + \frac{1}{ b_n }( b_n - b_m ) c - c \\
&=& \frac{ a_m - b_m c }{ b_n } + \frac{1}{ b_n } \sum_{k=m}^{n-1}( b_{k+1} - b_k )( \frac{ a_{k+1} - a_k }{ b_{k+1} - b_k } - c )
\end{eqnarray*}
ここで、無限大超自然数 $n$ を任意にとる。$\displaystyle \lim_{n \to \infty} b_n = +\infty$ だから、この $n$ に対する $b_n$ は正の無限大超実数であり、従って $\sqrt{ b_n }$ も正の無限大超実数である。任意の自然数 $m$ に対して $a_m - b_m c$ は実数だから $\left| a_m - b_m c \right| < \sqrt{ b_n }$ であり、従って $m$ を十分小さな無限大超自然数にとると $\left| a_m - b_m c \right| < \sqrt{ b_n }$ とできる。この $m,n$ に対して、
\[ \mu = \max_{m \le k \le n-1} \left| \frac{ a_{k+1} - a_k }{ b_{k+1} - b_k } - c \right| \]
が存在し、
\[ \lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = c \]
より $\mu \approx 0$(無限小超実数)である。これらと $\{ b_n \}$ が狭義単調増加であることより、
\begin{eqnarray*}
\left| \frac{ a_n }{ b_n } - c \right| &\le& \frac{ \left| a_m - b_m c \right| }{ b_n } + \frac{1}{ b_n } \sum_{k=m}^{n-1}( b_{k+1} - b_k ) \left| \frac{ a_{k+1} - a_k }{ b_{k+1} - b_k } - c \right| \\
&<& \frac{\sqrt{ b_n }}{ b_n } + \frac{1}{ b_n } \sum_{k=m}^{n-1}( b_{k+1} - b_k ) \mu \\
&=& \frac{1}{\sqrt{ b_n }} + \frac{1}{ b_n } ( b_n - b_m ) \mu \\
&<& \frac{1}{\sqrt{ b_n }} + \mu \\
&\approx& 0
\end{eqnarray*}
従って、任意の無限大超自然数 $n$ に対して $\displaystyle \frac{a_n}{b_n} \approx c$ が成り立つから、$\displaystyle \lim_{n \to \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$ である。□
どうでしょうか。普通の証明に比べて簡単になっているわけでもなさそうですが、やはり無限大や無限小を数として式変形して証明できるところは面白いかもしれません。
念のため、上の証明中に使った超準解析の基本的な補題を証明しておきましょう。
【補題】実数列 $\{ a_n \}$ と正の超実数 $M$ について、任意の自然数 $k$ に対して $\left| a_k \right| < M$ ならば、ある無限大超自然数 $n$ が存在して、$\{ a_n \}$ を拡大した超実数列において、
\[ \forall k \in {}^*\mathbb{N} \, ( k \le n \to \left| a_k \right| < M ) \tag{1} \]
とすることができる。
(証明)
$\{ a_n \}$ を超自然数を番号とする超実数列に拡大しておく。$K$ を任意の正の実数とし、$A_K = \{ \, k \in \mathbb{N} \, \mid \, \left| a_k \right| \ge K \, \}$ とおくと、自然数の性質より $A_K$ は空でなければ最小元をもつ。すなわち、
\[ \forall K \in \mathbb{R} \, ( K > 0 \land A_K \neq \emptyset \to \exists m \in \mathbb{N} \, ( m = \min A_K ) ) \]
移行原理より、
\[ \forall K \in {}^*\mathbb{R} \, ( K > 0 \land {}^*A_K \neq \emptyset \to \exists m \in {}^*\mathbb{N} \, ( m = \min {}^*A_K ) ) \]
ここで ${}^*A_K = \{ \, k \in {}^*\mathbb{N} \, \mid \, \left| a_k \right| \ge K \, \}$ であるから、これを $B_K$ とおく。
そこで、正の超実数 $M$ が任意の自然数 $k$ に対して $\left| a_k \right| < M$ であるとする。$B_M = \emptyset$ ならば、任意の無限大超自然数 $n$ に対して明らかに$(1)$は成立する。$B_M \neq \emptyset$ ならば、$m = \min B_M$ となる超自然数 $m$ が存在し、任意の自然数 $k$ に対して $k \notin B_M$ だから $m$ は無限大超自然数である。$n = m - 1$ とすると $n$ も無限大超自然数で、この $n$ に対し$(1)$が成立する。□
超フィルターを用いた距離空間の完備化 [数学]
先日の記事「超フィルターを使った距離空間「全有界+完備 ⇔ コンパクト」の証明」で、距離空間の完備性を超フィルターを用いた同値な条件で表しました。今回はそれと関連して、距離空間の完備化を超フィルターを用いて構成するということをやってみます。
超フィルターについての予備知識は、こちらの記事を参照してください。今回はそれに加えて次の事実も使います。$X$ を空でない集合、$\mathbf{F}$ を $X$(の冪集合)上の超フィルターとすると、次が成立します。
\begin{equation*} \tag{0}
A \in \mathbf{F} \land B \subseteq X \to B \in \mathbf{F} \lor A \setminus B \in \mathbf{F}
\end{equation*}
また、全体を通じて、正実数の全体を $\mathbb{R}^+$ で、非負実数の全体を $\mathbb{R}^+_0$ で表します。
1. 距離空間上の超フィルター間に擬距離を定める
$\langle X, d_X \rangle$ を距離空間とします。$X$ は空でない集合で、$d_X : X^2 \to \mathbb{R}^+_0$ は距離関数です。$X$ の要素は慣習にならって点とよびます。
$X$ の空でない部分集合 $A,B$ に対し、$A,B$ 間の「距離」を
\begin{equation*}
\mathrm{dist}_X(A,B) = \inf \{ \, d_X(a,b) \, \mid \, a \in A \land b \in B \, \}
\end{equation*}
によって定めます。これは感覚的には距離と言ってよいですが、点間の距離とは違って三角不等式を満たしません。
次に、$X$ 上の超フィルターの全体を $\mathrm{U}(X)$ とし、その要素 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ に対して次によって関数 $\bar{d}_X : \mathrm{U}(X)^2 \to \mathbb{R}^+_0 \cup \{ \infty \}$ を定めます。
\begin{equation*}
\bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B}) = \sup \{ \, \mathrm{dist}_X(A,B) \, \mid \, A \in \mathbf{A} \land B \in \mathbf{B} \, \}
\end{equation*}
これは「超フィルター間の距離のようなもの」といえます。なぜそう言えるかはすぐ後で証明します。
$X$ の点 $x,y$ に対し、単項フィルター $\uparrow x, \uparrow y$ を考えると、
\begin{equation*}
\bar{d}_X( \uparrow x, \uparrow y ) = d_X(x,y)
\end{equation*}
となることはすぐわかります。
関数 $\bar{d}_X$ は一般には $\infty$ になることがあり得ます。そこで、ある $X$ の点 $x$ に対して $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \uparrow x ) < \infty$ となるような超フィルター $\mathbf{A}$ を「有界超フィルター」と呼び、$X$上の有界超フィルターの全体を $\mathrm{U}_B(X)$ とかくことにします(ここだけの勝手な用語です)。単項フィルター $\uparrow x$ はもちろん有界超フィルターであり、$\mathbf{A}, \mathbf{B}$ がともに有界超フィルターならば $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B} ) < \infty$ であることも容易にわかります(ある $x,y \in X$ に対して $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \uparrow x ) < \infty, \bar{d}_X( \mathbf{B}, \uparrow y ) < \infty$ とすると、任意の $A \in \mathbf{A}, B \in \mathbf{B}$ と $a \in A, b \in B$ に対して $d_X(a,b) \le d_X(a,x) + d_X(b,y) + d_X(x,y)$ だから $\mathrm{dist}_X(A,B) \le d_X(a,x) + d_X(b,y) + d_X(x,y)$ より $\mathrm{dist}_X(A,B) \le \mathrm{dist}_X(A, \{x\} ) + \mathrm{dist}_X(B, \{y\} ) + d_X(x,y) \le \bar{d}_X( \mathbf{A}, \uparrow x ) + \bar{d}_X( \mathbf{B}, \uparrow y ) + d_X(x,y) < \infty$ となり、これより $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B} ) < \infty$ が得られる)。従って $\mathrm{U}_B(X)$ 上では関数 $\bar{d}_X$ の値は $\infty$ にはならずに $\mathbb{R}^+_0$ 内にとられます。
このとき、次が成立します。
(証明)
① $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{A}) = 0$
フィルターの有限交差性から明らか。
② $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B}) = \bar{d}_X( \mathbf{B}, \mathbf{A})$(対称性)
定義の対称性から明らか。
③ $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B}) \le \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{C}) + \bar{d}_X( \mathbf{B}, \mathbf{C})$(三角不等式)
まず一般に $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B}) < \infty$ ならば、次の$2$性質が成り立つことに注意する。
i) $\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \forall A \in \mathbf{A} \, \forall B \in \mathbf{B} \, \exists a \in A \, \exists b \in B \, ( d_X(a,b) < \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B}) + \epsilon )$
ii) $\exists A \in \mathbf{A} \, \exists B \in \mathbf{B} \, \forall a \in A \, \forall b \in B \, ( d_X(a,b) \ge \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B}) )$
このことを念頭におきつつ、ある $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathrm{U}_B(X)$ に対して $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B}) > \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{C}) + \bar{d}_X( \mathbf{B}, \mathbf{C})$ と仮定して矛盾を導く。$\epsilon = \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B}) - \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{C}) + \bar{d}_X( \mathbf{B}, \mathbf{C})$ とおくと $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ である。ii) より
\begin{equation} \tag{1}
\forall a \in A \, \forall b \in B \, ( d_X(a,b) \ge \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B}) )
\end{equation}
をみたす $A \in \mathbf{A}, B \in \mathbf{B}$ がとれる。$C \in \mathbf{C}$ を一つとり、
\begin{eqnarray*}
C_1 &=& \{ \, c \in C \, \mid \, \exists a \in A \, ( d_X(a,c) < \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{C}) + \epsilon /2 ) \, \} \\
C_2 &=& \{ \, c \in C \, \mid \, \exists b \in B \, ( d_X(b,c) < \bar{d}_X( \mathbf{B}, \mathbf{C}) + \epsilon /2 ) \, \}
\end{eqnarray*}
とおくと、
\begin{equation*}
C \setminus C_1 = \{ \, c \in C \, \mid \, \forall a \in A \, ( d_X(a,c) \ge \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{C}) + \epsilon /2 ) \, \}
\end{equation*}
なので、
\begin{equation*}
\forall c \in C \setminus C_1 \, \forall a \in A \, ( d_X(a,c) \ge \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{C}) + \epsilon /2 )
\end{equation*}
と i) と $A \in \mathbf{A}$ より $C \setminus C_1 \notin \mathbf{C}$ であり、$\mathbf{C}$ は超フィルターだから($0$)より $C_1 \in \mathbf{C}$ である。同様に $C_2 \in \mathbf{C}$ が得られるから、フィルターの有限交差性より $C_1 \cap C_2 \neq \emptyset$ である。$c \in C_1 \cap C_2$ を一つとると、$d_X(a,c) < \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{C}) + \epsilon /2$ となる $a \in A$ と $d_X(b,c) < \bar{d}_X( \mathbf{B}, \mathbf{C}) + \epsilon /2$ となる $b \in B$ が存在するから、
\begin{equation*}
d_X(a,b) \le d_X(a,c) + d_X(b,c) < \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{C}) + \bar{d}_X( \mathbf{B}, \mathbf{C}) + \epsilon = \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B})
\end{equation*}
これは $(1)$と矛盾するから、仮定が誤っている。□
ここで三角不等式の証明に超フィルターの性質を使用しています。
2. 同値類によって距離空間を構成する
$X$ の完備化を求めるために、上で定まった擬距離空間 $\langle \mathrm{U}_B(X), \bar{d}_X \rangle$ をもう少し制限します。
\begin{equation} \tag{2}
\mathrm{U}_C(X) = \{ \, \mathbf{A} \in \mathrm{U}_B(X) \, \mid \, \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \exists x \in X \, ( \bar{d}_X( \mathbf{A}, \uparrow x ) < \epsilon ) \, \}
\end{equation}
によって $\mathrm{U}_C(X)$ を定め、$\langle \mathrm{U}_B(X), \bar{d}_X \rangle$ の部分擬距離空間 $\langle \mathrm{U}_C(X), \bar{d}_X \rangle$ を考えます。この上に次によって自然な同値関係 $\sim$ を定めます。
\begin{equation*}
\mathbf{A} \sim \mathbf{B} \quad \Leftrightarrow \quad \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B} ) = 0
\end{equation*}
そしてこの同値関係による商集合 $Y$ と、関数 $d_Y : Y^2 \to \mathbb{R}^+_0$ を次によって定めます。
\begin{eqnarray*}
&&Y = \mathrm{U}_C(X) / \sim \\
&&d_Y( [ \mathbf{A} ], [ \mathbf{B} ] ) = \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B} )
\end{eqnarray*}
ここで $[ \mathbf{A} ]$ は $\mathbf{A}$ が属する同値類を表します。この $d_Y$ は Well Defined で、$Y$ 上の距離関数の条件をみたすことが容易にわかるので、$\langle Y, d_Y \rangle$ は距離空間になります。
単項フィルター $ \uparrow x $ は明らかに $\mathrm{U}_C(X)$ に属するので、写像 $\iota : X \to Y$ を
\begin{equation*}
\iota(x) = [ \uparrow x ]
\end{equation*}
によって定めると、明らかに $d_Y( \iota(x), \iota(y) ) = d_X(x,y)$ すなわち $\iota$ は距離を保つ単射になり、$Y$ は $X$ の拡大とみなすことができます。この $\langle Y, d_Y \rangle$ が $\langle X, d_X \rangle$ の完備化(以下簡単に $Y$ が $X$ の完備化)であることを示すのが本記事の目的です。
3. 完備化であることの証明
距離空間 $Y$ が 距離空間 $X$ の完備化であることを示すには、次の2点を示すことが必要十分です。
i) $\iota$ による $X$ の像 $\iota[X]$ は $Y$ において稠密である。
ii) $Y$ は完備である。
以下、ひとつずつ証明していきます。i) は簡単です。
(証明)
任意に $a \in Y$ と $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ をとる。$a = [ \mathbf{A} ] \ ( \mathbf{A} \in \mathrm{U}_C(X) )$ とすると、$\mathrm{U}_C(X)$ の定義($2$)より、ある $x \in X$ があって $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \uparrow x ) < \epsilon$ をみたす。従って $d_Y(a, \iota(x) ) = \bar{d}_X( \mathbf{A}, \uparrow x ) < \epsilon$ となるから、$\iota[X]$ は $Y$ において稠密である。□
これに対し、ii) の証明はちょっと一手間かかります。先日の記事で紹介した完備性の超フィルターによる同値条件を使って証明します。
(証明)
$Y$ が完備であることを示すためには、任意にとった $Y$ 上の超フィルター $\mathbf{F}$ について次が成立することを示せばよい。
\begin{equation} \tag{3}
\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \exists y \in Y \, ( U(y, \epsilon ) \in \mathbf{F} ) \to \exists y \in Y \, \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, ( U(y, \epsilon ) \in \mathbf{F} )
\end{equation}
ここで $U(y, \epsilon )$ は $Y$ における点 $y$ を中心とする半径 $\epsilon$ の開球を表す。そこで($3$)の矢印の左側、次の条件をみたす $Y$ 上の超フィルター $\mathbf{F}$ を任意にとる。
\begin{equation} \tag{4}
\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \exists y \in Y \, ( U(y, \epsilon ) \in \mathbf{F} )
\end{equation}
$\iota[X]$ が $Y$ において稠密だから $\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \forall y \in Y \, ( U(y, \epsilon ) \cap \iota[X] \neq \emptyset )$ である。これより、
\begin{equation*}
\mathbf{A} = \{ \, A \subseteq X \, \mid \, \exists \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \exists y \in Y \, ( U(y, \epsilon ) \in \mathbf{F} \land \iota[A] = U(y, \epsilon ) \cap \iota[X] ) \, \}
\end{equation*}
と定めると、$\mathbf{F}$ の条件($4$)より $\mathbf{A}$ は空でない。また、任意に有限個の $\mathbf{A}$ の要素 $A_1, A_2, \cdots , A_n$ をとると、$\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots , \epsilon_n \in \mathbb{R}^+$ と $y_1, y_2, \cdots , y_n \in X$ が存在して、
\begin{equation*}
U(y_i, \epsilon_i ) \in \mathbf{F} \land \iota[A_i] = U(y_i, \epsilon_i ) \cap \iota[X] \quad (i=1,2, \cdots ,n)
\end{equation*}
であるから、
\begin{equation*}
\iota[A_1] \cap \iota[A_2] \cap \cdots \cap \iota[A_n] = ( U(y_1, \epsilon_1 ) \cap U(y_2, \epsilon_2 ) \cap \cdots \cap U(y_n, \epsilon_n ) ) \cap \iota[X] \neq \emptyset
\end{equation*}
ここで最後の $\neq \emptyset$ は、$U(y_1, \epsilon_1 ) \cap U(y_2, \epsilon_2 ) \cap \cdots \cap U(y_n, \epsilon_n ) \in \mathbf{F}$ と $\mathbf{F}$ の有限交差性より、$\in$ の左側が空でない開集合であることと、$\iota[X]$ が $Y$ において稠密であることから導かれる。従って、
\begin{equation*}
A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n \neq \emptyset
\end{equation*}
であるから $\mathbf{A}$ は有限交差性をもち、これより $\mathbf{A}$ を含む $X$ 上の超フィルター $\mathbf{B}$ が存在する。
$\mathbf{B} \in \mathrm{U}_C(X)$ を示す。任意に $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ をとると、($4$)よりある $y \in Y$ に対して
\begin{equation*}
U(y, \epsilon /3 ) \in \mathbf{F} \land \iota[A] = U(y, \epsilon /3 ) \cap \iota[X]
\end{equation*}
となる $A \in \mathbf{A} \subseteq \mathbf{B}$ が存在する。$a \in A$ を一つとると、任意の $x \in A$ に対して、
\begin{equation*}
d_X(x,a) = d_Y( \iota(x), \iota(a) ) \le d_Y( \iota(x), y ) + d_Y( \iota(a), y ) < \epsilon /3 + \epsilon /3 = 2 \epsilon /3
\end{equation*}
であり、任意の $B \in \mathbf{B}$ は $A \cap B \neq \emptyset$ をみたすから $\mathrm{dist}_X( B, \{a\} ) < 2 \epsilon /3$ である。従って、
\begin{equation*}
\bar{d}_X( \mathbf{B}, \uparrow a ) \le 2 \epsilon /3 < \epsilon
\end{equation*}
これで($2$)より $\mathbf{B} \in \mathrm{U}_C(X)$ が示されたから、$b = [ \mathbf{B} ]$ として $b \in Y$ が定まる。
最後に次が成立すること( $\mathbf{F}$ が この $b$ に収束すること)を示す。
\begin{equation} \tag{5}
\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, ( U(b, \epsilon ) \in \mathbf{F} )
\end{equation}
これが成立しないと仮定して矛盾を導く。このとき $U(b, \epsilon ) \notin \mathbf{F}$ となる $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ が存在する。($4$)より $U(c, \epsilon /4) \in \mathbf{F}$ をみたす $c \in Y$ がとれ、$\iota[C] = U(c, \epsilon /4 ) \cap \iota[X]$ となる $C \subseteq X$ をとると $C \in \mathbf{A} \subseteq \mathbf{B}$ である。$U(b, \epsilon ) \notin \mathbf{F}$ より $U(c, \epsilon /4) \not \subseteq U(b, \epsilon )$ であるから $d_Y(b,c) > 3 \epsilon /4$ でなければならない。一方、$\iota[X]$ が $Y$ において稠密だから、
\begin{equation*}
d_Y(b, \iota[x] ) < \epsilon /4
\end{equation*}
となる $x \in X$ をとることができる。この $x$ に対し任意に $z \in C$ をとると、
\begin{equation*}
d_X(z, x) = d_Y( \iota[z], \iota[x] ) \ge d_Y(b,c) - d_Y( \iota[z], c ) - d_Y( \iota[x], b ) > 3 \epsilon /4 - \epsilon /4 - \epsilon /4 = \epsilon /4
\end{equation*}
よって $\mathrm{dist}_X( C, \{x\} ) \ge \epsilon /4$ であり、$C \in \mathbf{B}$ かつ $b = [ \mathbf{B} ]$ より
\begin{equation*}
d_Y(b, \iota[x] ) \ge \epsilon /4
\end{equation*}
が得られるが、これは $x$ のとり方に矛盾する。従って($5$)が成立する。
以上で任意の $Y$ 上の超フィルター $\mathbf{F}$ について($3$)が成立することが示されたから、$Y$ は完備である。□
これで、超フィルターを用いた距離空間の完備化の構成法を示すことができました。
4. おわりに
いかがでしたでしょうか。この方法は、距離空間の完備化の構成法として普通にみられるコーシー列を用いたものに比べても相当ゴチャゴチャしていて、手法としてはあまり価値がなさそうな気もしますが、超フィルターのこのような利用法があるということ自体が面白いと思います。また、こちらの記事で紹介した「超準モデルを使った距離空間の完備化」とのアナロジーも感じることができます。一つの手法として紹介しました。
(前記事)
超フィルターについての予備知識は、こちらの記事を参照してください。今回はそれに加えて次の事実も使います。$X$ を空でない集合、$\mathbf{F}$ を $X$(の冪集合)上の超フィルターとすると、次が成立します。
\begin{equation*} \tag{0}
A \in \mathbf{F} \land B \subseteq X \to B \in \mathbf{F} \lor A \setminus B \in \mathbf{F}
\end{equation*}
また、全体を通じて、正実数の全体を $\mathbb{R}^+$ で、非負実数の全体を $\mathbb{R}^+_0$ で表します。
1. 距離空間上の超フィルター間に擬距離を定める
$\langle X, d_X \rangle$ を距離空間とします。$X$ は空でない集合で、$d_X : X^2 \to \mathbb{R}^+_0$ は距離関数です。$X$ の要素は慣習にならって点とよびます。
$X$ の空でない部分集合 $A,B$ に対し、$A,B$ 間の「距離」を
\begin{equation*}
\mathrm{dist}_X(A,B) = \inf \{ \, d_X(a,b) \, \mid \, a \in A \land b \in B \, \}
\end{equation*}
によって定めます。これは感覚的には距離と言ってよいですが、点間の距離とは違って三角不等式を満たしません。
次に、$X$ 上の超フィルターの全体を $\mathrm{U}(X)$ とし、その要素 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ に対して次によって関数 $\bar{d}_X : \mathrm{U}(X)^2 \to \mathbb{R}^+_0 \cup \{ \infty \}$ を定めます。
\begin{equation*}
\bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B}) = \sup \{ \, \mathrm{dist}_X(A,B) \, \mid \, A \in \mathbf{A} \land B \in \mathbf{B} \, \}
\end{equation*}
これは「超フィルター間の距離のようなもの」といえます。なぜそう言えるかはすぐ後で証明します。
$X$ の点 $x,y$ に対し、単項フィルター $\uparrow x, \uparrow y$ を考えると、
\begin{equation*}
\bar{d}_X( \uparrow x, \uparrow y ) = d_X(x,y)
\end{equation*}
となることはすぐわかります。
関数 $\bar{d}_X$ は一般には $\infty$ になることがあり得ます。そこで、ある $X$ の点 $x$ に対して $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \uparrow x ) < \infty$ となるような超フィルター $\mathbf{A}$ を「有界超フィルター」と呼び、$X$上の有界超フィルターの全体を $\mathrm{U}_B(X)$ とかくことにします(ここだけの勝手な用語です)。単項フィルター $\uparrow x$ はもちろん有界超フィルターであり、$\mathbf{A}, \mathbf{B}$ がともに有界超フィルターならば $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B} ) < \infty$ であることも容易にわかります(ある $x,y \in X$ に対して $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \uparrow x ) < \infty, \bar{d}_X( \mathbf{B}, \uparrow y ) < \infty$ とすると、任意の $A \in \mathbf{A}, B \in \mathbf{B}$ と $a \in A, b \in B$ に対して $d_X(a,b) \le d_X(a,x) + d_X(b,y) + d_X(x,y)$ だから $\mathrm{dist}_X(A,B) \le d_X(a,x) + d_X(b,y) + d_X(x,y)$ より $\mathrm{dist}_X(A,B) \le \mathrm{dist}_X(A, \{x\} ) + \mathrm{dist}_X(B, \{y\} ) + d_X(x,y) \le \bar{d}_X( \mathbf{A}, \uparrow x ) + \bar{d}_X( \mathbf{B}, \uparrow y ) + d_X(x,y) < \infty$ となり、これより $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B} ) < \infty$ が得られる)。従って $\mathrm{U}_B(X)$ 上では関数 $\bar{d}_X$ の値は $\infty$ にはならずに $\mathbb{R}^+_0$ 内にとられます。
このとき、次が成立します。
【定理1】上で定義した $\bar{d}_X$ は、$\mathrm{U}_B(X)$ 上の擬距離を定める。
(証明)
① $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{A}) = 0$
フィルターの有限交差性から明らか。
② $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B}) = \bar{d}_X( \mathbf{B}, \mathbf{A})$(対称性)
定義の対称性から明らか。
③ $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B}) \le \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{C}) + \bar{d}_X( \mathbf{B}, \mathbf{C})$(三角不等式)
まず一般に $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B}) < \infty$ ならば、次の$2$性質が成り立つことに注意する。
i) $\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \forall A \in \mathbf{A} \, \forall B \in \mathbf{B} \, \exists a \in A \, \exists b \in B \, ( d_X(a,b) < \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B}) + \epsilon )$
ii) $\exists A \in \mathbf{A} \, \exists B \in \mathbf{B} \, \forall a \in A \, \forall b \in B \, ( d_X(a,b) \ge \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B}) )$
このことを念頭におきつつ、ある $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathrm{U}_B(X)$ に対して $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B}) > \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{C}) + \bar{d}_X( \mathbf{B}, \mathbf{C})$ と仮定して矛盾を導く。$\epsilon = \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B}) - \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{C}) + \bar{d}_X( \mathbf{B}, \mathbf{C})$ とおくと $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ である。ii) より
\begin{equation} \tag{1}
\forall a \in A \, \forall b \in B \, ( d_X(a,b) \ge \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B}) )
\end{equation}
をみたす $A \in \mathbf{A}, B \in \mathbf{B}$ がとれる。$C \in \mathbf{C}$ を一つとり、
\begin{eqnarray*}
C_1 &=& \{ \, c \in C \, \mid \, \exists a \in A \, ( d_X(a,c) < \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{C}) + \epsilon /2 ) \, \} \\
C_2 &=& \{ \, c \in C \, \mid \, \exists b \in B \, ( d_X(b,c) < \bar{d}_X( \mathbf{B}, \mathbf{C}) + \epsilon /2 ) \, \}
\end{eqnarray*}
とおくと、
\begin{equation*}
C \setminus C_1 = \{ \, c \in C \, \mid \, \forall a \in A \, ( d_X(a,c) \ge \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{C}) + \epsilon /2 ) \, \}
\end{equation*}
なので、
\begin{equation*}
\forall c \in C \setminus C_1 \, \forall a \in A \, ( d_X(a,c) \ge \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{C}) + \epsilon /2 )
\end{equation*}
と i) と $A \in \mathbf{A}$ より $C \setminus C_1 \notin \mathbf{C}$ であり、$\mathbf{C}$ は超フィルターだから($0$)より $C_1 \in \mathbf{C}$ である。同様に $C_2 \in \mathbf{C}$ が得られるから、フィルターの有限交差性より $C_1 \cap C_2 \neq \emptyset$ である。$c \in C_1 \cap C_2$ を一つとると、$d_X(a,c) < \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{C}) + \epsilon /2$ となる $a \in A$ と $d_X(b,c) < \bar{d}_X( \mathbf{B}, \mathbf{C}) + \epsilon /2$ となる $b \in B$ が存在するから、
\begin{equation*}
d_X(a,b) \le d_X(a,c) + d_X(b,c) < \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{C}) + \bar{d}_X( \mathbf{B}, \mathbf{C}) + \epsilon = \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B})
\end{equation*}
これは $(1)$と矛盾するから、仮定が誤っている。□
ここで三角不等式の証明に超フィルターの性質を使用しています。
2. 同値類によって距離空間を構成する
$X$ の完備化を求めるために、上で定まった擬距離空間 $\langle \mathrm{U}_B(X), \bar{d}_X \rangle$ をもう少し制限します。
\begin{equation} \tag{2}
\mathrm{U}_C(X) = \{ \, \mathbf{A} \in \mathrm{U}_B(X) \, \mid \, \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \exists x \in X \, ( \bar{d}_X( \mathbf{A}, \uparrow x ) < \epsilon ) \, \}
\end{equation}
によって $\mathrm{U}_C(X)$ を定め、$\langle \mathrm{U}_B(X), \bar{d}_X \rangle$ の部分擬距離空間 $\langle \mathrm{U}_C(X), \bar{d}_X \rangle$ を考えます。この上に次によって自然な同値関係 $\sim$ を定めます。
\begin{equation*}
\mathbf{A} \sim \mathbf{B} \quad \Leftrightarrow \quad \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B} ) = 0
\end{equation*}
そしてこの同値関係による商集合 $Y$ と、関数 $d_Y : Y^2 \to \mathbb{R}^+_0$ を次によって定めます。
\begin{eqnarray*}
&&Y = \mathrm{U}_C(X) / \sim \\
&&d_Y( [ \mathbf{A} ], [ \mathbf{B} ] ) = \bar{d}_X( \mathbf{A}, \mathbf{B} )
\end{eqnarray*}
ここで $[ \mathbf{A} ]$ は $\mathbf{A}$ が属する同値類を表します。この $d_Y$ は Well Defined で、$Y$ 上の距離関数の条件をみたすことが容易にわかるので、$\langle Y, d_Y \rangle$ は距離空間になります。
単項フィルター $ \uparrow x $ は明らかに $\mathrm{U}_C(X)$ に属するので、写像 $\iota : X \to Y$ を
\begin{equation*}
\iota(x) = [ \uparrow x ]
\end{equation*}
によって定めると、明らかに $d_Y( \iota(x), \iota(y) ) = d_X(x,y)$ すなわち $\iota$ は距離を保つ単射になり、$Y$ は $X$ の拡大とみなすことができます。この $\langle Y, d_Y \rangle$ が $\langle X, d_X \rangle$ の完備化(以下簡単に $Y$ が $X$ の完備化)であることを示すのが本記事の目的です。
3. 完備化であることの証明
距離空間 $Y$ が 距離空間 $X$ の完備化であることを示すには、次の2点を示すことが必要十分です。
i) $\iota$ による $X$ の像 $\iota[X]$ は $Y$ において稠密である。
ii) $Y$ は完備である。
以下、ひとつずつ証明していきます。i) は簡単です。
【定理2】$\iota$ による $X$ の像 $\iota[X]$ は $Y$ において稠密である。
(証明)
任意に $a \in Y$ と $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ をとる。$a = [ \mathbf{A} ] \ ( \mathbf{A} \in \mathrm{U}_C(X) )$ とすると、$\mathrm{U}_C(X)$ の定義($2$)より、ある $x \in X$ があって $\bar{d}_X( \mathbf{A}, \uparrow x ) < \epsilon$ をみたす。従って $d_Y(a, \iota(x) ) = \bar{d}_X( \mathbf{A}, \uparrow x ) < \epsilon$ となるから、$\iota[X]$ は $Y$ において稠密である。□
これに対し、ii) の証明はちょっと一手間かかります。先日の記事で紹介した完備性の超フィルターによる同値条件を使って証明します。
【定理3】$Y$ は完備である。
(証明)
$Y$ が完備であることを示すためには、任意にとった $Y$ 上の超フィルター $\mathbf{F}$ について次が成立することを示せばよい。
\begin{equation} \tag{3}
\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \exists y \in Y \, ( U(y, \epsilon ) \in \mathbf{F} ) \to \exists y \in Y \, \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, ( U(y, \epsilon ) \in \mathbf{F} )
\end{equation}
ここで $U(y, \epsilon )$ は $Y$ における点 $y$ を中心とする半径 $\epsilon$ の開球を表す。そこで($3$)の矢印の左側、次の条件をみたす $Y$ 上の超フィルター $\mathbf{F}$ を任意にとる。
\begin{equation} \tag{4}
\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \exists y \in Y \, ( U(y, \epsilon ) \in \mathbf{F} )
\end{equation}
$\iota[X]$ が $Y$ において稠密だから $\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \forall y \in Y \, ( U(y, \epsilon ) \cap \iota[X] \neq \emptyset )$ である。これより、
\begin{equation*}
\mathbf{A} = \{ \, A \subseteq X \, \mid \, \exists \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \exists y \in Y \, ( U(y, \epsilon ) \in \mathbf{F} \land \iota[A] = U(y, \epsilon ) \cap \iota[X] ) \, \}
\end{equation*}
と定めると、$\mathbf{F}$ の条件($4$)より $\mathbf{A}$ は空でない。また、任意に有限個の $\mathbf{A}$ の要素 $A_1, A_2, \cdots , A_n$ をとると、$\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots , \epsilon_n \in \mathbb{R}^+$ と $y_1, y_2, \cdots , y_n \in X$ が存在して、
\begin{equation*}
U(y_i, \epsilon_i ) \in \mathbf{F} \land \iota[A_i] = U(y_i, \epsilon_i ) \cap \iota[X] \quad (i=1,2, \cdots ,n)
\end{equation*}
であるから、
\begin{equation*}
\iota[A_1] \cap \iota[A_2] \cap \cdots \cap \iota[A_n] = ( U(y_1, \epsilon_1 ) \cap U(y_2, \epsilon_2 ) \cap \cdots \cap U(y_n, \epsilon_n ) ) \cap \iota[X] \neq \emptyset
\end{equation*}
ここで最後の $\neq \emptyset$ は、$U(y_1, \epsilon_1 ) \cap U(y_2, \epsilon_2 ) \cap \cdots \cap U(y_n, \epsilon_n ) \in \mathbf{F}$ と $\mathbf{F}$ の有限交差性より、$\in$ の左側が空でない開集合であることと、$\iota[X]$ が $Y$ において稠密であることから導かれる。従って、
\begin{equation*}
A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n \neq \emptyset
\end{equation*}
であるから $\mathbf{A}$ は有限交差性をもち、これより $\mathbf{A}$ を含む $X$ 上の超フィルター $\mathbf{B}$ が存在する。
$\mathbf{B} \in \mathrm{U}_C(X)$ を示す。任意に $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ をとると、($4$)よりある $y \in Y$ に対して
\begin{equation*}
U(y, \epsilon /3 ) \in \mathbf{F} \land \iota[A] = U(y, \epsilon /3 ) \cap \iota[X]
\end{equation*}
となる $A \in \mathbf{A} \subseteq \mathbf{B}$ が存在する。$a \in A$ を一つとると、任意の $x \in A$ に対して、
\begin{equation*}
d_X(x,a) = d_Y( \iota(x), \iota(a) ) \le d_Y( \iota(x), y ) + d_Y( \iota(a), y ) < \epsilon /3 + \epsilon /3 = 2 \epsilon /3
\end{equation*}
であり、任意の $B \in \mathbf{B}$ は $A \cap B \neq \emptyset$ をみたすから $\mathrm{dist}_X( B, \{a\} ) < 2 \epsilon /3$ である。従って、
\begin{equation*}
\bar{d}_X( \mathbf{B}, \uparrow a ) \le 2 \epsilon /3 < \epsilon
\end{equation*}
これで($2$)より $\mathbf{B} \in \mathrm{U}_C(X)$ が示されたから、$b = [ \mathbf{B} ]$ として $b \in Y$ が定まる。
最後に次が成立すること( $\mathbf{F}$ が この $b$ に収束すること)を示す。
\begin{equation} \tag{5}
\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, ( U(b, \epsilon ) \in \mathbf{F} )
\end{equation}
これが成立しないと仮定して矛盾を導く。このとき $U(b, \epsilon ) \notin \mathbf{F}$ となる $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ が存在する。($4$)より $U(c, \epsilon /4) \in \mathbf{F}$ をみたす $c \in Y$ がとれ、$\iota[C] = U(c, \epsilon /4 ) \cap \iota[X]$ となる $C \subseteq X$ をとると $C \in \mathbf{A} \subseteq \mathbf{B}$ である。$U(b, \epsilon ) \notin \mathbf{F}$ より $U(c, \epsilon /4) \not \subseteq U(b, \epsilon )$ であるから $d_Y(b,c) > 3 \epsilon /4$ でなければならない。一方、$\iota[X]$ が $Y$ において稠密だから、
\begin{equation*}
d_Y(b, \iota[x] ) < \epsilon /4
\end{equation*}
となる $x \in X$ をとることができる。この $x$ に対し任意に $z \in C$ をとると、
\begin{equation*}
d_X(z, x) = d_Y( \iota[z], \iota[x] ) \ge d_Y(b,c) - d_Y( \iota[z], c ) - d_Y( \iota[x], b ) > 3 \epsilon /4 - \epsilon /4 - \epsilon /4 = \epsilon /4
\end{equation*}
よって $\mathrm{dist}_X( C, \{x\} ) \ge \epsilon /4$ であり、$C \in \mathbf{B}$ かつ $b = [ \mathbf{B} ]$ より
\begin{equation*}
d_Y(b, \iota[x] ) \ge \epsilon /4
\end{equation*}
が得られるが、これは $x$ のとり方に矛盾する。従って($5$)が成立する。
以上で任意の $Y$ 上の超フィルター $\mathbf{F}$ について($3$)が成立することが示されたから、$Y$ は完備である。□
これで、超フィルターを用いた距離空間の完備化の構成法を示すことができました。
4. おわりに
いかがでしたでしょうか。この方法は、距離空間の完備化の構成法として普通にみられるコーシー列を用いたものに比べても相当ゴチャゴチャしていて、手法としてはあまり価値がなさそうな気もしますが、超フィルターのこのような利用法があるということ自体が面白いと思います。また、こちらの記事で紹介した「超準モデルを使った距離空間の完備化」とのアナロジーも感じることができます。一つの手法として紹介しました。
(前記事)
超フィルターを使った距離空間「全有界+完備 ⇔ コンパクト」の証明 [数学]
だいぶ前ですが、超準解析について書いた記事の中で、距離空間における表題の有名な定理を超準モデルを使って証明しました。
本記事では同じ定理を超準モデルではなく、超フィルターを使って証明してみます。超準モデルを使った証明と同じく、距離空間における「全有界」「完備」「コンパクト」のそれぞれの性質が、超フィルターを使った同値な条件で置き換えられることを証明することによって、目的の定理を証明することができます。超フィルターが何かということについては、この記事を参照してください。
では、順に進めていきましょう。本記事全体を通して $(X,d)$ は距離空間とします($X$ は空でない集合、$d : X^2 \mapsto \mathbb{R}$ は距離関数を表します)。以下 $d$ を省略して「距離空間 $X$ 」ということとします。また、正実数の全体を $\mathbb{R}^+$ で表し、さらに $a \in X, \epsilon \in \mathbb{R}^+$ に対し、$a$ を中心とする半径 $\epsilon$ の開球を $U(a, \epsilon)$ で表します。
まずは全有界性から。
(証明)$X$は全有界とし、任意に超フィルター $\mathbf{F}$ をとる。任意に正実数 $\epsilon$ をとると、有限個の$X$の点 $a_1, a_2, \cdots a_n$ が存在して、これらを中心とする半径 $\epsilon$ の開球で $X$ を覆うことができるから、
\[ X \subseteq U(a_1, \epsilon) \cup U(a_2, \epsilon) \cup \cdots \cup U(a_n, \epsilon) \]
が成り立つ。ここで $U(a_1, \epsilon), U(a_2, \epsilon), \cdots , U(a_n, \epsilon)$ のどれも $\mathbf{F}$ に属さないと仮定すると、$\mathbf{F}$ が超フィルターだから $X \setminus U(a_1, \epsilon), X \setminus U(a_2, \epsilon), \cdots , X \setminus U(a_n, \epsilon)$ はすべて $\mathbf{F}$ に属し、かつ
\begin{eqnarray*}
&&( X \setminus U(a_1, \epsilon) ) \cap ( X \setminus U(a_2, \epsilon) ) \cap \cdots \cap ( X \setminus U(a_n, \epsilon) )\\
&=& X \setminus ( U(a_1, \epsilon) \cup U(a_2, \epsilon) \cup \cdots \cup U(a_n, \epsilon) )\\
&=& \emptyset
\end{eqnarray*}
となるが、これはフィルター $\mathbf{F}$ が有限交叉性を持つことに矛盾する。従って仮定が誤りであり、$U(a_1, \epsilon), U(a_2, \epsilon), \cdots , U(a_n, \epsilon)$ のどれかが $\mathbf{F}$ に属するから、$(1)$ が成立する。
逆に、$X$ 上の任意の超フィルター $\mathbf{F}$ に対して$(1)$が成立するものとする。$X$ が全有界でないと仮定すると、ある正実数 $\epsilon$ をとって、どのような $X$ の有限個の点をとってもそれらを中心とする半径 $\epsilon$ の開球で $X$ を覆うことができないようにすることができる。この $\epsilon$ に対し、有限個の半径 $\epsilon$ の開球(中心は任意の点)の和集合の補集合( $X$ からの差)の全体 $\mathbf{A}$ を考える。$\epsilon$ のとり方から明らかに $\mathbf{A}$ は有限交叉性を持つので、$\mathbf{A}$ を含む超フィルター $\mathbf{F}$ が存在する。$(1)$よりある $a \in X$ が存在して $U(a, \epsilon) \in \mathbf{F}$ となるが、一方で $\mathbf{F}$ の作り方より $X \setminus U(a, \epsilon) \in \mathbf{F}$ であるので、$\mathbf{F}$ がフィルターであることと矛盾する。従って $X$ は全有界である。□
次に完備性に移ります。ここで $X$ 上のフィルター $\mathbf{F}$ が点 $x$ に収束するとは、$x$ の近傍が全て $\mathbf{F}$ に属することをいいます。単に $\mathbf{F}$ が収束するとは、ある点 $a$ に収束することです。距離空間の場合にはこれは次と同値です。
\[ \exists a \in X \, \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, (U(a, \epsilon) \in \mathbf{F} ) \tag{2} \]
(証明)$X$は完備とする。任意に$(1)$をみたす$X$ 上の超フィルター $\mathbf{F}$ をとると、$X$ の点列 $\{ a_n \}$ で
\[ \forall n \in \mathbb{N} \, ( n \ge 1 \to U(a_n, 1/n) \in \mathbf{F} ) \]
をみたすものがとれる。この点列と任意の $k \in \mathbb{N}, k \ge 1$ に対し、$m,n \ge k$ ならば $U(a_m, 1/m) \cap U(a_n, 1/n) \in \mathbf{F}$ より $U(a_m, 1/m) \cap U(a_n, 1/n) \ne \emptyset$ だから、ある $x \in U(a_m, 1/m) \cap U(a_n, 1/n)$ がとれて、
\[ d(a_m,a_n) \le d(a_m,x) + d(a_n,x) < 1/m+1/n \le 2/k \]
となるから、$\{ a_n \}$ はコーシー列であり、$X$ の完備性よりある点 $a$ に収束する。超フィルター $\mathbf{F}$ も同じ点に収束することを示す。任意に $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ をとると、$d(a_n,a) < \epsilon /2 \land 1/n < \epsilon /2$ をみたす $n \in \mathbb{N}$ がとれて、任意の $x \in U(a_n, 1/n)$ に対し、
\[ d(x,a) \le d(x,a_n) + d(a_n,a) < 1/n + \epsilon /2 < \epsilon \]
であるから $U(a_n, 1/n) \subseteq U(a, \epsilon)$ であり、従って $U(a, \epsilon) \in \mathbf{F}$ であるから $\mathbf{F}$ は $a$ に収束する。
逆に、$X$ 上の任意の超フィルター $\mathbf{F}$ は$(1)$が成り立つならば収束するものとする。任意に $X$ 上のコーシー列 $\{ a_n \}$ をとる。任意の $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ に対し、ある $k \in \mathbb{N}$ がとれて
\[ m,n \in \mathbb{N} \land m,n \ge k \to d(a_m,a_n) < \epsilon \]
をみたすから、そのような $k$ の最小値を $k(\epsilon)$ とする。こう定めると
\[ n \in \mathbb{N} \land n \ge k(\epsilon) \to a_n \in U(a_{k(\epsilon)},\epsilon) \]
が成り立つ。有限個の $\epsilon_1 \ge \epsilon_2 \ge \cdots \ge \epsilon_m$ に対して $k(\epsilon_1) \le k(\epsilon_2) \le \cdots \le k(\epsilon_m)$ だから、
\[ a_{k(\epsilon_m)} \in U(a_{k(\epsilon_1)},\epsilon_1) \cap U(a_{k(\epsilon_2)},\epsilon_2) \cap \cdots \cap U(a_{k(\epsilon_m)},\epsilon_m) \]
であり、これより $X$ の部分集合の族 $\mathbf{A}$ を
\[ \mathbf{A} = \{ \, U(a_{k(\epsilon)}, \epsilon) \, \mid \, \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \} \]
と定めると、$\mathbf{A}$ は有限交叉性を持ち、よって $\mathbf{A}$ を含む超フィルター $\mathbf{F}$ が存在する。明らかにこの $\mathbf{F}$ は$(1)$をみたすから、仮定によって $\mathbf{F}$ はある点 $a$ に収束する。点列 $\{ a_n \}$ も同じ点 $a$ に収束することを示す。これが成り立たないと仮定すると、ある $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ が存在して、$d(a_n,a) \ge \epsilon$ となるようないくらでも大きい $n \in \mathbb{N}$ がとれる。そこで $n \ge k(\epsilon /3) \land d(a_n,a) \ge \epsilon$ となる $n \in \mathbb{N}$ をとると、$d(a_n,a_{k(\epsilon /3)})
< \epsilon /3$ だから、
\[ d(a,a_{k(\epsilon /3)}) \ge d(a_n,a) - d(a_n,a_{k(\epsilon /3)}) > \epsilon - \epsilon /3 = 2 \epsilon /3 \]
であり、これより $U(a, \epsilon /3) \cap U(a_{k(\epsilon /3)}, \epsilon /3) = \emptyset$ が従う。しかし、$\mathbf{F}$ が $a$ に収束するから $U(a, \epsilon /3) \in \mathbf{F}$ であり、また $\mathbf{F}$ の作り方より $U(a_{k(\epsilon /3)}, \epsilon /3) \in \mathbf{F}$ であるから、これは $\mathbf{F}$ がフィルターであることと矛盾する。従って $\{ a_n \}$ は $a$ に収束するから、$X$ 上の任意のコーシー列は収束し、$X$ は完備である。□
(【定理2】の証明をよく見ると、$\mathbf{F}$ について超フィルターの性質が使われていません。ということは【定理2】の「超フィルター」をただの「フィルター」に置き換えても成立するということになりますが、話の流れがややこしくなるのでこのままにしておきます。)
続いてコンパクト性に移ります。これは距離空間にとどまらず一般の位相空間で成立する定理ですが、証明は全有界性についての【定理1】と非常によく似ています。
(証明)$X$ はコンパクトとする。$X$ 上の超フィルターでどの点にも収束しないものが存在すると仮定し、$\mathbf{F}$ がそのような超フィルターとする。任意の $a \in X$ に対し、$a$ の開近傍 $U(a)$ で $U(a) \notin \mathbf{F}$ をみたすようなものがとれる。すべての $a \in X$ に対する $U(a)$ の全体は $X$ の開被覆になるから、$X$ のコンパクト性よりそのうちの有限個 $U(a_1), U(a_2), \cdots , U(a_n)$ によって
\[ X \subseteq U(a_1) \cup U(a_2) \cup \cdots \cup U(a_n) \]
が成り立つ。$U(a_1), U(a_2), \cdots , U(a_n)$ はどれも $\mathbf{F}$ に属さないから、【定理1】の証明の前半と同様の考察によって矛盾が導かれる。従って $X$ 上の任意の超フィルターはある点に収束する。
逆に、$X$ 上の任意の超フィルターは収束するものとする。$X$ がコンパクトでないと仮定すると、ある $X$ の開被覆 $\mathbf{S}$ で、どの有限個をとっても $X$ の被覆にならないものが存在する。有限個の $\mathbf{S}$ の要素の和集合の補集合の全体 $\mathbf{A}$ を考える。$\mathbf{S}$ の性質から明らかに $\mathbf{A}$ は有限交叉性を持つので、$\mathbf{A}$ を含む超フィルター $\mathbf{F}$ が存在する。$\mathbf{F}$ はある $a \in X$ に収束するから、$a \in A \in \mathbf{S}$ をみたす $A$ が存在し、$A$ は開集合だから $A \in \mathbf{F}$ となるが、一方で $\mathbf{F}$ の作り方より $X \setminus A \in \mathbf{F}$ であるので、$\mathbf{F}$ がフィルターであることと矛盾する。従って $X$ はコンパクトである。□
さて、【定理1】から【定理3】を証明してしまうと、本記事の目的である次の定理はほとんど自明になってしまいました。
(証明)$X$ が全有界かつ完備ならば、$X$ 上の任意の超フィルターは、【定理1】より$(1)$をみたし、かつ【定理2】より「$(1)$が成り立つならば収束する」をみたすから、収束する。従って【定理3】より $X$ はコンパクトである。
逆に $X$ がコンパクトならば、$X$ 上の任意の超フィルターは、【定理3】より収束するから$(2)$を満たし、$(2)$より$(1)$は明らかに従うので【定理1】より $X$ は全有界である。さらに「$(1)$が成り立つならば収束する」も自明に成り立つから、【定理2】より $X$ は完備である。□
以上で、超フィルターを使ってタイトルの結果を証明することができました。流れとしてはこの記事で紹介した超準モデルを使った証明の類似になっています。ただやはり超準モデルのシンプルな論理式と比べると、フィルターそのものの複雑さも相まってちょっとモッチャリした感は否めません(個人の感想です)。
(続く)(前記事)
本記事では同じ定理を超準モデルではなく、超フィルターを使って証明してみます。超準モデルを使った証明と同じく、距離空間における「全有界」「完備」「コンパクト」のそれぞれの性質が、超フィルターを使った同値な条件で置き換えられることを証明することによって、目的の定理を証明することができます。超フィルターが何かということについては、この記事を参照してください。
では、順に進めていきましょう。本記事全体を通して $(X,d)$ は距離空間とします($X$ は空でない集合、$d : X^2 \mapsto \mathbb{R}$ は距離関数を表します)。以下 $d$ を省略して「距離空間 $X$ 」ということとします。また、正実数の全体を $\mathbb{R}^+$ で表し、さらに $a \in X, \epsilon \in \mathbb{R}^+$ に対し、$a$ を中心とする半径 $\epsilon$ の開球を $U(a, \epsilon)$ で表します。
まずは全有界性から。
【定理1】距離空間 $X$ が全有界であることと、
「$X$ 上の任意の超フィルター $\mathbf{F}$ に対して \[ \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \exists a \in X \, (U(a, \epsilon) \in \mathbf{F} ) \tag{1} \] が成り立つ。」
ことは同値である。
「$X$ 上の任意の超フィルター $\mathbf{F}$ に対して \[ \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \exists a \in X \, (U(a, \epsilon) \in \mathbf{F} ) \tag{1} \] が成り立つ。」
ことは同値である。
(証明)$X$は全有界とし、任意に超フィルター $\mathbf{F}$ をとる。任意に正実数 $\epsilon$ をとると、有限個の$X$の点 $a_1, a_2, \cdots a_n$ が存在して、これらを中心とする半径 $\epsilon$ の開球で $X$ を覆うことができるから、
\[ X \subseteq U(a_1, \epsilon) \cup U(a_2, \epsilon) \cup \cdots \cup U(a_n, \epsilon) \]
が成り立つ。ここで $U(a_1, \epsilon), U(a_2, \epsilon), \cdots , U(a_n, \epsilon)$ のどれも $\mathbf{F}$ に属さないと仮定すると、$\mathbf{F}$ が超フィルターだから $X \setminus U(a_1, \epsilon), X \setminus U(a_2, \epsilon), \cdots , X \setminus U(a_n, \epsilon)$ はすべて $\mathbf{F}$ に属し、かつ
\begin{eqnarray*}
&&( X \setminus U(a_1, \epsilon) ) \cap ( X \setminus U(a_2, \epsilon) ) \cap \cdots \cap ( X \setminus U(a_n, \epsilon) )\\
&=& X \setminus ( U(a_1, \epsilon) \cup U(a_2, \epsilon) \cup \cdots \cup U(a_n, \epsilon) )\\
&=& \emptyset
\end{eqnarray*}
となるが、これはフィルター $\mathbf{F}$ が有限交叉性を持つことに矛盾する。従って仮定が誤りであり、$U(a_1, \epsilon), U(a_2, \epsilon), \cdots , U(a_n, \epsilon)$ のどれかが $\mathbf{F}$ に属するから、$(1)$ が成立する。
逆に、$X$ 上の任意の超フィルター $\mathbf{F}$ に対して$(1)$が成立するものとする。$X$ が全有界でないと仮定すると、ある正実数 $\epsilon$ をとって、どのような $X$ の有限個の点をとってもそれらを中心とする半径 $\epsilon$ の開球で $X$ を覆うことができないようにすることができる。この $\epsilon$ に対し、有限個の半径 $\epsilon$ の開球(中心は任意の点)の和集合の補集合( $X$ からの差)の全体 $\mathbf{A}$ を考える。$\epsilon$ のとり方から明らかに $\mathbf{A}$ は有限交叉性を持つので、$\mathbf{A}$ を含む超フィルター $\mathbf{F}$ が存在する。$(1)$よりある $a \in X$ が存在して $U(a, \epsilon) \in \mathbf{F}$ となるが、一方で $\mathbf{F}$ の作り方より $X \setminus U(a, \epsilon) \in \mathbf{F}$ であるので、$\mathbf{F}$ がフィルターであることと矛盾する。従って $X$ は全有界である。□
次に完備性に移ります。ここで $X$ 上のフィルター $\mathbf{F}$ が点 $x$ に収束するとは、$x$ の近傍が全て $\mathbf{F}$ に属することをいいます。単に $\mathbf{F}$ が収束するとは、ある点 $a$ に収束することです。距離空間の場合にはこれは次と同値です。
\[ \exists a \in X \, \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, (U(a, \epsilon) \in \mathbf{F} ) \tag{2} \]
【定理2】距離空間 $X$ が完備であることと、
「$X$ 上の任意の超フィルター $\mathbf{F}$ は、$(1)$が成り立つならば収束する。」すなわち
「$X$ 上の任意の超フィルター $\mathbf{F}$ に対して \[ \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \exists a \in X \, (U(a, \epsilon) \in \mathbf{F} ) \to \exists a \in X \, \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, (U(a, \epsilon) \in \mathbf{F} ) \] が成り立つ」
ことは同値である。
「$X$ 上の任意の超フィルター $\mathbf{F}$ は、$(1)$が成り立つならば収束する。」すなわち
「$X$ 上の任意の超フィルター $\mathbf{F}$ に対して \[ \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \exists a \in X \, (U(a, \epsilon) \in \mathbf{F} ) \to \exists a \in X \, \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, (U(a, \epsilon) \in \mathbf{F} ) \] が成り立つ」
ことは同値である。
(証明)$X$は完備とする。任意に$(1)$をみたす$X$ 上の超フィルター $\mathbf{F}$ をとると、$X$ の点列 $\{ a_n \}$ で
\[ \forall n \in \mathbb{N} \, ( n \ge 1 \to U(a_n, 1/n) \in \mathbf{F} ) \]
をみたすものがとれる。この点列と任意の $k \in \mathbb{N}, k \ge 1$ に対し、$m,n \ge k$ ならば $U(a_m, 1/m) \cap U(a_n, 1/n) \in \mathbf{F}$ より $U(a_m, 1/m) \cap U(a_n, 1/n) \ne \emptyset$ だから、ある $x \in U(a_m, 1/m) \cap U(a_n, 1/n)$ がとれて、
\[ d(a_m,a_n) \le d(a_m,x) + d(a_n,x) < 1/m+1/n \le 2/k \]
となるから、$\{ a_n \}$ はコーシー列であり、$X$ の完備性よりある点 $a$ に収束する。超フィルター $\mathbf{F}$ も同じ点に収束することを示す。任意に $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ をとると、$d(a_n,a) < \epsilon /2 \land 1/n < \epsilon /2$ をみたす $n \in \mathbb{N}$ がとれて、任意の $x \in U(a_n, 1/n)$ に対し、
\[ d(x,a) \le d(x,a_n) + d(a_n,a) < 1/n + \epsilon /2 < \epsilon \]
であるから $U(a_n, 1/n) \subseteq U(a, \epsilon)$ であり、従って $U(a, \epsilon) \in \mathbf{F}$ であるから $\mathbf{F}$ は $a$ に収束する。
逆に、$X$ 上の任意の超フィルター $\mathbf{F}$ は$(1)$が成り立つならば収束するものとする。任意に $X$ 上のコーシー列 $\{ a_n \}$ をとる。任意の $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ に対し、ある $k \in \mathbb{N}$ がとれて
\[ m,n \in \mathbb{N} \land m,n \ge k \to d(a_m,a_n) < \epsilon \]
をみたすから、そのような $k$ の最小値を $k(\epsilon)$ とする。こう定めると
\[ n \in \mathbb{N} \land n \ge k(\epsilon) \to a_n \in U(a_{k(\epsilon)},\epsilon) \]
が成り立つ。有限個の $\epsilon_1 \ge \epsilon_2 \ge \cdots \ge \epsilon_m$ に対して $k(\epsilon_1) \le k(\epsilon_2) \le \cdots \le k(\epsilon_m)$ だから、
\[ a_{k(\epsilon_m)} \in U(a_{k(\epsilon_1)},\epsilon_1) \cap U(a_{k(\epsilon_2)},\epsilon_2) \cap \cdots \cap U(a_{k(\epsilon_m)},\epsilon_m) \]
であり、これより $X$ の部分集合の族 $\mathbf{A}$ を
\[ \mathbf{A} = \{ \, U(a_{k(\epsilon)}, \epsilon) \, \mid \, \epsilon \in \mathbb{R}^+ \, \} \]
と定めると、$\mathbf{A}$ は有限交叉性を持ち、よって $\mathbf{A}$ を含む超フィルター $\mathbf{F}$ が存在する。明らかにこの $\mathbf{F}$ は$(1)$をみたすから、仮定によって $\mathbf{F}$ はある点 $a$ に収束する。点列 $\{ a_n \}$ も同じ点 $a$ に収束することを示す。これが成り立たないと仮定すると、ある $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ が存在して、$d(a_n,a) \ge \epsilon$ となるようないくらでも大きい $n \in \mathbb{N}$ がとれる。そこで $n \ge k(\epsilon /3) \land d(a_n,a) \ge \epsilon$ となる $n \in \mathbb{N}$ をとると、$d(a_n,a_{k(\epsilon /3)})
< \epsilon /3$ だから、
\[ d(a,a_{k(\epsilon /3)}) \ge d(a_n,a) - d(a_n,a_{k(\epsilon /3)}) > \epsilon - \epsilon /3 = 2 \epsilon /3 \]
であり、これより $U(a, \epsilon /3) \cap U(a_{k(\epsilon /3)}, \epsilon /3) = \emptyset$ が従う。しかし、$\mathbf{F}$ が $a$ に収束するから $U(a, \epsilon /3) \in \mathbf{F}$ であり、また $\mathbf{F}$ の作り方より $U(a_{k(\epsilon /3)}, \epsilon /3) \in \mathbf{F}$ であるから、これは $\mathbf{F}$ がフィルターであることと矛盾する。従って $\{ a_n \}$ は $a$ に収束するから、$X$ 上の任意のコーシー列は収束し、$X$ は完備である。□
(【定理2】の証明をよく見ると、$\mathbf{F}$ について超フィルターの性質が使われていません。ということは【定理2】の「超フィルター」をただの「フィルター」に置き換えても成立するということになりますが、話の流れがややこしくなるのでこのままにしておきます。)
続いてコンパクト性に移ります。これは距離空間にとどまらず一般の位相空間で成立する定理ですが、証明は全有界性についての【定理1】と非常によく似ています。
【定理3】位相空間 $X$ がコンパクトであることと、
「$X$ 上の任意の超フィルターは収束する」
ことは同値である。
「$X$ 上の任意の超フィルターは収束する」
ことは同値である。
(証明)$X$ はコンパクトとする。$X$ 上の超フィルターでどの点にも収束しないものが存在すると仮定し、$\mathbf{F}$ がそのような超フィルターとする。任意の $a \in X$ に対し、$a$ の開近傍 $U(a)$ で $U(a) \notin \mathbf{F}$ をみたすようなものがとれる。すべての $a \in X$ に対する $U(a)$ の全体は $X$ の開被覆になるから、$X$ のコンパクト性よりそのうちの有限個 $U(a_1), U(a_2), \cdots , U(a_n)$ によって
\[ X \subseteq U(a_1) \cup U(a_2) \cup \cdots \cup U(a_n) \]
が成り立つ。$U(a_1), U(a_2), \cdots , U(a_n)$ はどれも $\mathbf{F}$ に属さないから、【定理1】の証明の前半と同様の考察によって矛盾が導かれる。従って $X$ 上の任意の超フィルターはある点に収束する。
逆に、$X$ 上の任意の超フィルターは収束するものとする。$X$ がコンパクトでないと仮定すると、ある $X$ の開被覆 $\mathbf{S}$ で、どの有限個をとっても $X$ の被覆にならないものが存在する。有限個の $\mathbf{S}$ の要素の和集合の補集合の全体 $\mathbf{A}$ を考える。$\mathbf{S}$ の性質から明らかに $\mathbf{A}$ は有限交叉性を持つので、$\mathbf{A}$ を含む超フィルター $\mathbf{F}$ が存在する。$\mathbf{F}$ はある $a \in X$ に収束するから、$a \in A \in \mathbf{S}$ をみたす $A$ が存在し、$A$ は開集合だから $A \in \mathbf{F}$ となるが、一方で $\mathbf{F}$ の作り方より $X \setminus A \in \mathbf{F}$ であるので、$\mathbf{F}$ がフィルターであることと矛盾する。従って $X$ はコンパクトである。□
さて、【定理1】から【定理3】を証明してしまうと、本記事の目的である次の定理はほとんど自明になってしまいました。
【定理4】距離空間においては、全有界かつ完備であることと、コンパクトであることは同値である。
(証明)$X$ が全有界かつ完備ならば、$X$ 上の任意の超フィルターは、【定理1】より$(1)$をみたし、かつ【定理2】より「$(1)$が成り立つならば収束する」をみたすから、収束する。従って【定理3】より $X$ はコンパクトである。
逆に $X$ がコンパクトならば、$X$ 上の任意の超フィルターは、【定理3】より収束するから$(2)$を満たし、$(2)$より$(1)$は明らかに従うので【定理1】より $X$ は全有界である。さらに「$(1)$が成り立つならば収束する」も自明に成り立つから、【定理2】より $X$ は完備である。□
以上で、超フィルターを使ってタイトルの結果を証明することができました。流れとしてはこの記事で紹介した超準モデルを使った証明の類似になっています。ただやはり超準モデルのシンプルな論理式と比べると、フィルターそのものの複雑さも相まってちょっとモッチャリした感は否めません(個人の感想です)。
(続く)(前記事)
続・超フィルターによる全順序集合の拡大 [数学]
昨年の12月に書いた「超フィルターによる全順序集合の拡大」の記事の続きです。
全順序集合 $X$ に対し、$X$ 上の超フィルター間に擬順序関係を定め、それを使って全順序集合 $\widehat{X}$ を構成し、$X$ を $\widehat{X}$ に埋め込みました。
この $\widehat{X}$ がどんな構造になっているかを、もう少しきちんと調べてみます。
まず、元の $X$ を2個の部分に「切断」します。具体的には、$X$ の2個の部分集合の組 $X_1, X_2$ で、次の性質を持つものを考えます。
\begin{equation*}
X_1 \neq \emptyset \ \land \ X_2 \neq \emptyset \ \land \ X_1 \cup X_2 = X \ \land \ X_1 < X_2
\end{equation*}
ここで最後の式は $\forall x_1 \in X_1 \, \forall x_2 \in X_2 \, (x_1 < x_2)$ の略記です。この条件をみたす組 $(X_1, X_2)$ を $X$ の切断と呼ぶことにします(切断が存在すれば、当然 $X$ は2個以上の元を持ちますので、以下そのことを仮定します)。
$X$ が有理数体 $\mathbb{Q}$ のときは、切断がそれぞれ唯一の実数に対応するという有名な事実がありました。しかし超フィルターから構成した今回の $\widehat{X}$ では、$X_1$ の上限と $X_2$ の下限に対応するそれぞれ別の $\widehat{X}$ の元が存在するのです。
(証明)任意の $a \in X_1$ に対して、
\begin{equation*}
I_a = \{ \, x \in X_1 \, \mid \, a \le x \, \}
\end{equation*}
とおくと、$I_a$ は $X$ の区間であり、これら $I_a$ の全体からなる集合族は明らかに有限交差性を持つので、それらを含む超フィルター $\mathbf{A}$ が作れ、$\alpha = [\mathbf{A}]$ が $\widehat{X}$ の元として定まる。同様に、任意の $b \in X_2$ に対して、
\begin{equation*}
I_b = \{ \, x \in X_2 \, \mid \, x \le b \, \}
\end{equation*}
とおくと、これらの区間 $I_b$ の全体を含む超フィルター $\mathbf{B}$ が作れ、$\beta = [\mathbf{B}]$ が $\widehat{X}$ の元として定まる。作り方から明らかに $\lnot(\mathbf{B} \preceq \mathbf{A})$ なので $\alpha < \beta$ である。ある $a \in X_1$ が $\alpha < a$ となったと仮定すると、ある $A \in \mathbf{A}$ が $A < \{ a \}$ をみたすが、これから $A \cap I_a = \emptyset$ が従うから $\mathbf{A}$ のフィルターの条件に反し矛盾であり、従って $\forall x \in X_1 \, (x \le \alpha)$ が成立する。$\forall x \in X_2 \, (\beta \le x)$ も同様に示される。
$\alpha, \beta$ がそれぞれ唯一に定まることを示す。このためには、
\begin{equation*}
\forall x \in X_1 \, (x \le \alpha) \land \alpha < \gamma < \beta \land \forall x \in X_2 \, (\beta \le x)
\end{equation*}
をみたす $\alpha, \beta, \gamma \in \widehat{X}$ が存在しえないことを示せばよい(唯一に定まらなければ必ずこのような順序関係になる $\widehat{X}$ の3個の元が存在する)。そこでこれらが存在すると仮定して矛盾を導く。$\alpha = [\mathbf{A}], \beta = [\mathbf{B}], \gamma = [\mathbf{C}]$ とすると、$\alpha < \gamma < \beta$ より、
\begin{equation*}
A < C_1\ \land \ C_2 < B
\end{equation*}
をみたす $A \in \mathbf{A}, C_1, C_2 \in \mathbf{C}, B \in \mathbf{B}$ が存在する。$\mathbf{C}$ のフィルターの条件より $c \in C_1 \cap C_2$ となる $c \in X$ が存在し、
\begin{equation*}
A < \{ c \} < B
\end{equation*}
が成り立つが、$c$ で生成される $X$ 上の単項フィルター $\uparrow c$ によって $\widehat{X}$ 上で $c = [ \uparrow c ]$ とみなされるから、$\alpha < c < \beta$ が成り立ち、$c \in X_1$ としても $c \in X_2$ としても矛盾である。従って $\alpha, \beta$ は唯一に定まる。□
逆に、任意に $\widehat{X}$ の元 $\gamma$ を取ると、それは
① ある $X$ の切断の境界に位置し、切断の下側の上限か、または上側の下限となる。
② 全ての $X$ の元より大きい。
③ 全ての $X$ の元より小さい。
のどれかになります。そして、②をみたす $\widehat{X}$ の元は、任意の $a \in X$ に対して、
\begin{equation*}
I_a = \{ \, x \in X \, \mid \, a \le x \, \}
\end{equation*}
で定まる $X$ の区間 $I_a$ の全体を含む超フィルターから構成できて、同様に③をみたす $\widehat{X}$ の元は、任意の $b \in X$ に対して、
\begin{equation*}
I_b = \{ \, x \in X \, \mid \, x \le b \, \}
\end{equation*}
で定まる $X$ の区間 $I_b$ の全体を含む超フィルターから構成できて、それぞれ唯一に定まります。
以上で全順序集合 $X$ から超フィルターによって構成された $\widehat{X}$ の構造が明らかになりました。また、前回で証明を省略した「 $\widehat{X}$ は順序完備である」という事実についても、$\widehat{X}$ の任意の切断に対してそれに対応する $X$ の切断を考えて【定理】を適用することにより、切断の境界に位置する $\widehat{X}$ の元が高々2個存在することがわかるので、これで順序完備であることが証明できました。
これ、何に使えるんでしょうか?まだよくわかりません。
(続く)(前記事)
全順序集合 $X$ に対し、$X$ 上の超フィルター間に擬順序関係を定め、それを使って全順序集合 $\widehat{X}$ を構成し、$X$ を $\widehat{X}$ に埋め込みました。
この $\widehat{X}$ がどんな構造になっているかを、もう少しきちんと調べてみます。
まず、元の $X$ を2個の部分に「切断」します。具体的には、$X$ の2個の部分集合の組 $X_1, X_2$ で、次の性質を持つものを考えます。
\begin{equation*}
X_1 \neq \emptyset \ \land \ X_2 \neq \emptyset \ \land \ X_1 \cup X_2 = X \ \land \ X_1 < X_2
\end{equation*}
ここで最後の式は $\forall x_1 \in X_1 \, \forall x_2 \in X_2 \, (x_1 < x_2)$ の略記です。この条件をみたす組 $(X_1, X_2)$ を $X$ の切断と呼ぶことにします(切断が存在すれば、当然 $X$ は2個以上の元を持ちますので、以下そのことを仮定します)。
$X$ が有理数体 $\mathbb{Q}$ のときは、切断がそれぞれ唯一の実数に対応するという有名な事実がありました。しかし超フィルターから構成した今回の $\widehat{X}$ では、$X_1$ の上限と $X_2$ の下限に対応するそれぞれ別の $\widehat{X}$ の元が存在するのです。
【定理】$X$ の切断 $(X_1, X_2)$ に対して、
\begin{equation*}
\forall x \in X_1 \, (x \le \alpha) \ \land \ \alpha < \beta \ \land \ \forall x \in X_2 \, (\beta \le x)
\end{equation*}
となるような $\widehat{X}$ の2個の元 $\alpha, \beta$ がそれぞれ唯一存在する。
(証明)任意の $a \in X_1$ に対して、
\begin{equation*}
I_a = \{ \, x \in X_1 \, \mid \, a \le x \, \}
\end{equation*}
とおくと、$I_a$ は $X$ の区間であり、これら $I_a$ の全体からなる集合族は明らかに有限交差性を持つので、それらを含む超フィルター $\mathbf{A}$ が作れ、$\alpha = [\mathbf{A}]$ が $\widehat{X}$ の元として定まる。同様に、任意の $b \in X_2$ に対して、
\begin{equation*}
I_b = \{ \, x \in X_2 \, \mid \, x \le b \, \}
\end{equation*}
とおくと、これらの区間 $I_b$ の全体を含む超フィルター $\mathbf{B}$ が作れ、$\beta = [\mathbf{B}]$ が $\widehat{X}$ の元として定まる。作り方から明らかに $\lnot(\mathbf{B} \preceq \mathbf{A})$ なので $\alpha < \beta$ である。ある $a \in X_1$ が $\alpha < a$ となったと仮定すると、ある $A \in \mathbf{A}$ が $A < \{ a \}$ をみたすが、これから $A \cap I_a = \emptyset$ が従うから $\mathbf{A}$ のフィルターの条件に反し矛盾であり、従って $\forall x \in X_1 \, (x \le \alpha)$ が成立する。$\forall x \in X_2 \, (\beta \le x)$ も同様に示される。
$\alpha, \beta$ がそれぞれ唯一に定まることを示す。このためには、
\begin{equation*}
\forall x \in X_1 \, (x \le \alpha) \land \alpha < \gamma < \beta \land \forall x \in X_2 \, (\beta \le x)
\end{equation*}
をみたす $\alpha, \beta, \gamma \in \widehat{X}$ が存在しえないことを示せばよい(唯一に定まらなければ必ずこのような順序関係になる $\widehat{X}$ の3個の元が存在する)。そこでこれらが存在すると仮定して矛盾を導く。$\alpha = [\mathbf{A}], \beta = [\mathbf{B}], \gamma = [\mathbf{C}]$ とすると、$\alpha < \gamma < \beta$ より、
\begin{equation*}
A < C_1\ \land \ C_2 < B
\end{equation*}
をみたす $A \in \mathbf{A}, C_1, C_2 \in \mathbf{C}, B \in \mathbf{B}$ が存在する。$\mathbf{C}$ のフィルターの条件より $c \in C_1 \cap C_2$ となる $c \in X$ が存在し、
\begin{equation*}
A < \{ c \} < B
\end{equation*}
が成り立つが、$c$ で生成される $X$ 上の単項フィルター $\uparrow c$ によって $\widehat{X}$ 上で $c = [ \uparrow c ]$ とみなされるから、$\alpha < c < \beta$ が成り立ち、$c \in X_1$ としても $c \in X_2$ としても矛盾である。従って $\alpha, \beta$ は唯一に定まる。□
逆に、任意に $\widehat{X}$ の元 $\gamma$ を取ると、それは
① ある $X$ の切断の境界に位置し、切断の下側の上限か、または上側の下限となる。
② 全ての $X$ の元より大きい。
③ 全ての $X$ の元より小さい。
のどれかになります。そして、②をみたす $\widehat{X}$ の元は、任意の $a \in X$ に対して、
\begin{equation*}
I_a = \{ \, x \in X \, \mid \, a \le x \, \}
\end{equation*}
で定まる $X$ の区間 $I_a$ の全体を含む超フィルターから構成できて、同様に③をみたす $\widehat{X}$ の元は、任意の $b \in X$ に対して、
\begin{equation*}
I_b = \{ \, x \in X \, \mid \, x \le b \, \}
\end{equation*}
で定まる $X$ の区間 $I_b$ の全体を含む超フィルターから構成できて、それぞれ唯一に定まります。
以上で全順序集合 $X$ から超フィルターによって構成された $\widehat{X}$ の構造が明らかになりました。また、前回で証明を省略した「 $\widehat{X}$ は順序完備である」という事実についても、$\widehat{X}$ の任意の切断に対してそれに対応する $X$ の切断を考えて【定理】を適用することにより、切断の境界に位置する $\widehat{X}$ の元が高々2個存在することがわかるので、これで順序完備であることが証明できました。
これ、何に使えるんでしょうか?まだよくわかりません。
(続く)(前記事)
超フィルターによる全順序集合の拡大 [数学]
【この記事は 日曜数学 Advent Calendar 2021 の、12月12日用として書きました。】
「超フィルター」については、知っている人はよく知っていると思います(知らない方はWikipediaの記事などを参照してください)。コンパクト性の特徴付けや超準解析に使われるなど、色々と面白い性質を持っています。
この超フィルターを使って、全順序集合を拡大することができます。この辺りの話は探せばどこかに論文や記事があると思いますが、練習問題のつもりで自分でやってみたところ、予想に反して何やら奇妙な集合ができあがってきましたので、本記事ではそれを紹介します。
0.予備知識
まず、本記事で用いるフィルターに関する予備知識を列記します。
$X$ を空でない集合とすると、$X$ の部分集合の族 $\mathbf{F} \, ( \neq \emptyset )$ が $X$ の冪集合上のフィルター(本記事では単に $X$ 上のフィルターと言います)であるとは、次の3つの条件を満たすことを言います。
(1) $\emptyset \notin \mathbf{F}$
(2) $A, B \in \mathbf{F} \to A \cap B \in \mathbf{F}$
(3) $A \in \mathbf{F} \land A \subseteq B \subseteq X \to B \in \mathbf{F}$
(1)と(2)から、フィルターから有限個の元をどう取っても、それらの共通部分は空にならないことがわかります。この性質を有限交差性と言います。逆に、$X$ の部分集合の族が有限交差性を持つならば、それらを含む $X$ 上のフィルターが存在します。
ツォルンの補題を使うと、任意のフィルターに対し、それを含む極大フィルターの存在が証明できます。極大フィルターは超フィルターとも呼ばれます。$X$ 上のフィルター $\mathbf{F}$ が超フィルターであることと、次の性質とは同値です。
(4) $A \subseteq X \to A \in \mathbf{F} \lor X \setminus A \in \mathbf{F}$
$X$ の任意の元 $x$ に対し、$x$ を元に持つ $X$ の部分集合の全体は、超フィルターになります。これを $x$ が生成する単項フィルターと呼び、$\uparrow x$ と書きます。$X$ が有限集合ならば $X$ 上の超フィルターは必ず単項フィルターですが、$X$ が無限集合ならば単項フィルターにならない超フィルター(非単項超フィルター)が存在します。
非単項超フィルターは実体がイメージしにくく、存在することはわかっても具体的にビシッと記述することはできませんが、それだけに深掘りすると面白いです。しかし本記事で用いる予備知識としてはここまであれば十分です。
1.超フィルター間に擬順序関係を定める
$(X, \le)$ を全順序集合とします。例えば有理数の順序集合 $(\mathbb{Q}, \le)$ がその一例です。
$X$ 上の超フィルターの全体を $\mathrm{U}(X)$ とし、その元 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ に対して次によって関係 $\preceq$ を定めます。
\begin{equation*}
\mathbf{A} \preceq \mathbf{B} \quad \Leftrightarrow \quad \forall A \in \mathbf{A} \, \forall B \in \mathbf{B} \, \exists a \in A \, \exists b \in B \, (a \le b)
\end{equation*}
つまり「超フィルター $\mathbf{A}$ と $\mathbf{B}$ からそれぞれどのように( $X$ の部分集合である)元 $A,B$ を取っても、$B$ が $A$ より完全に下になることはない」という関係を $\mathbf{A} \preceq \mathbf{B}$ と定めるわけです。以下見やすさのために、$X$ の部分集合 $A,B$ について「$B$ が $A$ より完全に下になる」という条件を $B < A$ すなわち、
\begin{equation*}
B < A \quad \Leftrightarrow \quad \forall a \in A \, \forall b \in B \, (b < a)
\end{equation*}
のように略記することにします。こうすると、
\begin{equation*}
\mathbf{A} \preceq \mathbf{B} \quad \Leftrightarrow \quad \forall A \in \mathbf{A} \, \forall B \in \mathbf{B} \, \lnot(B < A)
\end{equation*}
となります。イメージ図にすると次の感じです。
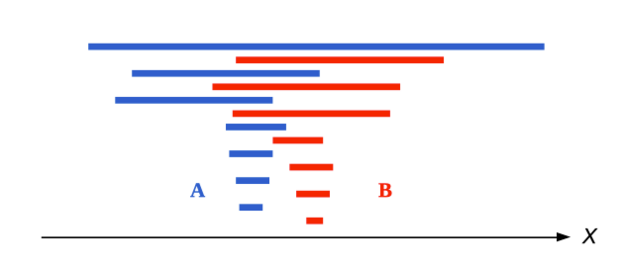
この関係 $\preceq$ は $\mathrm{U}(X)$ 上の全擬順序関係になります。証明は次のとおりです。
[反射律]フィルターの有限交差性から $\mathbf{A} \preceq \mathbf{A}$ は明らか。
[推移律]$\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C} \in \mathrm{U}(X), \ \mathbf{A} \preceq \mathbf{B} \land \mathbf{B} \preceq \mathbf{C} \land \lnot (\mathbf{A} \preceq \mathbf{C})$ と仮定して矛盾を導く。このときある $A \in \mathbf{A}, C \in \mathbf{C}$ が存在して $C < A$ となる。そして任意に $B \in \mathbf{B}$ をとると、
\begin{equation*}
\lnot(B < A) \land \lnot(C < B)
\end{equation*}
が成立する。そこで、
\begin{equation*}
C' = \{ \, x \in X \, \mid \, \exists c \in C \, (x \le c) \, \}
\end{equation*}
と定めると、$C' < A$ だから $C' \notin \mathbf{B}$ であり、かつ $\mathbf{B} \cup \{ C' \}$ は有限交差性を持つ。従って $\mathbf{B} \cup \{ C' \}$ を含むフィルターが存在し、それは $\mathbf{B}$ を真に拡張する。このことは $\mathbf{B}$ が超フィルター(=極大フィルター)であることと矛盾する。
[比較可能律]$\mathbf{A},\mathbf{B} \in \mathrm{U}(X), \ \lnot(\mathbf{A} \preceq \mathbf{B}) \land \lnot(\mathbf{B} \preceq \mathbf{A})$ と仮定して矛盾を導く。このときある $A_1,A_2 \in \mathbf{A}$ と $B_1,B_2 \in \mathbf{B}$ が存在して $B_1 < A_1 \land A_2 < B_2$ となる。フィルターの有限交差性から $a \in A_1 \cap A_2, b \in B_1 \cap B_2$ となる $a,b$ がとれるが、これに対して $b < a \land a < b$ となるから矛盾を生じる。
以上で関係 $\preceq$ が $\mathrm{U}(X)$ 上の全擬順序関係になることが証明できました。推移律の証明に超フィルターであることを使用しています。
2.同値類によって全順序集合を構成する
全擬順序集合 $(\mathrm{U}(X), \preceq)$ から、一般論によって全順序集合を構成することができます。
$\mathrm{U}(X)$ 上に関係 $\sim$ を、
\begin{equation*}
\mathbf{A} \sim \mathbf{B} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{A} \preceq \mathbf{B} \land \mathbf{B} \preceq \mathbf{A}
\end{equation*}
によって定めると、$\sim$ は同値関係です。そこで、商集合 $\mathrm{U}(X) / \sim$ を $\widehat{X}$ とおくと、$\widehat{X}$ 上に自然な順序関係 $\le$ が定まり、$(\widehat{X}, \le)$ は全順序集合になります。以下、$\mathbf{A} \in \mathrm{U}(X)$ を代表元とする $\widehat{X}$ の元を $[ \mathbf{A} ]$ と書きます。
$a \in X$ に対し、$a$ で生成される $X$ 上の単項フィルター $\uparrow a$ は超フィルターですから、$a$ と $[ \uparrow a ]$ を同一視することによって、$X$ を順序を保って $\widehat{X}$ に埋め込むことができます。
これで全順序集合 $X$ を超フィルターを使って全順序集合 $\widehat{X}$ に拡大することができました。
3.何ができあがったのか?
さて、問題はこのようにして作られた全順序集合 $\widehat{X}$ がなにものかということです。
はじめ、$\widehat{X}$ は $X$ の順序完備化になるとばかり思っていました。ところが、完備化の条件である「 $X$ は $\widehat{X}$ において稠密」という命題が、$X$ に自己稠密という条件をつけても、どうにも証明できません。よく考えると次のような反例が存在します。
$X$ を有理数の全体 $\mathbb{Q}$ とし、上の方法で $\widehat{\mathbb{Q}}$ を構成します。無理数 $\gamma$ をひとつとると、$\mathbb{Q}$ の区間 $[x, \gamma)$ の全体は有限交差性を持つので、それらを含む超フィルター $\mathbf{C}_-$ が作れます。同様に $\mathbb{Q}$ の区間 $(\gamma, x]$ の全体は有限交差性を持つので、それらを含む超フィルター $\mathbf{C}_+$ が作れます(少し記号の濫用をしていますが、解釈できると思います)。このとき明らかに $\lnot(\mathbf{C}_+ \preceq \mathbf{C}_-)$ なので $\gamma_- = [\mathbf{C}_-], \ \gamma_+ = [\mathbf{C}_+]$ とおくと、$\gamma_- < \gamma_+$ になります。そして明らかに、$a < \gamma$ なる有理数 $a$ と $\gamma < b$ なる有理数 $b$ に対して、$\widehat{\mathbb{Q}}$ 上で $a < \gamma_- < \gamma_+ < b$ です。つまり $\gamma_-$ と $\gamma_+$ の間には有理数は存在せず、$\mathbb{Q}$ は $\widehat{\mathbb{Q}}$ において稠密ではありません。
$\mathbb{Q}$ を順序完備化すると実数の順序空間 $\mathbb{R}$ が得られますが、この方法で得られた $\widehat{\mathbb{Q}}$ はそれ以上の何か、少なくとも各無理数に対して「下側の無理数」と「上側の無理数」の2つが存在する空間になっています。
さらに、もし $\gamma$ が有理数ならば、同様に作られた超フィルター $\mathbf{C}_+, \mathbf{C}_-$ のほかに単項フィルター $\uparrow \gamma$ が存在して $[\mathbf{C}_-] < [\uparrow \gamma] < [\mathbf{C}_+]$ すなわち $\gamma_- < \gamma < \gamma_+$ となるので、各有理数に対しては「下側の有理数」と「真ん中の有理数」と「上側の有理数」の3つが存在します。
一方で、証明は少し長いので省略しますが、$\widehat{X}$ は順序完備にはなります。すなわち $\widehat{X}$ のデデキント切断 $(A, B)$ には必ず $\max{A}$ または $\min{B}$ のどちらかが存在します。このとき $\max{A}$ と $\min{B}$ の両方が存在し得ることは、先ほどの反例からもわかります。
$X$ が順序群のときに、群演算を $\widehat{X}$ に拡大することができるのか、$X$ が半順序集合のときはどうなるのかなど興味は尽きませんが、まだ自分の頭の中で整理できていませんので、今回はここまでにしておきます。
(続く)
「超フィルター」については、知っている人はよく知っていると思います(知らない方はWikipediaの記事などを参照してください)。コンパクト性の特徴付けや超準解析に使われるなど、色々と面白い性質を持っています。
この超フィルターを使って、全順序集合を拡大することができます。この辺りの話は探せばどこかに論文や記事があると思いますが、練習問題のつもりで自分でやってみたところ、予想に反して何やら奇妙な集合ができあがってきましたので、本記事ではそれを紹介します。
0.予備知識
まず、本記事で用いるフィルターに関する予備知識を列記します。
$X$ を空でない集合とすると、$X$ の部分集合の族 $\mathbf{F} \, ( \neq \emptyset )$ が $X$ の冪集合上のフィルター(本記事では単に $X$ 上のフィルターと言います)であるとは、次の3つの条件を満たすことを言います。
(1) $\emptyset \notin \mathbf{F}$
(2) $A, B \in \mathbf{F} \to A \cap B \in \mathbf{F}$
(3) $A \in \mathbf{F} \land A \subseteq B \subseteq X \to B \in \mathbf{F}$
(1)と(2)から、フィルターから有限個の元をどう取っても、それらの共通部分は空にならないことがわかります。この性質を有限交差性と言います。逆に、$X$ の部分集合の族が有限交差性を持つならば、それらを含む $X$ 上のフィルターが存在します。
ツォルンの補題を使うと、任意のフィルターに対し、それを含む極大フィルターの存在が証明できます。極大フィルターは超フィルターとも呼ばれます。$X$ 上のフィルター $\mathbf{F}$ が超フィルターであることと、次の性質とは同値です。
(4) $A \subseteq X \to A \in \mathbf{F} \lor X \setminus A \in \mathbf{F}$
$X$ の任意の元 $x$ に対し、$x$ を元に持つ $X$ の部分集合の全体は、超フィルターになります。これを $x$ が生成する単項フィルターと呼び、$\uparrow x$ と書きます。$X$ が有限集合ならば $X$ 上の超フィルターは必ず単項フィルターですが、$X$ が無限集合ならば単項フィルターにならない超フィルター(非単項超フィルター)が存在します。
非単項超フィルターは実体がイメージしにくく、存在することはわかっても具体的にビシッと記述することはできませんが、それだけに深掘りすると面白いです。しかし本記事で用いる予備知識としてはここまであれば十分です。
1.超フィルター間に擬順序関係を定める
$(X, \le)$ を全順序集合とします。例えば有理数の順序集合 $(\mathbb{Q}, \le)$ がその一例です。
$X$ 上の超フィルターの全体を $\mathrm{U}(X)$ とし、その元 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ に対して次によって関係 $\preceq$ を定めます。
\begin{equation*}
\mathbf{A} \preceq \mathbf{B} \quad \Leftrightarrow \quad \forall A \in \mathbf{A} \, \forall B \in \mathbf{B} \, \exists a \in A \, \exists b \in B \, (a \le b)
\end{equation*}
つまり「超フィルター $\mathbf{A}$ と $\mathbf{B}$ からそれぞれどのように( $X$ の部分集合である)元 $A,B$ を取っても、$B$ が $A$ より完全に下になることはない」という関係を $\mathbf{A} \preceq \mathbf{B}$ と定めるわけです。以下見やすさのために、$X$ の部分集合 $A,B$ について「$B$ が $A$ より完全に下になる」という条件を $B < A$ すなわち、
\begin{equation*}
B < A \quad \Leftrightarrow \quad \forall a \in A \, \forall b \in B \, (b < a)
\end{equation*}
のように略記することにします。こうすると、
\begin{equation*}
\mathbf{A} \preceq \mathbf{B} \quad \Leftrightarrow \quad \forall A \in \mathbf{A} \, \forall B \in \mathbf{B} \, \lnot(B < A)
\end{equation*}
となります。イメージ図にすると次の感じです。
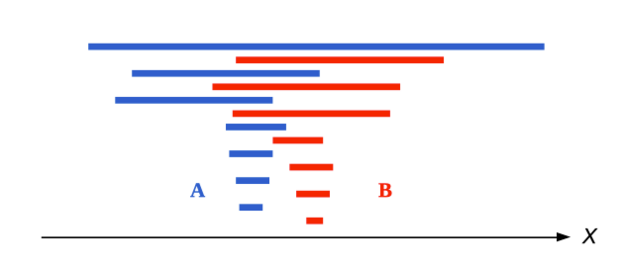
この関係 $\preceq$ は $\mathrm{U}(X)$ 上の全擬順序関係になります。証明は次のとおりです。
[反射律]フィルターの有限交差性から $\mathbf{A} \preceq \mathbf{A}$ は明らか。
[推移律]$\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C} \in \mathrm{U}(X), \ \mathbf{A} \preceq \mathbf{B} \land \mathbf{B} \preceq \mathbf{C} \land \lnot (\mathbf{A} \preceq \mathbf{C})$ と仮定して矛盾を導く。このときある $A \in \mathbf{A}, C \in \mathbf{C}$ が存在して $C < A$ となる。そして任意に $B \in \mathbf{B}$ をとると、
\begin{equation*}
\lnot(B < A) \land \lnot(C < B)
\end{equation*}
が成立する。そこで、
\begin{equation*}
C' = \{ \, x \in X \, \mid \, \exists c \in C \, (x \le c) \, \}
\end{equation*}
と定めると、$C' < A$ だから $C' \notin \mathbf{B}$ であり、かつ $\mathbf{B} \cup \{ C' \}$ は有限交差性を持つ。従って $\mathbf{B} \cup \{ C' \}$ を含むフィルターが存在し、それは $\mathbf{B}$ を真に拡張する。このことは $\mathbf{B}$ が超フィルター(=極大フィルター)であることと矛盾する。
[比較可能律]$\mathbf{A},\mathbf{B} \in \mathrm{U}(X), \ \lnot(\mathbf{A} \preceq \mathbf{B}) \land \lnot(\mathbf{B} \preceq \mathbf{A})$ と仮定して矛盾を導く。このときある $A_1,A_2 \in \mathbf{A}$ と $B_1,B_2 \in \mathbf{B}$ が存在して $B_1 < A_1 \land A_2 < B_2$ となる。フィルターの有限交差性から $a \in A_1 \cap A_2, b \in B_1 \cap B_2$ となる $a,b$ がとれるが、これに対して $b < a \land a < b$ となるから矛盾を生じる。
以上で関係 $\preceq$ が $\mathrm{U}(X)$ 上の全擬順序関係になることが証明できました。推移律の証明に超フィルターであることを使用しています。
2.同値類によって全順序集合を構成する
全擬順序集合 $(\mathrm{U}(X), \preceq)$ から、一般論によって全順序集合を構成することができます。
$\mathrm{U}(X)$ 上に関係 $\sim$ を、
\begin{equation*}
\mathbf{A} \sim \mathbf{B} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{A} \preceq \mathbf{B} \land \mathbf{B} \preceq \mathbf{A}
\end{equation*}
によって定めると、$\sim$ は同値関係です。そこで、商集合 $\mathrm{U}(X) / \sim$ を $\widehat{X}$ とおくと、$\widehat{X}$ 上に自然な順序関係 $\le$ が定まり、$(\widehat{X}, \le)$ は全順序集合になります。以下、$\mathbf{A} \in \mathrm{U}(X)$ を代表元とする $\widehat{X}$ の元を $[ \mathbf{A} ]$ と書きます。
$a \in X$ に対し、$a$ で生成される $X$ 上の単項フィルター $\uparrow a$ は超フィルターですから、$a$ と $[ \uparrow a ]$ を同一視することによって、$X$ を順序を保って $\widehat{X}$ に埋め込むことができます。
これで全順序集合 $X$ を超フィルターを使って全順序集合 $\widehat{X}$ に拡大することができました。
3.何ができあがったのか?
さて、問題はこのようにして作られた全順序集合 $\widehat{X}$ がなにものかということです。
はじめ、$\widehat{X}$ は $X$ の順序完備化になるとばかり思っていました。ところが、完備化の条件である「 $X$ は $\widehat{X}$ において稠密」という命題が、$X$ に自己稠密という条件をつけても、どうにも証明できません。よく考えると次のような反例が存在します。
$X$ を有理数の全体 $\mathbb{Q}$ とし、上の方法で $\widehat{\mathbb{Q}}$ を構成します。無理数 $\gamma$ をひとつとると、$\mathbb{Q}$ の区間 $[x, \gamma)$ の全体は有限交差性を持つので、それらを含む超フィルター $\mathbf{C}_-$ が作れます。同様に $\mathbb{Q}$ の区間 $(\gamma, x]$ の全体は有限交差性を持つので、それらを含む超フィルター $\mathbf{C}_+$ が作れます(少し記号の濫用をしていますが、解釈できると思います)。このとき明らかに $\lnot(\mathbf{C}_+ \preceq \mathbf{C}_-)$ なので $\gamma_- = [\mathbf{C}_-], \ \gamma_+ = [\mathbf{C}_+]$ とおくと、$\gamma_- < \gamma_+$ になります。そして明らかに、$a < \gamma$ なる有理数 $a$ と $\gamma < b$ なる有理数 $b$ に対して、$\widehat{\mathbb{Q}}$ 上で $a < \gamma_- < \gamma_+ < b$ です。つまり $\gamma_-$ と $\gamma_+$ の間には有理数は存在せず、$\mathbb{Q}$ は $\widehat{\mathbb{Q}}$ において稠密ではありません。
$\mathbb{Q}$ を順序完備化すると実数の順序空間 $\mathbb{R}$ が得られますが、この方法で得られた $\widehat{\mathbb{Q}}$ はそれ以上の何か、少なくとも各無理数に対して「下側の無理数」と「上側の無理数」の2つが存在する空間になっています。
さらに、もし $\gamma$ が有理数ならば、同様に作られた超フィルター $\mathbf{C}_+, \mathbf{C}_-$ のほかに単項フィルター $\uparrow \gamma$ が存在して $[\mathbf{C}_-] < [\uparrow \gamma] < [\mathbf{C}_+]$ すなわち $\gamma_- < \gamma < \gamma_+$ となるので、各有理数に対しては「下側の有理数」と「真ん中の有理数」と「上側の有理数」の3つが存在します。
一方で、証明は少し長いので省略しますが、$\widehat{X}$ は順序完備にはなります。すなわち $\widehat{X}$ のデデキント切断 $(A, B)$ には必ず $\max{A}$ または $\min{B}$ のどちらかが存在します。このとき $\max{A}$ と $\min{B}$ の両方が存在し得ることは、先ほどの反例からもわかります。
$X$ が順序群のときに、群演算を $\widehat{X}$ に拡大することができるのか、$X$ が半順序集合のときはどうなるのかなど興味は尽きませんが、まだ自分の頭の中で整理できていませんので、今回はここまでにしておきます。
(続く)



